
被相続人の財産を相続放棄しても、管理義務が発生するケースもあります。管理義務を怠ってしまうと、訴訟沙汰に発展する場合もあるため注意が必要です。
そこでこの記事では、以下の内容を解説していきます。
- 相続放棄と管理義務の関係
- 相続放棄後に相続財産の管理業務を怠るリスク
- 相続放棄後に相続財産の管理業務から免れる方法
相続放棄後の管理業務に関する法改正の内容にも触れるため、これから相続放棄を検討している方はぜひ参考にしてください。
このページの目次
1.【重要】2023年に相続放棄した場合の管理業務について法改正がおこなわれた
2023年4月1日の民法改正により、相続放棄をしたあとの遺産の管理に関するルールが、より明確で分かりやすいものに変更されました。この法改正によって、どのような点が変わり、責任の範囲がどう限定されたのか、4つの大きな変更点を見ていきましょう。
1-1.相続放棄後の管理義務が「保存義務」に変更された
これまでの「管理義務」が、より責任の範囲が限定された「保存義務」へと変更されました。
旧法では、相続放棄をしても、他人の財産を管理するのと同じ、重い注意義務が課されていました。しかし新法では、自分の財産を管理するのと同じ程度の注意を払えば良い、と責任が軽減されています。
たとえば、積極的に修繕をおこなう必要はなく、現状を維持すれば良いと解釈されます。相続放棄をした人の、過度な負担を軽減するための重要な変更です。
1-2.保存業務の責任が生じる人・生じない人の線引きが明確化された
新しい法律では、相続放棄をした人の中で保存義務を負うのは、「その財産を現に占有している人」に限定されることが明確に定められました。これが、今回の法改正で最も大きな変更点の一つです。
たとえば、亡くなった親の実家を相続放棄した場合、その家に住んでいた相続人は保存義務を負いますが、遠方に住んでいて全く関与していなかった相続人は、保存義務を負いません。これにより、誰が責任を負うのか、その対象者が非常に分かりやすくなりました。
1-3.保存業務の責任を負う期間が明確化された
保存義務を負う期間の終わりがいつなのかも、今回の法改正で明確になりました。具体的には、あなたに代わってその財産を管理すべき次の順位の相続人や、後述する「相続財産清算人」に財産を現実に引き渡した時点で、あなたの保存義務は終了します。
これまでは、いつまで責任が続くのかが不明確でしたが、ゴールがはっきりと示されたことで、相続放棄をした人の安心に繋がります。
1-4.相続財産管理人から相続財産清算人に呼称が変更された
相続人が一人も存在しない場合、故人の財産(遺産)を適正に整理・清算するために、「相続財産清算人」が家庭裁判所によって選ばれます。
相続財産清算人の主な役割は、遺産を現金化し、債権者への支払いを済ませたあと、最終的に残った財産を国庫へ引き渡す(帰属させる)などの法的な手続きをおこなうことです。
この「相続財産清算人」という名称は、2023年の民法改正に伴い、従来の「相続財産管理人」から変更されました。これは、財産の清算という役割をより分かりやすく示すためです。
2.相続放棄後に発生する可能性のある管理義務とは?
相続放棄をしたあとに管理義務が発生しうるケースとして、以下の3点が挙げられます。
- 不動産の管理・維持義務
- 相続財産の保管・管理責任
- 債権者からの請求対応
一般的にどういった義務が生じるか、今後の対策として押さえておきましょう。
2-1.不動産の管理・維持義務
まず挙げられる管理義務の一つが、不動産の維持です。たとえば実家で同居していた父が亡くなり、相続が発生したとしましょう。仮に土地や家の所有者が父親だった場合、法務局で相続登記の手続きが必要です。
しかし相続手続きは時間がかかるため、しばらくの間は所有権を持たない家族が土地や家を管理しなければなりません。放置し続けていると、屋根や外壁が破損するなど近隣住民に迷惑がかかる恐れもあるためです。
なお土地や建物における事故は、基本的に無過失責任となります。したがって管理している者は、注意義務を怠った事実がなくても、相手に対して損害賠償を負うのが原則です。
2-2.相続財産の保管・管理責任
民法上では、管理義務が生じる財産を不動産に限定していません。預金や現金、宝石などの動産についても保管・管理責任を負う可能性があります。
ただし、あくまで管理義務を負う者に求めているのは、財産の性質を変えない範囲での保存行為です。預金口座からお金を引き出したり、動産を売却したりすると遺産の使い込みとみなされます。相続放棄ができなくなるほか、訴訟沙汰に発展しかねないため注意してください。
2-3.債権者からの請求対応
管理義務が課せられるケースの一つに、債権者からの請求対応も挙げられます。しかし相続放棄しようと考えている方は、被相続人の財産から借金を返済してはいけません。こうした行為は単純承認とみなされ、相続放棄ができなくなるためです。
ここで説明する債権者からの請求対応とは、自分が相続放棄した旨を相手に伝えることです。具体的には、家庭裁判所から送られてきた「相続放棄受理通知書」を提示しましょう。
債権者側も相続放棄した事実がわかれば、基本的に何度も通知を送ることはありません。相手が理解してくれないときは、弁護士を通して説明してもらうとよいでしょう。
3.相続放棄後に相続財産の管理業務を怠るリスク
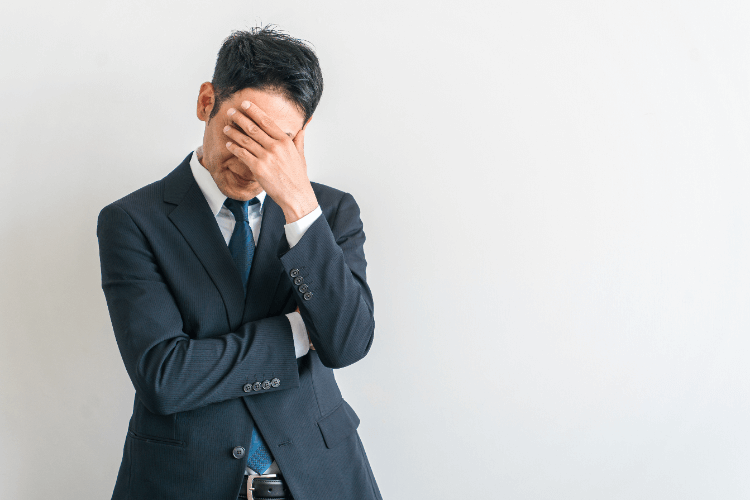
相続放棄後に相続財産の管理業務を怠ると、さまざまなトラブルに巻き込まれやすくなります。ここでは考えられるリスクについて、いくつかまとめていきます。
- 相続放棄が無効になる可能性がある
- 管理義務不履行による損害賠償責任を問われる可能性がある
- 他の相続人とのトラブルが発生する可能性がある
- 無関係な事件に巻き込まれる可能性がある
それぞれ解説します。
3-1.相続放棄が無効になる可能性がある
相続財産をきちんと管理していないと、相続放棄が無効になりうる点に注意が必要です。たとえば現に占有している不動産を、第三者に売却したとしましょう。この場合、法律上は財産を処分したとみなされます。
相続人が財産を処分すると、単純承認とみなされて相続放棄ができなくなります。相続放棄が認められるためにも、財産を使い込んだり、誰かに売却したりしてはいけません。
3-2.管理義務不履行による損害賠償責任を問われる可能性がある
損害賠償責任を問われる可能性がある点も、管理義務を怠るリスクの一つです。先程も説明したとおり、家の一部が破損して近隣住民に迷惑がかかることも考えられます。
主な例として、屋根の一部が落ちて通行人にケガをさせたり、隣人のペットに傷をつけたりケガをさせたりするケースが考えられます。財産の管理を怠っていると、自分の想像している以上に大きなトラブルを起こしてしまうため注意してください。
3-3.他の相続人とのトラブルが発生する可能性がある
管理義務をきちんと果たさなければ、他の相続人とトラブルが発生する可能性もあります。たとえば家を長期間にわたって放置した結果、ほかの相続人や受遺者に渡せないくらいまで劣化したとしましょう。
相続人や受遺者からすれば、家を相続できる権利が失われた状態です。したがって財産を不当に奪われたとして、訴訟沙汰に発展する恐れがあります。
3-4.無関係な事件に巻き込まれる可能性がある
管理義務を果たさないで放置した結果、無関係な事件に巻き込まれる可能性もあります。主な例として挙げられるのが、建物を放置したために詐欺集団が住み着いてしまうケースです。
場合によっては、アジトを管理している者として共犯を疑われてしまいます。こうしたトラブルを防ぐためにも、土地や建物などの財産はしっかりと管理しなければなりません。
4.相続放棄後に相続財産の管理業務から免れる方法

被相続人の相続財産を管理することに、負担を感じる方も少なからずいるでしょう。こういった悩みを抱える方に向けて、相続財産の管理業務を免れる方法を解説していきます。
4-1.相続財産を他の相続人に引き継いでもらう
もし、あなた以外にも相続人がいる場合や、あなたが相続放棄したことで新たに相続人となった人がいる場合は、その人に、財産の管理を現実に引き継いでもらいましょう。
たとえば、第一順位である子が全員相続放棄した場合、第二順位である亡くなった方の親が、新たな相続人となります。その親に対して、実家の鍵を渡すなど、管理を引き継いだことが客観的に分かる形で、財産を引き渡すことが重要です。
4-2.相続放棄後に相続財産清算人を選任する
相続人全員が相続放棄をしたなどで財産を引き継ぐべき相続人が誰もいなくなってしまった場合は、家庭裁判所に「相続財産清算人」の選任を申し立てるのが、保存義務から免れるための唯一の方法です。
相続財産清算人は、相続人に代わって、その財産を法的に管理・清算してくれる専門家です。相続財産清算人に財産の管理を完全に引き渡した時点で、あなたの責任は終了します。
4-2-1.相続財産清算人の選任は義務ではない
相続財産清算人の選任を、家庭裁判所に申し立てることは、法律上の「義務」ではありません。しかし、ほかに財産を引き継ぐ相続人がおらず、あなたがその財産を現に占有している場合は話が別です。相続財産清算人の選任手続きをおこなわない限り、あなたの保存義務は、理論上半永久的に続いてしまいます。
たとえば、老朽化した空き家が倒壊して他人に損害を与えた場合、あなたが賠償責任を問われるリスクが残り続けます。そのため、事実上申し立てが必要不可欠なケースといえます。
4-2-2.相続財産清算人の選任方法
相続財産清算人の選任にかかる申立先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。法律上は、誰でも相続財産清算人の候補者になれます。したがって誰を候補者にするかは、相続人たちで自由に選んでも問題ありません。
とはいえ最終的には、家庭裁判所に相続財産清算人を選任します。相続人たちで選んだ候補者ではなく、司法書士や弁護士が選任されるケースも少なからずあります。
4-2-3.相続財産清算人の選任に必要な書類
手続きするときは、以下の必要書類を揃えないといけません。
- 申立書(家庭裁判所で入手可)
- 被相続人の戸籍謄本(出生〜死亡までの記載のあるもの)
- 被相続人の父母、直系尊属の戸籍謄本(出生〜死亡までの記載のあるもの)
- 被相続人の兄弟姉妹の戸籍謄本(死亡している場合、出生〜死亡までの記載のあるもの)
- 被相続人の住民票除票か戸籍附票
- 被相続人の財産を証明する書類(不動産登記事項証明書、預貯金通帳など)
- 相続財産清算人の候補者の住民票か戸籍附票
上記以外にも、申立人の立場や代襲相続の有無によって、提出が必要になる書類もあります。まずは最寄りの司法書士事務所で、何を揃えるべきかを確認するとよいでしょう。
4-2-4.相続財産清算人の選任にかかる費用
相続財産清算人の選任にかかる費用を表でまとめてみました。
| 費用の内訳 | 金額 |
|---|---|
| 収入印紙 | 800円 |
| 郵便切手 | 1,000円程度 |
| 官報公告料 | 5,075円 |
| 予納金 | 10万〜100万円 |
予納金は、司法書士や弁護士が相続財産清算人になるときに発生する事務費や報酬を指します。具体的な金額については、司法書士事務所や法律事務所で取扱いが異なります。
5.まとめ
相続放棄の管理義務は、2023年の法改正で「保存義務」に改められました。当該法改正により、「現に占有している者」でなければ管理する必要性もなくなりました。
一方で被相続人の実家に住んでいるなど、現に占有している者は引き続き管理義務(保存義務)が課せられます。思わぬトラブルに巻き込まれないためにも、しっかりと財産を管理してください。
どうしても管理が難しいのであれば、相続財産清算人を選ぶことも方法の一つです。候補者として、相続手続きに強い司法書士も選択肢に入れるとよいでしょう。
弁護士法人池袋吉田総合法律事務所では、相続に関する無料相談を受け付けています。相続に関する問題でお困りの方は、ぜひ当事務所までご相談ください。
このコラムの監修者
弁護士法人池袋吉田総合法律事務所は、相続全般、遺産分割、遺留分、相続放棄、生前対策、遺言作成、事業承継、
相続税など、法律のプロとして幅広い案件を取り扱っています。
初回相談は無料です。一人で悩まず、まずは当事務所へご相談ください。

第二東京弁護士会所属





