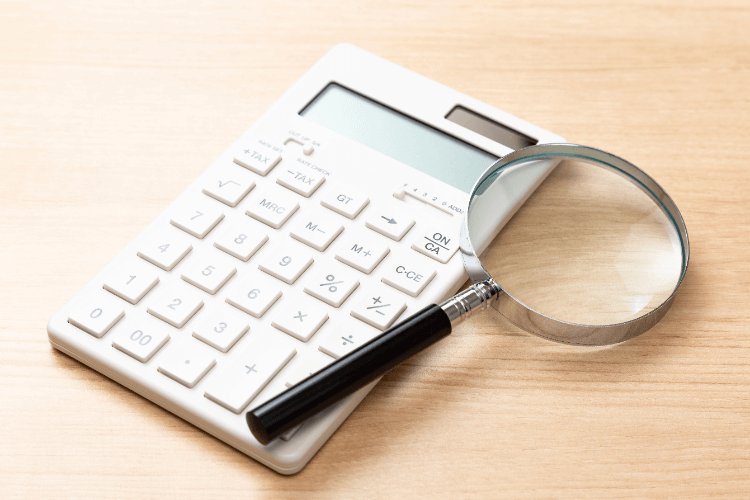
親が死亡し、自分にも一定の財産が分配されると期待していたものの、遺言で1円さえ渡されないケースもあるでしょう。このような遺言書が残されていても、相続人は遺留分として最低額を請求できます。
この記事では、遺留分は必ずもらえるのかを解説するとともに、請求方法もまとめています。相続分が分配されないといったトラブルに巻き込まれており、少しでも財産を請求したい方はぜひ参考にしてください。
このページの目次
1.遺留分は一定の条件を満たすことで「必ずもらえる」

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に分配される相続分の最低額です。もらえる条件と遺留分の割合についてまとめます。
| 相続人(遺留分をもらえる人) | 遺留分の割合 |
| 配偶者と子1人 | 1/4ずつ:法定相続分(1/2)×1/2 |
| 配偶者と直系尊属 | 配偶者1/3:法定相続分(2/3)×1/2直系尊属1/6:法定相続分(1/3)×1/2 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者1/2、兄弟姉妹なし |
| 配偶者のみ | 1/2 |
| 子1人のみ | 1/2 |
| 子2人のみ | 1/4ずつ:法定相続分(1/2)×1/2 |
| 直系尊属のみ | 1/3 |
上記のように、どの程度の遺留分を請求できるかは相続人の構成によって異なります。
1-1.遺留分は遺言書の内容よりも優先される強力な権利
遺言で相続人の一人に財産を渡さないようにしても、遺留分侵害額請求権は消滅しません。遺留分は、遺言書の内容よりも優先すべき権利であるためです。
そもそも民法には、法定相続人に一定の相続分を分配する旨が定められています。そのため法定相続人からすれば、相続によって一定の財産をもらえると期待するでしょう。
その期待を遺言で裏切ってしまうと、相続人同士でトラブルに発展する可能性が高まります。加えて財産が一切分配されない場合、法定相続人の生活が苦しくなる要因にもつながります。
以上の理由により、遺留分は優先的に認められなければなりません。
関連記事:「遺留分は認めない」と遺言で残せる?遺留分請求を防ぐための対策
1-2.ただし「請求」しなければ1円ももらえない
遺留分侵害請求権は、自動的に発生する権利ではありません。自ら請求しなければ、1円ももらえなくなってしまいます。具体的な流れは後述しますが、請求する際には次のプロセスを踏みましょう。
- 直接の話し合い
- 調停
- 訴訟
調停を申し立てるのであれば、手続きする先は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。ただし相手との合意があれば、別の家庭裁判所での手続きも認められています。
1-3.遺留分が「必ずもらえる人」と「もらえない人」
遺留分は、法律上の相続人であれば誰でも必ずもらえるわけではなく、「もらえる人」と「もらえない人」が明確に区別されています。
遺留分は、亡くなった方の財産形成に深く関わってきた近親者の生活を保障するための制度です。そのため、一定の範囲の相続人にのみ、この最低限の取り分を主張する権利が認められているのです。ご自身が遺留分をもらえる立場なのか、それとももらえない立場なのかを正しく知っておくことが、請求の第一歩となります。
1-3-1.遺留分を必ずもらえる人:配偶者、子(孫)、父母(祖父母)
遺留分が必ずもらえる人(遺留分権利者)は、亡くなった方の「配偶者」、「子」、そして「親(直系尊属)」です。
配偶者はどのような場合でも常に遺留分が認められます。子は第1順位の相続人として遺留分が認められます(もし子が既に亡くなっている場合は、その子である孫が権利を引き継ぎます)。
子がいない場合は、第2順位である親(父母)が相続人となり、遺留分も認められます(もし親が亡くなっている場合は祖父母が権利を持ちます)。
1-3-2.遺留分をもらえない人:兄弟姉妹には遺留分はない
遺留分がもらえない人の代表例は、亡くなった方の「兄弟姉妹」およびその代襲相続人である「甥・姪」です。
兄弟姉妹は法律上の相続人(第3順位)にはなりますが、遺留分を主張する権利は法律で認められていません。これは、兄弟姉妹は配偶者や子と比べて、亡くなった方との生活関係が薄いと一般的に考えられているためです。
したがって、たとえば「全財産を妻に相続させる」という遺言書があった場合、故人の兄弟姉妹はそれに不満があっても遺留分を請求できません。
2.遺留分侵害額請求の流れ
一般的に遺留分侵害額を請求する流れは、以下のとおりです。
- 遺留分侵害額を計算する(財産の調査と評価)
- 内容郵便証明で「遺留分侵害額請求」をおこなう
- 調停を申し立てる
- 訴訟を提起する
それぞれの手続きにおいて、注意すべきポイントをまとめます。
2-1.①遺留分侵害額を計算する(財産の調査と評価)
まずはどの程度の遺留分を請求できるか、具体的に計算しなければなりません。財産を計算する際には、以下の書類を探しておくとよいでしょう。
- 被相続人の預金通帳
- 証券会社および信託銀行からの書類
- 登記事項証明書
- 固定資産税評価証明書
- 死亡退職金および最後の給与明細書
とはいえ初心者だけですべての書類を集め、正確に調査することは簡単ではありません。計算ミスによって揉めごとが大きくなる前に、弁護士を雇って対応してもらうのをおすすめします。
2-2.②内容証明郵便で「遺留分侵害額請求」をおこなう
遺産の調査が完了し、相続分の最低額をもらえていない場合は、内容証明郵便で遺留分侵害額請求をしましょう。調停や訴訟の前に、まずは話し合いで解決を試みることが大切です。
口頭での話し合いでも請求自体はできるものの、証拠として残りにくくなってしまいます。証拠の有無で争いが生じないためにも、遺留分侵害額請求書を作成するのがおすすめです。一人で作成するのが難しい場合は、弁護士に頼めば代わりに対応してもらえます。
2-3.③調停を申し立てる
相手と直接話し合いをしても、全く対応してもらえず進展しない場合もあります。解決できないと感じたら、家庭裁判所に調停を申し立てましょう。
調停がスタートすると、双方はそれぞれ別室で待機となります。そのあと交互に調停室へ行くよう指示され、調停委員に意見を主張する形で話し合いを進めます。
要するに調停では、争っている相手と顔を合わせることはありません。議論がヒートアップするリスクが抑えられ、話し合いを前に進めやすくする点がメリットです。
そもそも遺留分は、権利を消滅させる事由がない限り分配しないといけません。相手が頑なに拒んでいても、正当な理由がないのであれば、調査委員の説得によって請求を認めざるを得ないでしょう。
2-4.④訴訟を提起する
調停はあくまで家庭裁判所を通した話し合いであるため、最終的には相手からの合意を必要とします。つまり調停には強制力がなく、場合によっては遺留分を回収できないケースも考えられます。
どうしても解決に至らないときは、最終手段として訴訟を検討しましょう。裁判に勝利できれば、相手から強制的に遺留分を回収できます。
遺留分侵害額請求訴訟は調停前置主義を採用しているため、調停を経ないと提起が認められません。調停と訴訟の順番は、必ず押さえてください。
訴訟では、お互いに弁護士を雇ったうえで戦います。あらかじめ相続トラブルに強い弁護士を調べ、信頼の置ける人に依頼しておきましょう。
3.【要注意】遺留分が「必ずもらえる」とは限らない3つのケース

基本的に必ずもらえる遺留分でも、次の条件に該当したら請求できなくなります。
- 時効が成立してしまった
- 生前に「遺留分放棄」の手続きをしていた
- 「相続欠格」や「相続廃除」に該当する
自分でも気付いていないうちに、これらの条件に当てはまっている可能性もあるため注意が必要です。注意すべき要素を具体的に解説します。
3-1.ケース1:時効が成立してしまった(1年または10年)
時効が成立してしまったら、兄弟姉妹以外の法定相続人でも遺留分を請求できません。遺留分侵害額請求権の時効は、以下のように設定されています。
- 相続の開始及び遺留分の侵害を知った時から1年
- 相続の開始から10年
このように遺留分の請求に関する手続きは、ほとんど時間が与えられていません。後回しにしていると、請求できなくなる恐れもあります。
時効をストップさせたいのであれば、遺留分侵害額請求書を作成し、相手方にきちんと請求しましょう。内容証明などによる請求は「催告」に該当するため、6カ月間は時効の完成が猶予されます。
3-2.ケース2:生前に「遺留分放棄」の手続きをしていた
生前に「遺留分放棄」の手続きをした場合も、遺留分侵害額請求権が消滅する要因の一つです。遺留分を放棄する方法としては、次の2点が挙げられます。
- 家庭裁判所で相続放棄をした
- 遺産分割協議で遺留分放棄に同意した
まず家庭裁判所で相続放棄を申述した場合、遺留分を請求できません。相続放棄は、相続権を自ら手放す手続きであるためです。
また遺産分割協議で「遺留分を放棄する」旨に同意した場合も、基本的に遺留分の請求ができなくなります。後悔しないためにも、よく考えたうえで話し合いに参加してください。
遺留分放棄は、相続が開始する前か後かで手続きが異なります。相続開始前では、遺産分割協議に加え、家庭裁判所から許可をもらわないといけません。一方で相続開始後は、遺産分割協議だけで成立できてしまうため、手続きのタイミングにも注意しましょう。
関連記事:【相続放棄してくれと言われた】5つの対処法や言われたあとの対応手順
3-3.ケース3:「相続欠格」や「相続廃除」に該当する
相続欠格や相続廃除に該当するときも、遺留分侵害額請求権は認められません。これらも相続権が失われる条件に該当するためです。
相続欠格については民法の規定に該当した場合、相続権が自動的に消滅します。相続欠格事由として挙げられるのが次のとおりです。
- 被相続人を相続人が殺害した
- 被相続人が殺害されたのに相続人が告発しなかった
- 詐欺や強迫を用いて遺言書の作成や撤回等を妨げた
- 詐欺や強迫を用いて遺言書の作成や撤回をさせた
- 遺言書の偽造や変造した
一方で相続欠格事由に該当しなくても、相続廃除によって相続権が失われるケースもあります。相続廃除とは、虐待や著しい非行、重大な侮辱があったときに被相続人が家庭裁判所に申し立てることで、相続権を奪う方法です。
相続欠格とは異なり、自動的に効果が発揮されるわけではなく、家庭裁判所が拒否するケースも少なくありません。しかし申し立てが認められると、遺留分の請求ができなくなるため注意しましょう。
4.遺留分に関連してよくあるトラブル
遺留分に関連してよくあるトラブルは、以下のような請求する側とされる側の感情的な対立から生じるものがほとんどです。
- 遺留分侵害額の計算・評価額で揉める
- 遺言書内で遺留分が無視されている
- 相手が請求に応じない・無視する
- 生前贈与が偏っていた
- 兄弟間・親族間の感情的対立が起こる
一つずつ見ていきましょう。
4-1.遺留分侵害額の計算・評価額で揉める
遺留分侵害額の計算・評価額で揉めるのは、最もよくあるトラブルの一つです。遺留分の金額は、相続財産全体の価値をもとに計算されますが、その財産に不動産や自社株といった評価が難しいものが含まれていると、その金額をいくらにするかで必ず対立します。
遺留分請求する側はできるだけ高い評価額を主張し、支払う側はできるだけ低い評価額を主張するため、話し合いが平行線になりがちです。最終的には不動産鑑定士による鑑定や、裁判所の判断が必要になる場合も少なくありません。
関連記事:遺産が不動産しかない場合遺留分の計算や請求方法はどうなる?
4-2.遺言書内で遺留分が無視されている
遺言書内で遺留分が完全に無視されている場合、相続トラブルに発展しやすくなります。
たとえば、「全財産を長男に相続させる」や「財産はすべて愛人に遺贈する」といった内容の遺言書が残されていると、ほかの相続人(配偶者やほかの子)は自身の遺留分が侵害された状態になります。
遺言書で「遺留分を渡さない」と書いても法的な効力はないため、侵害された相続人は遺留分侵害額請求をおこなえます。しかし、感情的なしこりが残り、深刻な対立につながりやすいです。
4-3.相手が請求に応じない・無視する
遺留分侵害額請求をおこなっても、相手方(財産を多くもらった相続人)が請求に応じなかったり、無視したりするのもよくあるトラブルです。
遺留分は自動的にもらえるものではなく、請求の意思表示をして初めて発生する権利です。しかし、相手が「遺言書が絶対だ」と誤解していたり、感情的になって話し合いを拒否したりする場合があります。
この場合、内容証明郵便で請求の証拠を残したうえで、家庭裁判所での調停や訴訟といった法的な手続きに進むしかありません。
4-4.生前贈与が偏っていた
生前贈与が特定の相続人に偏っていた場合、それが遺留分侵害の原因となりトラブルになります。遺留分を計算する際の基礎となる財産には、原則として相続開始前10年以内におこなわれた相続人への生前贈与(特別受益)も含まれます。
たとえば、亡くなる前に長男だけが事業資金として多額の援助を受けていた場合、その金額も遺産に含めて遺留分を計算します。しかし、ほかの相続人がその生前贈与の事実を知らなかったり、証拠がなかったりすると、計算が難航しトラブルの原因になります。
4-5.兄弟間・親族間の感情的対立が起こる
遺留分トラブルは、兄弟間・親族間の根深い感情的な対立を引き起こしやすい問題です。「親の介護を自分だけが負担したのに」「兄は昔から優遇されていた」といった、お金だけでは割り切れない長年の不満や嫉妬が噴出しやすいからです。
一度関係がこじれると、当事者同士での冷静な話し合いは非常に困難になります。法的な権利(遺留分)の主張と、家族としての感情がぶつかり合い、「争族」と呼ばれる深刻な紛争に発展してしまうケースも少なくありません。
5.遺留分の権利を確実にするなら弁護士への相談がおすすめ
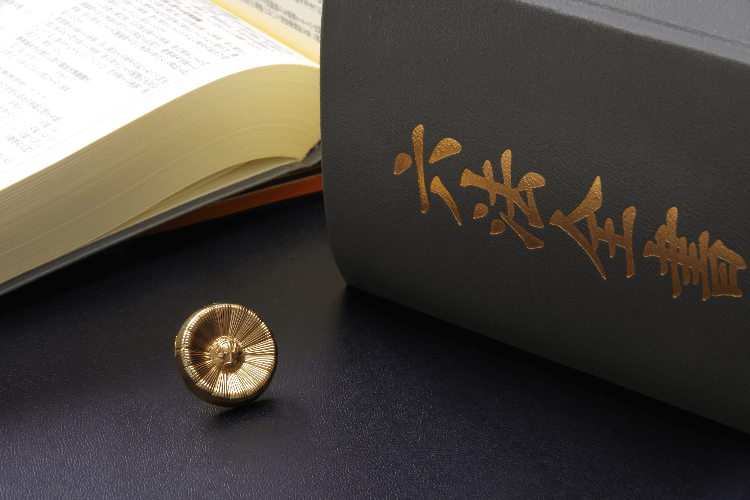
遺留分の権利を確実に実現するなら、法律の専門家である弁護士への相談がおすすめです。弁護士への相談には、以下のようなメリットがあります。
- 正確な財産調査と侵害額の計算を任せられる
- 相手との交渉や法的手続きをすべて代理してもらえる
- 時効の成立を防ぎ、権利を守れる
それぞれ解説していきます。
5-1.正確な財産調査と侵害額の計算を任せられる
弁護士に依頼する大きなメリットは、遺留分計算の基礎となる正確な財産調査と侵害額の計算を全て任せられる点です。
相続財産にはどのようなものがあるか、生前贈与はなかったかなどを調べるのは非常に大変です。弁護士は、相続人の委任を受けて金融機関への照会をおこなうほか、必要資料の提供を求めることができ、必要に応じて不動産鑑定士と連携して評価を進めます(照会先には正当理由があれば回答義務が課されます)。
そして、法律にもとづいて正確な遺留分侵害額を算出してくれるため、根拠のある正当な金額を相手方に請求できます。
5-2.相手との交渉や法的手続きをすべて代理してもらえる
弁護士があなたの「代理人」として、相手方との交渉や法的手続きをすべて代行してくれるため、精神的な負担を大幅に軽減できます。
遺留分の話し合いは家族間だからこそ感情的になり、冷静な交渉が難しいものです。弁護士が窓口となることで、相手方と直接顔を合わせるストレスがなくなります。
また、弁護士は法的な根拠にもとづいて冷静に交渉を進め、もし話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所での調停や訴訟の手続きにもスムーズに移行して対応してもらえます。
5-3.時効の成立を防ぎ、権利を守れる
弁護士に依頼すれば、「知った時から1年」「相続開始から10年」という期間制限(前者は時効、後者は除斥期間)を踏まえ、時効の完成猶予や更新に向けた手続きを適時に管理してもらうことが可能です。
まずは証拠が残る内容証明郵便で催告をおこない、最大6か月の時効完成猶予を確保します。そのうえで、調停申立てや訴訟提起等をおこなって時効を更新します。
内容証明の送付だけでは恒久的な停止にはならない点に注意が必要です。
6.まとめ
遺言などによって被相続人から財産を一切分配されなくても、兄弟姉妹以外の相続人は遺留分を請求できます。自ら請求しなければ、遺留分は分配されません。財産の調査を済ませ、請求できる準備をしましょう。
遺留分を請求する方法は、直接の話し合い、調停、訴訟の3種類があります。まずは相手方と直接話し合い、解決を目指すことが基本です。解決が難しいと感じたら、調停も検討してください。
一方で時効の完成や遺留分放棄、相続欠格事由、相続廃除のいずれかに該当すると、遺留分の請求ができなくなります。
このように遺留分は、ルールが複雑です。一人で悩むのではなく、弁護士と話し合いながら手続きを進めていきましょう。
弁護士法人池袋吉田総合法律事務所では、遺留分をはじめとした相続に関する無料相談を受け付けています。相続に関する問題でお困りの方は、ぜひ当事務所までご相談ください。
このコラムの監修者
弁護士法人池袋吉田総合法律事務所は、相続全般、遺産分割、遺留分、相続放棄、生前対策、遺言作成、事業承継、
相続税など、法律のプロとして幅広い案件を取り扱っています。
初回相談は無料です。一人で悩まず、まずは当事務所へご相談ください。

第二東京弁護士会所属





