
相続で発生する問題として挙げられるのが、別居している親が亡くなり、誰も実家に住んでいないことです。何も考えずに実家を相続してしまうと、人間関係やコストなどでトラブルが発生する恐れがあります。
この記事では実家の相続において、やってはいけないことを詳しく解説します。実家の相続で揉めている、あるいは今後似たようなケースが起こる可能性のある方はぜひ参考にしてください。
このページの目次
1.実家の相続でやってはいけない行動6選

早速、実家の相続でやってはいけない行動として、以下の6つのNG行動を解説していきます。
- 実家の活用方法を決めないままとりあえず相続する
- ほかの相続人と共有名義で相続する
- 相続登記を怠る・放置する
- 無計画に家屋を解体してしまう
- 相続直後に急いで売却する
- 相続税・維持コストをシミュレーションせずに決める
詳しく見ていきましょう。
1-1.実家の活用方法を決めないままとりあえず相続する
まずやってはいけない行為の一つが、実家の活用方法を決めないまま相続することです。活用方法を決めておかないと、結果的に空き家を放置している状態になります。
空き家として放置した場合、特定空き家とみなされて6倍の固定資産税が発生する恐れがあります。相続人の誰かが暮らすのか、第三者に売却するのかをあらかじめ決めておきましょう。
1-2.ほかの相続人と共有名義で相続する
ほかの相続人と共有名義で相続することも、避けたほうが望ましい方法の一つです。たとえば自分の兄弟姉妹と相続した場合、家を自由に使用することが難しくなります。
家を第三者に売却しようと思っても、共有名義人の同意を得なければなりません。管理方法を巡り、トラブルに発展するケースも考えられます。共有名義にするのではなく、単独で誰かが所有したり、家を売却して得た金銭を分配したりする方法も検討してください。
1-3.相続登記を怠る・放置する
実家の相続が面倒だからといって、相続登記を怠ってはいけません。2024年4月より空き家の減少を目指すべく、日本では不動産の相続登記が義務化されました。
相続登記をしないで放置していると、10万円以下の過料が科せられる恐れもあります。行政罰の一種である過料は前科がつかないものの、法律違反に変わりありません。経済的な負担がかかるので、相続するのであれば登記を必ず済ませてください。
1-4.無計画に家屋を解体してしまう
誰も実家を相続しない場合、家屋を解体することも選択肢の一つです。しかし無計画に解体するのは望ましくありません。家屋を解体すると、住宅用地特例が適用されなくなるため、固定資産税は最大6倍まで上がります。
さらに家屋が建てられた当時と現在で、建築基準法が改正されているケースも考えられます。この場合、新しく建物を建てようと思っても、従前の面積で建築できなくなることがあるので注意しましょう。
1-5.相続直後に急いで売却する
実家に住まないからといって、相続直後に急いで売却するのは避けたほうがよいでしょう。相続してから10カ月以内に売却すると、小規模宅地等の特例が適用されなくなるためです。
仮にすぐ売却したとしても、非課税枠を超えた場合は相続税を納めなければなりません。小規模宅地等の特例が適用されれば、相続税の節税につながります。
1-6.相続税・維持コストをシミュレーションせずに決める
実家を相続する際には、相続税や維持コストをシミュレーションすることが大切です。故人の居住用宅地を相続したとき、限度面積330㎡までは小規模宅地等の特例として80%分減額されます。
たとえば面積300㎡かつ評価額3,000万円の居住用宅地を相続しました。この場合に小規模宅地等の特例が適用されると、評価額は240万円です。発生するコストに加え、どの減額制度が適用されるかを細かく調べておきましょう。
2.実家の相続時にやってはいけない行動が招く3大リスク

実家の相続時に前述したような「やってはいけない行動」をすると、以下のようなリスクが生まれます。
- 多額の借金を背負う羽目になる
- 家族・親族間の深刻なトラブルを招く可能性がある
- 税金の増額や行政からの勧告リスクがある
一つずつ解説します。
2-1.リスク①多額の借金を背負う羽目になる
故人の借金の存在を知らないまま遺品を処分するなどして「単純承認」が成立すると、多額の借金を背負うことになるリスクがあります。
故人の預貯金を使ったり、価値のある遺品を売却・廃棄したりすると、法律上、全ての遺産(借金も含む)を相続する意思があると見なされます。そうなると、あとから多額の借金が発覚しても、もう相続放棄はできません。安易な遺品整理が、あなたの人生設計を大きく狂わせる可能性があるのです。
関連記事:【相続後に借金が発覚】泣き寝入りしないための対処法 | 相続放棄はできる?
2-2.リスク②家族・親族間の深刻なトラブルを招く可能性がある
実家の分け方について、口約束だけで済ませたり、安易に共有名義で相続したりすると、将来深刻な家族・親族間のトラブルを招く原因となります。口約束には法的な証拠力がなく、あとから「言った、言わない」の水掛け論になりがちです。
また、共有名義の不動産は、売却やリフォームをおこなう際に、共有者全員の同意が必要となり、一人でも反対すれば何もできなくなってしまいます。その場の感情で安易な決定をすると、子や孫の代まで続く、大きな火種を残すことになりかねません。
関連記事:相続でもめる原因とは?仲の良い家族でも注意したいポイントを解説
2-3.リスク③税金の増額や行政からの勧告リスクがある
誰も住まない実家を、管理もせずに空き家として放置すると、固定資産税が最大6倍に跳ね上がったり、行政から指導や勧告を受けたりするリスクがあります。
「空き家対策特別措置法」により、倒壊の危険などがある「特定空家」に指定されると、住宅用地の税金優遇が解除されてしまいます。また、無計画に家屋を解体した場合も、同様に税金が上がります。
さらに、2024年4月から義務化された相続登記を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性もあります。
3.実家を相続したほうが良いケースもある
実家を誰かに売却するよりも、そのまま相続したほうが望ましいケースもあります。以下のようなケースです。
- 実家にそのまま住む予定があるケース
- 実家や土地の活用方法を決めているケース
今後の生活をイメージしつつ、実家をどう活用するのか決めることが大切です。
3-1.実家にそのまま住む予定があるケース
実家にそのまま住む予定がある人は、相続すると月々の出費を抑えられることがあります。たとえば現在賃貸物件に暮らしている人は、家賃や管理費などを支払わなければなりません。
仮に実家の住宅ローンを支払い終わっていれば、これらの出費がなくなります。また住宅ローンが残っていたとしても、故人が団信(団体信用生命保険)に加入していたら、相続人が返済する必要はありません。
3-2.実家や土地の活用方法を決めているケース
実家や土地の活用方法を決めているときも、自ら相続したほうがよいでしょう。たとえば自身がオーナーとなり、家を誰かに賃貸するケースが挙げられます。ほかにも建物を取り壊しつつ、土地のみを活用する場合も相続が有効です。
4.実家を相続したあとの正しい選択肢4選
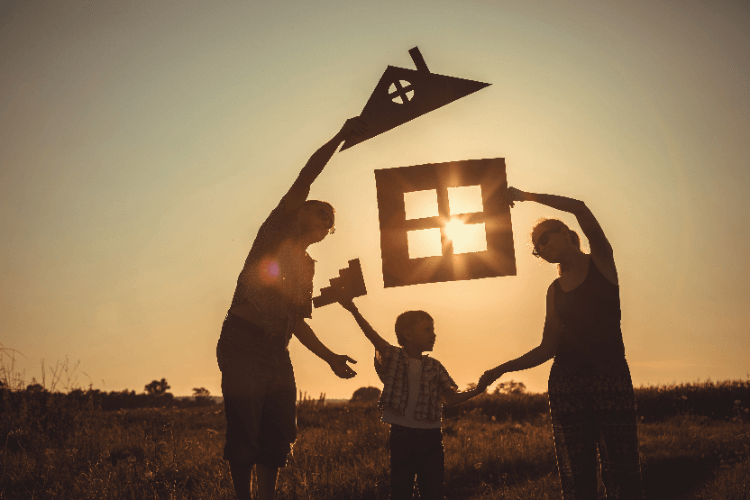
実家を相続した場合に採られる対策として、以下の4点が挙げられます。
- 相続人の誰かが住む
- 賃貸に出して家賃収入を得る
- 建物を取り壊し土地を貸し出す
- 土地活用する
これらを詳しく解説するので、今後対策する際の参考にしてください。
4-1.相続人の誰かが住む
まず一般的な対策として挙げられるのが、相続人の誰かが住むことです。この方法を採用するときは、維持費と相続人間の揉めごとに注意する必要があります。
4-1-1.維持費に注意する
故人の実家に住む際には、維持費に注意しなければなりません。建物が全体的に古くなっていれば、リフォームが必要になるケースもあります。
大規模な修繕が必要になる場合、リフォーム費用も高額になるでしょう。現在の暮らしと比較しつつ、どのくらいのコストがかかるかを押さえることが大切です。
4-1-2.相続人間で揉める原因になる可能性がある
故人の実家を相続すると、相続人間で揉める原因になる可能性があります。自分だけではなく、兄弟姉妹も住みたいと思っているかもしれないためです。
遺言で特別な指定がなければ、遺産分割協議でほかの相続人と話し合う必要があります。話し合いをスムーズに進めるべく、弁護士を間に入れるのをおすすめします。
4-2.賃貸に出して家賃収入を得る
自分で住むだけではなく、賃貸に出して家賃収入を得ることも可能です。ただし効率良く収入を得るには、立地や建物の状況をしっかりと調べなければなりません。
仮に建物の状態が悪く、崩落するなどの事故を起こしたら所有者の責任となります。工作物の管理は無過失責任であるため、リスクが大きくなる点も押さえてください。
4-3.建物を取り壊し土地を貸し出す
故人の実家を相続するうえでは、建物を取り壊して土地を第三者に貸し出すといった選択肢もあります。第三者との間で地上権設定契約を交わしたり、土地の賃貸借契約を結んだりするのが主な例です。
更地にすると固定資産税が6倍まで上がるため、相続税対策も考慮しながら計画を進めていきましょう。
4-4.土地活用する
建物を取り壊したあと、自ら土地を活用するといった方法もあります。主な例として駐車場を経営したり、トランクルームや資材置き場を設置したりするケースが挙げられます。
新しく建物を建築し、アパートやマンション経営する方法もあるので、どのように活用するか決めておきましょう。
5.相続した実家を手放す方法もある
実家を相続したとしても、それを手放すのも考え方の一つです。実家の手放し方としては以下の方法が考えられます。
- 頃合いを見て売却する
- 相続放棄を選択する
- 相続土地国庫帰属制度を活用する
- 寄付や贈与をおこなう
- 空き家バンクに登録する
それぞれ解説します。
5-1.頃合いを見て売却する
不動産を相続するとなると、管理や相続税などの負担が大きくなるケースも珍しくありません。そこで第三者に売却し、得たお金を相続人間で分配する方法があります(換価分割)。
実家を売るには査定してもらい、不動産会社に売却先を見つけてもらうのが基本です。売却先が見つからないと、不動産をいつまでも持ち続けることになるので注意しましょう。
5-2.相続放棄を選択する
故人の財産を引き継ぎたくないのであれば、相続放棄を検討する方法もあります。相続放棄とは、財産を一切相続しないとする意思表示です。相続の開始を知った日から3カ月以内に、家庭裁判所へ申述して効力が発生します。
しかし一度相続放棄を選択したら、原則として自分から撤回することは認められません。不動産以外の資産(預金や宝石など)も受け取れなくなるため、慎重に判断するようにしてください。
関連記事:相続放棄をするなら家の片付けはNG!では家の片付けはどうするべき?
5-3.相続土地国庫帰属制度を活用する
故人から土地を相続するうえで、相続土地国庫帰属制度を活用する方法もあります。こちらは遠方に住んでいるなどの理由により、相続した土地の管理が難しい場合、国に所有権を譲渡する制度のことです。
ただし相続土地国庫帰属制度は、建物が建てられている土地には適用されません。実家の相続において活用したいときは、一度建物を取り壊し、更地にしなければなりません。
5-4.寄付や贈与をおこなう
第三者に贈与したり、自治体に寄付したりすることも方法の一つです。金銭のやり取りになる売却と比べたら、譲渡するハードルは低いといえます。
ただし第三者が見つからず、家を所有し続けないといけなくなる可能性もあります。自治体によっては、寄付制度を設けていないところもあるので注意しましょう。
5-5.空き家バンクに登録する
空き家問題に悩まされている自治体では、空き家バンクを提供しているケースもあります。空き家バンクとは、自治体が譲渡先を見つけてくれるサービスのことです。
譲渡先をじっくりと選べるので、相手が見つからずに困っている方は空き家バンクに登録してみるとよいでしょう。
6.まとめ
家や土地といった不動産は、相続したあとの計画を決めておかないと、思わぬトラブルに巻き込まれる恐れがあります。誰が所有者となるか、今後不動産をどのように使うかを具体的に決めなければなりません。
経済的に難しい場合は、実家を相続または所有しないといった選択肢もあります。判断に迷ったら、弁護士などの専門家に相談してみましょう。
弁護士法人池袋吉田総合法律事務所では、相続に関する無料相談を受け付けています。相続に関する問題でお困りの方は、ぜひ当事務所までご相談ください。
このコラムの監修者
弁護士法人池袋吉田総合法律事務所は、相続全般、遺産分割、遺留分、相続放棄、生前対策、遺言作成、事業承継、
相続税など、法律のプロとして幅広い案件を取り扱っています。
初回相談は無料です。一人で悩まず、まずは当事務所へご相談ください。

第二東京弁護士会所属





