
親の借金を理由に相続放棄したものの、債権者から裁判を提起される人も少なからずいます。適切に対処しなければ、返済を命じられる恐れもあるため注意が必要です。
この記事では相続放棄をした場合において、裁判を提起されたときの対処法を紹介します。相続放棄を検討している方は、今後のトラブルへの備えとして参考にしてください。
このページの目次
1.相続放棄したら被相続人が抱えていた借金返済義務はなくなる
相続放棄をおこなうと、その人は被相続人(亡くなった方)の財産や負債を一切引き継がないことになります。したがって、相続放棄をした人は被相続人の借金を返済する義務を免れます。
しかし、被相続人の借金自体が消滅するわけではありません。相続放棄をした人以外の相続人が、その借金を引き継ぐことになります。
さらに、全ての相続人が相続放棄をした場合、最終的には相続財産清算人が選任され、被相続人の財産を清算し、残った借金があればそれに充てることになります。ただし、相続財産が借金を全て返済できない場合、債権者は未回収のままとなる可能性があります。
このように、相続放棄をすることで自身の借金返済義務は免れますが、他の相続人に負担が移ることになります。そのため、相続放棄を検討する際には、他の相続人との連絡や協力が重要です。
また、相続放棄はプラスの財産も放棄することになるため、慎重な判断が必要です。
関連記事:相続財産に借金があるのを知らなかったときに相続放棄できる条件とは?
2.相続放棄したのに裁判を提起されるケース

相続放棄したにもかかわらず、裁判を提起されるケースとして2種類があります。
- 被相続人の債権者に提訴される
- ほかの相続人に提訴される
具体的にどういったトラブルが想定されるかを解説していきます。
2-1.被相続人の債権者が提訴するケース
まず相続放棄後に提訴する可能性の高い人物の一人が、被相続人の債権者です。債務者が亡くなった場合、債権者は債務者の相続人に対して、貸金返還請求訴訟を提起できます。
本来は推定相続人が相続放棄をすれば、返還請求に応じる必要はありません。ただし債権者側は事実に気づかず、訴訟を提起することが考えられます。
ほかにも相手が「財産を処分したのでは」と疑っている場合、相続放棄の無効が争われることもあります。
2-2.ほかの相続人が提訴するケース
債権者以外にも、ほかの相続人に遺留分侵害額請求訴訟を起こされる恐れもあります。
たとえば被相続人が生きている間に、一部の相続人に対して多額の財産を贈与しました。生前贈与と相続放棄は、本来まったく別の手続きです。したがって生前贈与を受けた人も、相続放棄をすることは認められています。
しかし贈与されていない相続人は、生前贈与を受けていて相続放棄を選ぶ人に不満を抱くかもしれません。そうすれば最低限保証されている遺産(遺留分)を渡すよう、訴訟を提起するケースは十分考えられます。
関連記事:相続で遺留分がもらえないときはどうする?具体的な対処法を解説
3.相続放棄後に裁判所から通知が来たら
債権者やほかの相続人が訴訟を提起する場合、裁判所から通知が届きます。訴訟は、裁判所から通知が来た時点で始まっていると考えてください。
対応をおろそかにしていると、敗訴するリスクも高まってしまいます。自分の財産や生活を守るべく、適切に対処しなければなりません。
3-1.通知の内容を必ず確認する
裁判所から通知が届いたら、その内容を必ず確認してください。通知には、「訴状」や「口頭弁論期日呼出状」といった文言が記載されています。
書面をみれば、なぜ訴訟を提起しているのか、相手は自分に何を求めているかを確認できます。「期日に裁判所へ来なさい」「答弁書を提出しなさい」などの指示にも目を通しましょう。
一方で身に覚えのない請求について記載されている通知が、自宅に送られてくることもあります。この場合、裁判所を騙った詐欺もしくは訴訟を悪用した、架空請求である可能性も否定できません。訴状と実際の生活との整合性を確かめつつ、慎重に対応してください。
3-2.裁判所から通知が来た旨を専門家に相談する
たとえ裁判所から通知が届いても、一人で抱え込んではいけません。弁護士や司法書士といった専門家に相談し、どのように対応すべきかアドバイスをもらいましょう。
一般的に訴訟手続は、弁護士の専門領域ともいえる分野です。経過をひと通り説明すれば、書類作成や出頭といった全ての手続きを任せられます。
また、140万円以下の金銭について争う簡易裁判であれば、司法書士でも代理や和解交渉が可能です。地方裁判所での争いでも、書類作成は対応できます。
3-3.債権者に対しては相続受理通知書を提出する
債権者が貸金返還請求訴訟を提起する場合、相続放棄の事実を認知していないケースも珍しくありません。相続放棄の手続きを完了しているのであれば、家庭裁判所から相続受理通知書が送付されます。こちらは再送されないため、相手に渡すときはコピーのほうを送りましょう。
ほかにも家庭裁判所に申請し、相続放棄受理証明書を示すといった方法も可能です。相続放棄は絶対的な効力が働くので、無効事由に該当しない限りは督促を防げます。
3-4.裁判所に出頭して争う
訴状が届いたのであれば、期日に裁判所へ出頭しなければなりません。とはいえ、基本的に裁判所へ赴くのは代理人である専門家です。尋問を受けたり、和解したりする際に本人へ出頭が命じられることもありますが、その機会も実際にはほとんどありません。
納得のいく判決を得るためには、自分自身の意向を専門家にしっかりと伝えることが大切です。一人で戦おうとせず、専門家と協力し合いながら乗り越えましょう。
4.相続放棄前に裁判所から通知が来たら
相続放棄の期限(熟慮期間)は、被相続人が亡くなったのを知ったときから3カ月以内です。つまり被相続人の死を知るのが遅れれば、相続放棄の手続きをしていないことも考えられます。
このタイミングで債権者から訴状が届いたら、なぜ訴えられているか理解できずに困惑してしまうでしょう。こういったケースにおける対策法を解説します。
4-1.被相続人の財産状況を念入りに調べる
訴状が届いて借金の存在に気づいた場合、焦ってすぐに相続放棄をしようとするかもしれません。しかし、まずは落ち着いて被相続人の財産状況を念入りに調べる必要があります。
たとえ借金を抱えていたとしても、資産がその額を上回っている可能性もあるためです。貨幣だけではなく、不動産や自動車、ブランド品といった財産が隠れていないかも調べましょう。
財産調査は、ほかにも借金がないかを把握するうえでも役立ちます。財産状況を先に調べ、相続放棄を選んだほうが望ましい場合は、家庭裁判所での手続きに移りましょう。
関連記事:【相続後に借金が発覚】泣き寝入りしないための対処法 | 相続放棄はできる?
4-2.訴訟を提起されたあとも相続放棄できる
熟慮期間内であれば、訴訟を提起されたとしても相続放棄は可能です。この場合は、訴訟と相続放棄の手続きを並行して進めないといけません。まずは訴状について対応し、相手が有利な状態で判決が下されないようにしましょう。
裁判所には相続放棄を進める旨の説明をし、なるべく2回目の公判期日を遅らせてもらいます。相続放棄の申述が終了したら、上述した相続放棄受理通知書か証明書を提示しましょう。手続きに問題がなければ、裁判はそのまま終了となります。
5.相続放棄後の裁判で敗訴するケース
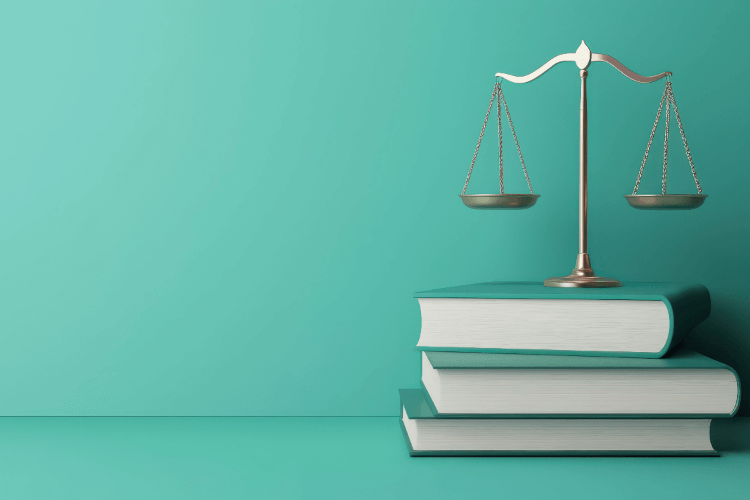
自分では問題なく相続放棄ができたと思っていても、裁判で認められずに敗訴するケースもあります。また相続放棄が正式に受理された場合でも、ほかの原因によって金銭の支払いを命じられることも考えられます。
敗訴する具体例について取り上げるので、裁判で争う人はしっかりと押さえてください。
関連記事:相続放棄後にしてはいけないこととは?認められる行為も解説
5-1.相続放棄の手続きを適切にしていなかった
相続放棄が適切に行われていない場合、家庭裁判所から却下されてしまいます。主な例として挙げられるのが、次の要因に該当するときです。
- 熟慮期間を超過していた
- 財産を処分した
- 書類不備を伝えているのに対応しない
却下の判断が下されると、改めての相続放棄の申述はできません。高等裁判所に対して、2週間以内に即時抗告をする必要があります。
一般的に相続放棄が却下される確率は、0.2%程度とごくわずかです。しかし今後の訴訟にも影響を受けるので、手続きは慎重に進めましょう。
5-2.財産を単純承認してしまった
先程も説明しましたが、財産を単純承認することも相続放棄における無効事由の一つです。どの行為が単純承認とみなされるか、詳しく解説します。
5-2-1.単純承認に該当する例
単純承認に該当するのは、以下の例に挙げられる行為です。
- 被相続人の預貯金を生活費に充てた
- 被相続人の預貯金から債務を弁済した
- 被相続人の不動産や車を売却した
- 被相続人が借りていたアパートを契約した
基本的に、被相続人のお金を使う行為は単純承認と捉えられてしまいます。必要な出費がある場合は、相続人自身の預貯金で対応しましょう。
5-2-2.単純承認に該当しない例
単純承認に該当しない例としては、次の項目が挙げられます。
- 葬祭費や墓石購入費を被相続人の財産から支払った
- (自分が受取人の場合)生命保険金を受け取った
- 遺族年金や死亡一時金を受け取った
ただし葬祭費や墓石購入費については、あまりにも金額が高すぎると、例外的に単純承認とみなされる恐れもあります。専門家に相談したうえで、支払いを進めたほうが賢明です。
5-3.被相続人の連帯保証人になっている
相続放棄をしても、被相続人の連帯保証人になっている場合は弁済をしなければなりません。相続放棄は、あくまで相続財産を引き継がないことを主張する意思表示です。
一方で連帯保証人は、主たる債務者が弁済できないケースにおいて、その金額を肩代わりする制度を指します。要するに連帯保証人も債務を負う立場であり、債権者への弁済にも応じないといけません。
5-4.裁判所からの通知を無視して出頭しなかった
裁判所による通知を無視して裁判に出頭しなかった場合、欠席裁判として扱われます。相手の請求をすべて認めた形となるため、場合によっては多額の賠償金を支払わないといけません。
こうしたリスクを避けるには、裁判所から送付された通知の内容を熟読する必要があります。専門家のアドバイスももらいながら、迅速に対応してください。
6.相続放棄する前に弁護士へ相談しよう
大半の人は訴訟される機会がないため、裁判所から訴状が届くと心に余裕がなくなるでしょう。しかし誰にも相談せず、焦って相続放棄を申述するのは望ましくありません。
まず訴状が届いたら、相続放棄すべきかを弁護士に相談しましょう。経験豊富な人に依頼すれば、自分一人では見つけられなかった解決法を示してくれる可能性もあります。
加えて弁護士に依頼すれば、相続放棄に必要な書類作成を一任できます。仕事や生活で、家庭裁判所での手続きがなかなかできない人にもおすすめです。
7.まとめ
相続放棄をしたのに裁判を提起されたとき、主な対処法は事実を証明することです。家庭裁判所が申述を受理した旨の証明書を用意し、債権者に提示してください。
まだ相続放棄をしていない場合は、財産調査をしたうえで手続きを進める必要があります。相続放棄には注意点がいくつかあるので、弁護士のアドバイスに従いましょう。
弁護士法人池袋吉田総合法律事務所では、相続に関する無料相談を受け付けています。相続に関する問題でお困りの方は、ぜひ当事務所までご相談ください。
このコラムの監修者
弁護士法人池袋吉田総合法律事務所は、相続全般、遺産分割、遺留分、相続放棄、生前対策、遺言作成、事業承継、
相続税など、法律のプロとして幅広い案件を取り扱っています。
初回相談は無料です。一人で悩まず、まずは当事務所へご相談ください。

第二東京弁護士会所属





