
「遺産が実家の不動産しかない」「遺言で全財産を相続した兄弟から『払う現金がない』と言われそう」とお悩みではありませんか?遺留分は法律で認められた権利ですが、遺産が不動産のみだと請求が難航しがちです。
そこでこの記事では、弁護士が以下の内容を解説していきます。
- 遺産が「不動産しかない」場合に遺留分はどうなるのか
- 遺産が不動産しかない場合の遺留分計算の流れ
- 遺産が不動産しかない場合の遺留分侵害額請求の流れ
- 相手(相続人)が遺留分を「現金で払えない」場合の4つの対処法
本来認められている遺留分がもらえないと泣き寝入りする前に、あなたの正当な権利を実現する方法をぜひご覧ください。
このページの目次
1.遺産が「不動産しかない」場合に遺留分はどうなる?
遺産が不動産しかない場合、遺留分の支払いや計算方法はどうなるのでしょうか。詳しく解説していきます。
1-1.遺留分侵害額請求は「金銭(お金)」での支払いが原則
遺留分侵害額請求は、原則として「金銭(お金)」で支払う必要があります。
2019年7月の民法改正以前は、遺留分を侵害された相続人は、不動産の持分(所有権の一部)そのものを返すよう請求できました。しかし、この方法では不動産が共有状態となり、かえって将来のトラブルの原因になりがちでした。
そこで法律が改正され、現在は不動産の持分ではなく、侵害された価値に相当するお金を支払うルールに一本化されています。
1-2.遺留分を計算するためには不動産の評価が必須
遺留分侵害額を計算するためには、遺産である不動産の「評価額」を正確に算出することが必須です。
遺留分の金額は、相続財産の総額をもとに計算されます。遺産が不動産しかない場合、その不動産がいくらの価値があるのかをまず確定させなくてはなりません。
この評価額をめぐって、遺留分を請求する側と支払う側で意見が対立し、トラブルになるケースが非常に多いです。たとえば、請求側は高い価格を、支払う側は低い価格を主張しがちといったケースです。
1-3.遺留分の支払い方法の考案が必要
遺産が不動産しかない場合、遺留分を支払う側は「どのようにして現金を用意するか」という支払い方法を考案する必要があります。不動産を相続した人に十分な預貯金があれば問題ありませんが、そうでない場合は困難が伴います。
たとえば、その不動産に住み続けたい場合は、金融機関からお金を借りる(ローンを組む)方法が考えられます。もし住み続ける必要がない、あるいは借り入れが難しい場合は、不動産そのものを売却して現金化し、その売却代金から遺留分を支払う方法を選択します。
1-4.遺留分侵害額請求をするなら時効に注意
遺留分侵害額請求権には、「遺留分の侵害を知った時から1年間」という非常に短い時効(消滅時効)が存在します。この期間を過ぎると、遺留分侵害額請求権を行使できなくなるため、注意が必要です。
この「1年間」という期間は、遺言書の内容を知ったり、遺留分が侵害されている事実を知った時からカウントが始まります。もしこの1年を過ぎてしまうと、たとえ遺留分を侵害されていても、その権利を主張することはできません。
さらに、相続の開始から10年が経過した場合にも、遺留分侵害額請求権が消滅します。この10年は、遺留分侵害額請求権自体の消滅時効に該当します。早期の対応が求められるため、遺留分侵害を知った際には早急に対応することが重要です。
2.遺産が不動産しかない場合の遺留分計算の流れ
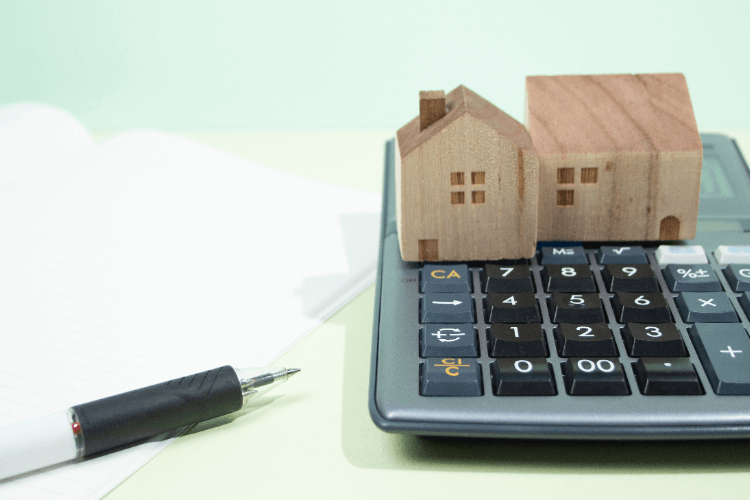
遺産が不動産しかない場合の遺留分計算は、以下の流れでおこなわれます。
- 不動産の基本情報を把握する
- 不動産の現状を確認する
- 不動産鑑定士に評価を依頼する
- 評価方法を選定・算出する
- 鑑定結果を確認し、報告書を受け取る
順を追って解説します。
2-1.不動産の基本情報を把握する
遺留分計算の第一歩は、対象となる不動産の基本情報を正確に把握することです。
まずは、法務局で「登記事項証明書(登記簿謄本)」を取得し、その不動産の正確な所在地(地番・家屋番号)、面積(地積・床面積)、所有者(名義人)を確認します。あわせて、市区町村役場で「固定資産評価証明書」を取得し、固定資産税の基準となる評価額も確認してください。
これらの公的な書類は、不動産の評価をおこなうための基礎資料として不可欠です。
2-2.不動産の現状を確認する
書類で基本情報を把握したら、次は必ず不動産の「現状」を現地で確認します。登記事項証明書に記載された情報と、実際の状況が異なっている場合があるためです。
たとえば、登記上の地目(土地の種類)は「畑」でも、実際には「宅地(家が建つ土地)」として利用されているかもしれません。また、建物がどれくらい古いか(築年数)、修繕は必要か、近隣の環境(日当たり、騒音、駅からの距離など)はどうかをご自身の目で確認します。
これらの情報は、不動産の時価を評価するうえで重要な要素となります。
2-3.不動産鑑定士に評価を依頼する
相続人間で評価額の合意が難しい場合、国家資格を持つ専門家である「不動産鑑定士」に評価を依頼するのが最も客観的で確実な方法です。不動産鑑定士は、現地の状況や市場の動向、法的な規制など、あらゆる要素を総合的に分析し、専門的な見地から公平な評価額(鑑定評価書)を算出します。
鑑定評価書は、当事者間の交渉はもちろん、家庭裁判所での調停や訴訟になった場合にも、客観的な証拠として非常に強い効力を持ちます。
2-3-1.遺留分の計算で使う不動産評価は「時価(実勢価格)」が原則
遺留分の計算で用いる不動産の評価額は、原則として「時価(実勢価格)」です。時価とは、その不動産が市場で実際に売買されるとしたらいくらになるか、という客観的な価格を指します。
相続税の計算で使う「路線価」や、固定資産税の計算で使う「固定資産税評価額」は、時価よりも低い金額に設定されているのが一般的です。そのため、遺留分の計算でこれらの低い価格を使うと、請求できる金額が不当に少なくなってしまいます。
相続開始時点(亡くなった日)の時価を基準にするのが、最も公平な方法とされています。
2-4.評価方法を選定・算出する
不動産の時価を算出する際は、「取引事例比較法」など複数の評価方法から最適なものを選定します。不動産鑑定士は、主に以下3つの評価方法を使い、不動産の特性に合わせて評価額を算出します。
- 原価法
- 取引事例比較法
- 収益還元法
たとえば、住宅地(宅地)の場合は、近隣の類似した土地の実際の売買事例と比較して価格を出す「取引事例比較法」がよく用いられます。
どの方法を選ぶかによっても評価額が変わる可能性があるため、専門的な知識が必要です。
2-5.鑑定結果を確認し、報告書を受け取る
不動産鑑定士による評価が完了すると、その結果をまとめた「不動産鑑定評価書」という正式な報告書を受け取ります。この報告書には、算出された評価額だけでなく、「なぜその金額になったのか」という具体的な根拠や、使用した資料、現地の状況などが詳述されています。
万が一、話し合いがまとまらず、調停や裁判に発展した場合には、不動産鑑定評価書を最も強力な証拠として提出し、ご自身の主張を裏付けることが可能です。
3.遺産が不動産しかない場合の遺留分侵害額請求の流れ
遺留分の計算が完了次第、遺留分侵害額請求に移ります。遺産が不動産しかない場合の遺留分侵害額請求は、以下の流れで進んでいきます。
- 内容証明郵便で「遺留分侵害額請求」を通知する
- 不動産の現金化または代物弁済の方法を検討する
- 話し合いで解決できない場合は調停・訴訟へ
各ステップで何をおこなうべきか、理解を深めましょう。
3-1.内容証明郵便で「遺留分侵害額請求」を通知する
まずは、不動産を相続した相手方に対し、「遺留分を侵害されているので、その分のお金を支払ってください」という意思表示を明確に通知しましょう。
通知は、口頭や普通のメールではなく、「内容証明郵便」でおこなうのが最も確実です。なぜなら、遺留分の請求権には「侵害の事実を知った時から1年間」という短い時効(消滅時効)があるためです。
内容証明郵便であれば、いつ、誰が、どのような内容の請求をおこなったかを郵便局が証明してくれるため、時効の成立を防ぐための確実な証拠となります。
3-2.不動産の現金化または代物弁済の方法を検討する
遺留分侵害額請求の通知をおこなったあとは、相手方の相続人と具体的な支払い方法について話し合います。
遺留分の支払いは「現金(お金)」が原則ですが、遺産が不動産しかない場合、相手方はすぐに現金を用意できないケースがほとんどです。そのため、不動産を売却して現金化し、その売却代金から支払う方法が検討されます。
あるいは、双方が合意すれば、お金の代わりに不動産の所有権の一部(持分)を受け取る「代物弁済」という方法をとる場合もあります。詳しくは後述します。
3-3.話し合いで解決できない場合は調停・訴訟へ
当事者同士の話し合いで不動産の評価額や支払い方法について合意できない場合は、家庭裁判所に「遺留分侵害額の請求調停」を申し立てます。調停は、裁判官と調停委員という中立な第三者が間に入り、話し合いでの円満な解決を目指す手続きです。
もし調停でも話がまとまらない場合は、最終的に「遺留分侵害額請求訴訟」を提起し、裁判所に法的な判断を仰ぐことになります。訴訟では、不動産鑑定士による評価などをもとに、裁判官が支払うべき金額を決定します。
4.相手(相続人)が遺留分をすぐには現金で払えない場合の4つの対処法

不動産を相続した相続人から「すぐには遺留分を現金で払えない」と言われた場合でも、すぐに諦めずに以下のような対処法を検討してみましょう。
- 【交渉】分割払い(支払期限の猶予)を合意する
- 【現物】不動産の「持分(所有権の一部)」で受け取る(代物弁済)
- 【売却】不動産を共同で売却し、売却代金から現金で受け取る
- 【法的手続】家庭裁判所に調停・訴訟を申し立てる
それぞれ解説します。
4-1.【交渉】分割払い(支払期限の猶予)を合意する
相手に一括で支払う現金がなくても、分割であれば支払い能力がある場合は、分割払い(支払期限の猶予)での合意を目指すのが現実的な対処法の一つです。
たとえば、「2年以内に4回に分けて支払う」といった具体的な支払い計画を交渉します。この場合、あとで支払われなくなったというトラブルを防ぐため、合意した内容は必ず「合意書」や「示談書」といった書面に残しましょう。
とくに、強制執行が可能な「公正証書」として作成しておくと、万が一支払いが滞った場合にも安心です。
4-2.【現物】不動産の「持分(所有権の一部)」で受け取る(代物弁済)
相手がどうしても現金を用意できず、あなたも合意するならば、金銭の代わりに不動産の「持分(所有権の一部)」を受け取る「代物弁済」という方法もあります。これは、侵害された遺留分額に相当する不動産の所有権を、相手から譲り受ける形で解決する方法です。
ただし代物弁済を選ぶと、その不動産は相手との「共有名義」になります。将来、その不動産を売却したり利用したりする際に、共有者全員の同意が必要となるため、新たなトラブルの原因になりやすい点には注意が必要です。
4-3.【売却】不動産を共同で売却し、売却代金から現金で受け取る
最も現実的かつ公平な解決方法の一つが、相手方と協力してその不動産全体を第三者に売却し、その売却代金から遺留分に相当する現金を受け取る方法です。この方法であれば、相手方は現金を用意する必要がなく、あなたは現金で遺留分を受け取れます。また、不動産が共有名義になって将来のトラブルの種を残す心配もありません。
ただし、相手がその不動産に住み続けたいと希望している場合は、この方法での解決は難しくなります。
4-4.【法的手続】家庭裁判所に調停・訴訟を申し立てる
分割払いも代物弁済も売却も拒否されるなど、当事者間の交渉で一切の合意が得られない場合は、家庭裁判所に調停や訴訟を申し立てるのが最終的な対処法です。
調停や訴訟であなたの遺留分侵害額請求権が法的に認められ、支払いを命じる判決などが出れば、法的な強制力(債務名義)を持ちます。そもし相手がそれでも支払いに応じない場合は、最終手段としてその判決をもとに相手が相続した不動産を差し押さえ、強制的に競売にかけて現金化し、遺留分を回収する方法も考えられます。
5.遺産が不動産しかない遺留分トラブルは弁護士への相談が必須
遺産が不動産しかなく、現金で支払えないといった遺留分トラブルは、法律の専門家である弁護士への相談が必須です。弁護士へ依頼することで、以下のようなメリットを享受できます。
- 不動産評価額の交渉(鑑定)を有利に進められる
- 相手(相続人)との感情的な対立を避け、冷静な交渉を任せられる
- 調停・訴訟・差し押さえまで見据えた法的手続きを一任できる
一つずつ解説します。
5-1.不動産評価額の交渉(鑑定)を有利に進められる
弁護士に依頼する大きなメリットは、遺留分計算で最大の争点となる「不動産評価額」の交渉を有利に進められる点です。
遺留分を請求する側は評価額を高く、支払う側は低く主張したいため、ここでの対立は避けられません。弁護士は、公平な「時価」を算出するため、提携する不動産鑑定士に正式な鑑定を依頼できます。そして、その客観的な鑑定評価書を法的な根拠として、相手方と交渉をおこないます。
ご自身で不動産業者の簡易査定を集めるのとは異なり、この鑑定評価書は調停や訴訟に発展した際にも、あなたの主張を裏付ける強力な証拠となります。
5-2.相手(相続人)との感情的な対立を避け、冷静な交渉を任せられる
弁護士へ依頼すれば、弁護士があなたの「代理人」として窓口になるため、相手と直接やり取りする必要がなくなり、感情的な対立を避けられます。
遺産相続、とくに遺留分の話し合いは、金銭の問題だけでなく、「なぜ自分だけが少ないのか」といった過去の不満や感情が噴出しがちです。家族同士だからこそ冷静な話し合いができず、関係が悪化するケースは少なくありません。
弁護士が間に入ることで、あなたは精神的なストレスから解放されます。そして、弁護士は法的な論点に絞って冷静に交渉を進めてくれるため、円満かつ現実的な解決を目指せます。
5-3.調停・訴訟・差し押さえまで見据えた法的手続きを一任できる
当事者間の話し合いで解決しない場合、弁護士に依頼していれば、家庭裁判所での調停や訴訟といった法的な手続きの全てを一任できます。
弁護士は、交渉が決裂した場合の次の手段を常に見据えて活動しています。家庭裁判所への調停申立てや、訴訟になった場合の代理人として、あなたの権利を法的に主張・立証してくれます。さらに、もし裁判で勝訴しても相手が支払いに応じない場合には、最終手段として不動産を「差し押さえ」、強制的に競売にかけて現金化するといった手続きも可能です。
6.まとめ
遺産が不動産しかない場合の遺留分請求について、不動産の評価方法から、相手が「現金で払えない」場合の対処法まで詳しく解説しました。
遺留分は金銭での請求が原則ですが、相手に現金がない場合、分割払いの交渉や不動産持分での受け取り、不動産の売却といった現実的な解決策を模索する必要があります。
しかし、時効も迫る中、最大の争点である不動産の評価などで当事者同士の解決は困難を極めます。あなたの正当な権利を確実に実現するため、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
弁護士法人池袋吉田総合法律事務所では、遺留分をはじめとした相続に関する無料相談を受け付けています。相続に関する問題でお困りの方は、ぜひ当事務所までご相談ください。
このコラムの監修者
弁護士法人池袋吉田総合法律事務所は、相続全般、遺産分割、遺留分、相続放棄、生前対策、遺言作成、事業承継、
相続税など、法律のプロとして幅広い案件を取り扱っています。
初回相談は無料です。一人で悩まず、まずは当事務所へご相談ください。

第二東京弁護士会所属





