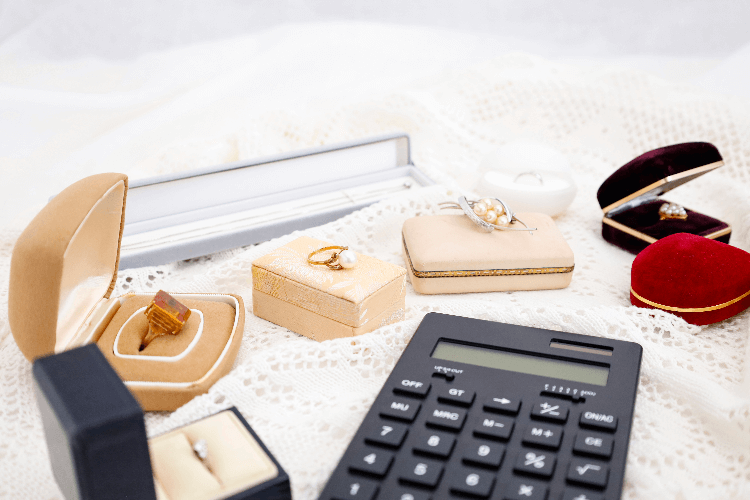
相続手続きにおいて、相続人とトラブルのきっかけにつながりやすいのが遺産の使い込みです。遺産使い込みの発覚があまりにも遅れた場合、時効によって訴訟する権利を失う恐れがあります。
この記事では、遺産の使い込みと時効の関係について紹介します。併せて使い込みの事実に気づいたときの対処法にも触れるので、相続トラブルに備えたい人はぜひ参考にしてください。
このページの目次
1.そもそも遺産の使い込みとは
遺産の使い込みとは、被相続人が遺した財産を、他の相続人の同意を得ずに(または遺産分割協議が終わる前に)一部の相続人や第三者が勝手に消費したり処分したりしてしまう行為です。
1-1.遺産の使い込みに該当するケース
遺産の使い込みには、たとえば以下のような行為が該当します。
- 被相続人の預金口座からお金を全額引き出し、自身の生活費に使う
- 被相続人名義の家や土地、株などを勝手に売却し、その代金を自分のものにする
- 価値のある美術品や貴金属などを勝手に売却・処分する
被相続人の遺産をどのように分配するかは、遺言や遺産分割協議で決定します。何も決定していない状態で勝手に遺産を使い込むことは許されません。
1-2.遺産の使い込みと処罰の関係
遺産の使い込みは、事実を証明できたとしても罪に問えないケースがあります。
刑法にて「親族相盗例(しんぞくそうとうれい)」という規定が定められており、配偶者、親子、祖父母と孫、または同居している親族の間での窃盗罪や横領罪などは、刑が免除される(処罰されない)と定められているためです。
しかし、これは全てのケースで処罰されないという意味ではありません。たとえば、同居していない兄弟姉妹間などの場合は、被害を受けた親族からの告訴があれば処罰の対象となりえます。
また、民事上の返還義務は、刑事処罰の有無とは全く別の問題として発生します。
2.遺産の使い込みに関する時効は2通り

自分以外の相続人による遺産の使い込みが発覚したら、損害賠償請求権や不当利得返還請求権を行使できます。しかしこれらの手続きは、時効が存在するので注意しなければなりません。それぞれの時効期間について解説します。
2-1.損害賠償請求をする場合の時効は3年
損害賠償請求とは、不法行為によって生じた損害の補償を求める訴訟です。損害賠償請求においては、消滅時効の期間が2種類あります。
| 損害または加害者を知っているか | 期間 |
| 知っている(主観的期間) | 知ったときから3年 |
| 知っていない(客観的期間) | 不法行為のときから20年 |
これらの期間が経過してしまうと、原則として訴訟を提起できません。ただし、相手が損害賠償責任を承認すれば時効の更新が適用され、期間は再びゼロからカウントされます。
2-2.不当利得返還請求権を行使する場合の時効は5年もしくは10年
損害賠償請求以外にも、加害者に対して不当利得返還請求権を行使できます。不当利得返還請求とは、法律上の権利がなく利益を受けた人に対して、その分の返還を求める手続きです。時効の期間は、以下のように設定されています。
| 使い込みについて知っているか | 期間 |
| 知っている(主観的期間) | 知ったときから5年 |
| 知っていない(客観的期間) | 使い込みの日から10年 |
主観的期間は損害賠償請求権よりも長いものの、客観的期間は短くなっているため注意してください。
3.遺産の使い込みは証明が難しい
時効までに解決が必要な遺産の使い込みですが、以下のような理由から証明が難しいと言われています。
- そもそも使い込みに気付きにくい
- 使い込みの証拠収集は難易度が高い
- 使い込まれた総額を特定しにくい
- 使い込んだ本人が事実を認めないことが多い
それぞれ解説していきます。
3-1.そもそも使い込みに気付きにくい
遺産の使い込みは、他の相続人からは気づかれにくいものです。とくに、亡くなった方(被相続人)の預金通帳を家族の一人が管理していたような場合、その発見は一層難しくなります。
主な理由として、日常的な生活費の支払いとの区別があいまいになりやすい点が挙げられます。たとえ不自然に多額の引き出しがあったとしても、「本人の生活のために使った」と説明されると、それ以上問い詰めるのが困難になることがあります。
また、疑問を感じたとしても、「まさか家族がそんなことをするはずがない」という信頼感が、使い込みの発見を遅らせる要因になることも少なくありません。
3-2.使い込みの証拠収集は難易度が高い
話し合いや訴訟で解決に持っていくには、証拠集めに力を入れる必要があります。しかし家族の一人が被相続人の通帳を管理していたのであれば、どのくらいの金額が使い込まれたかを特定するのは困難です。
預金が多めに引き出された形跡があっても、必ずしも全額が使い込まれたとは限りません。また被相続人が通院していた場合は、保存期間が過ぎ記録を処分されている可能性もあります。
決定的な証拠が見つからず、話し合いや訴訟に踏み込めない状態が続くことも考えられるのです。
3-3.使い込まれた総額を特定しにくい
遺産を使い込まれた可能性が高くても、実際にいくら使い込まれたのか、その正確な総額を特定するのは非常に難しいです。これは、被相続人の生前の財産管理状況やお金の流れを全て正確に把握するのが困難なためです。
たとえば、同居していた家族が長年にわたり預貯金を管理していたケースでは、日常的な生活費の支払いと不当な使い込みとの線引きがあいまいになります。領収書などの客観的な証拠が残っていなかったり、金融機関での取引履歴の保存期間が過ぎていたりすると、過去に遡って使い込みの全容を解明するのはさらに難しくなります。
3-4.使い込んだ本人が事実を認めないことが多い
遺産を使い込んだと疑われる本人が、その事実をなかなか認めないケースが多いのも、使い込みの証明を難しくする大きな要因です。使い込みを認めてしまうと、他の相続人に対して返還する義務が生じるため、それを避けるために事実を認めないことが多いです。
また、「被相続人の介護や生活のために必要だった」「生前にもらったものだ」といった主張をして、自身の行為を正当化しようとすることも少なくありません。明確な証拠がない限り、本人が否定し続けると、話し合いだけで解決するのは難しくなってしまいます。
4.遺産の使い込みに気づいたときの対処法

遺産の使い込みに気づいたら、なるべく早めに数々の対処法を講じる必要があります。きちんと取り戻すためにも、以下の順を追って対処してください。
- いつ・どのくらい使われているかを調査する
- 本人と直接返還するように話し合う
- 遺産分割調停を検討する
- 訴訟を提起する
一つずつ解説していきます。
4-1.いつ・どのくらい使われているかを調査する
いきなり本人と話し合う前に、遺産がいつ・どのくらい使われているかを調査しましょう。証拠をしっかりと押さえ、泣き寝入りするのを防ぐためです。調査には預金口座の履歴確認と裁判所の照会制度の2種類があります。
4-1-1.被相続人の預金口座の履歴をチェックする
まずは被相続人の預金口座の履歴から、いつ・どのくらい動きがあるかを確認しなければなりません。紙の通帳が手元にある場合は、不当にお金が引き出されていないかを調べましょう。オンライン通帳であれば、あらかじめログイン情報を把握する必要があります。
しかし親族の通帳といえども、調査を素人だけで進めるのは難しいでしょう。そのため家族だけでするのではなく、財産調査に強い弁護士を頼るのをおすすめします。金融機関に対してもやり取りしてくれるため、正確な情報を入手できる点が強みです。
4-1-2.裁判所の照会制度を利用する
被相続人の口座については、弁護士に依頼するだけである程度調査できます。一方で相続人や第三者の口座情報は、プライバシーのため金融機関も教えてくれません。相手が自分の口座にタンス預金のお金を入れたら、証拠を掴むのが難しくなるでしょう。
相続人や第三者の口座情報を知りたいのであれば、裁判所の照会制度を利用するのがおすすめです。ただし、損害賠償請求や不当利得返還請求を提起していることが前提となります。
4-2.本人と直接返還するように話し合う
財産調査により使い込みの事実が発覚したら、まずは本人(犯人)と直接話し合いましょう。相手が使い込みの事実を認めれば、遺産分割協議書に記載したうえで遺産分割協議に進みます。
とはいえ直接話し合うだけでは、相手も正当な理由で使ったと言い逃れようとする恐れがあります。話が前に進まないときは、次のステップとして遺産分割調停や訴訟を念頭に置いてください。
4-3.遺産分割調停を検討する
相続が開始したあとに遺産の使い込みが発覚したときは、遺産分割調停も検討するとよいでしょう。調停委員会を間に立たせて、遺産分割の問題を話し合いで解決します。
調停を申し立てるには、使い込みの疑いのある人を除いた相続人の同意が必要です。あくまで話し合いがベースとなるため、合意がまとまらない可能性もあります。
解決に至らないときは、遺産分割審判へ移ります。こちらは、裁判所が遺産分割の方法を決める手続きです。調停から審判まで、数ヶ月程度の期間がかかります。
4-4.訴訟を提起する
話し合いで全く解決しないときは、訴訟を提起するのが一般的な流れです。損害賠償請求訴訟も不当利得返還請求訴訟も、簡易裁判所または地方裁判所で手続きします。
訴訟のメリットは、相続争いについて終局的な決着がつく点です。たとえ相手が頑なに認めていなくとも、確固たる証拠を提出すれば勝訴できる可能性も高まります。
一方で裁判費用や弁護士費用を用意しなければならず、経済的に負担がかかるところがデメリットです。
関連記事:遺産の使い込みが発覚したら?泣き寝入りしないための対処法
5.他人に遺産を使い込まれるのを防ぐには
一度相続人や第三者に遺産を使い込まれると、これらを取り戻すのは難しいのが現状です。そのため、以下のような方法で遺産の使い込みを未然に防ぐ必要があります。
- 家族信託を利用する
- 後見制度・任意後見制度を活用する
- 預貯金口座を凍結する
それぞれ見ていきましょう。
5-1.家族信託を利用する
被相続人の財産を管理する際には、家族信託の利用を検討してみましょう。家族信託とは、信頼の置ける人に財産をすべて管理させる制度です。
受託者が財産を管理していれば、ほかの相続人や第三者に使い込まれる心配もなくなります。ただし受託者本人が、財産を使い込む危険性は否定できません。
家族信託を利用するときは、被相続人の生前からしっかりと話し合い、誰に管理を任せるかを慎重に決めましょう。
5-2.後見制度・任意後見制度を活用する
後見制度や任意後見制度も、遺産を守るうえで役立ちます。それぞれの制度の特徴は以下のとおりです。
- 後見制度:本人が重度の認知症を患ったとき、後見人が財産を管理する
- 任意後見制度:将来後見人となる人をあらかじめ選んでおく
後見人(任意後見人)には、親族以外にも弁護士や公益法人も選べます。財産を確実に守れる方法を選び、第三者が遺産を使い込みできないようにしましょう。
5-3.預貯金口座を凍結する
被相続人が亡くなったら、その時点で預貯金口座を凍結することも大切です。凍結の手続きさえ済ませておけば、第三者が勝手にお金を引き出すリスクもなくなります。
使い込みにつながりうる要素は、一つでも多く減らしておきましょう。
6.自分が遺産を使い込んでしまった場合はどうする?
もしご自身が、被相続人の遺産を使い込んでしまった場合、まずは正直に事実と向き合い、できるだけ早く誠実に対応することが大切です。後ろめたさや発覚を恐れる気持ちから問題を放置してしまうと、家族関係が修復困難になったり、法的なトラブルに発展したりするリスクが高まります。
以下のような流れで、事態を収拾しましょう。
- いつ、いくら、何のために遺産を使い込んだのか、可能な限り正確にまとめる
- ほかの相続人へ正直に告白し、謝罪する
- 使い込んでしまった遺産の返還方法を協議する
- 遺産分割協議で最終的な調整をおこなう
もし使い込みの事実を隠し通そうとしたり、話し合いに応じなかったりした場合、他の相続人から不当利得返還請求や損害賠償請求といった法的な手続きを起こされる可能性があります。悪質なケースでは、横領罪などの刑事責任を問われる可能性もゼロではありません。
スピード感を持って、なるべく早く解決へと動いてください。
7.遺産の使い込みは弁護士にすぐ相談しよう
遺産の使い込みが発覚したら、訴訟の提起も念頭に置かないといけません。そのため素人だけで対応せず、はじめから弁護士に相談するのをおすすめします。
弁護士に依頼するメリットは、調査から訴訟手続きまでのほとんどを代理できる点です。仕事や私生活で忙しいタイミングでも、トラブル解決に向けた手続きを進められます。
法律事務所によっては、無料相談を受け付けてくれるところもあります。無料相談を生かしつつ、弁護士の実績と人柄をチェックしましょう。
8.まとめ
遺産を使い込んだ相手と争うには、損害賠償請求訴訟や不当利得返還請求訴訟がありますが、どちらも時効が適用されます。長期間手続きに着手していないと、消滅時効が完成して争えなくなる恐れもあります。
権利を失わないようにするには、使い込みの事実が発覚したら迅速に対処しなければなりません。しかし証拠も確保しなければならず、素人だけで解決を目指すのは難しいでしょう。
解決につなげるためには、問題が発生したタイミングで弁護士に相談することをおすすめします。決して一人だけで悩まないでください。
弁護士法人池袋吉田総合法律事務所では、相続に関する無料相談を受け付けています。相続に関する問題でお困りの方は、ぜひ当事務所までご相談ください。
このコラムの監修者
弁護士法人池袋吉田総合法律事務所は、相続全般、遺産分割、遺留分、相続放棄、生前対策、遺言作成、事業承継、
相続税など、法律のプロとして幅広い案件を取り扱っています。
初回相談は無料です。一人で悩まず、まずは当事務所へご相談ください。

第二東京弁護士会所属





