
同じ相続人に対して遺留分を請求したところ、反対に相手からは寄与分を主張されて困っている方もいるでしょう。遺留分と寄与分は関係が複雑であるため、相続手続き時に揉める要因となります。
そこでこの記事では、以下の内容を解説します。
- 遺留分とはなにか
- 寄与分とはなにか
- 遺留分と寄与分の関係
- 【ケース別】遺留分と寄与分がぶつかったときの計算方法
遺産分割において、遺留分と寄与分について悩まされている方は、ぜひ参考にしてください。
このページの目次
1.遺留分とは?
遺留分とは、亡くなった人の財産を相続する際に、一定の相続人が最低限受け取れる取り分を法律で保障する制度です。民法第1042条から定められています。
たとえ遺言書で「全財産を特定の人に相続させる」と書かれていても、配偶者や子ども、直系尊属といった法定相続人には、生活の安定を守るために一定の取り分が認められています。
ここからは、具体的な制度の内容について解説していきます。
1-1.遺留分が認められる人
遺留分を主張できるのは、以下のような「兄弟姉妹を除く法定相続人」です。
- 配偶者(夫または妻)
- 子(実子・養子・代襲相続人を含む)
- 直系尊属(父母・祖父母など)
この制度は、被相続人の死後に残された家族の生活を守るため、相続人が最低限の財産を受け取れるようにする目的で設けられています。
一方兄弟姉妹や甥・姪には、被相続人との生活的・経済的な結びつきが比較的薄いと考えられるため、遺留分侵害額請求権は認められていません。また、配偶者と子が相続人となる場合には、直系尊属(親など)は相続人にならないため、当然ながら遺留分を請求することはできません。
さらに、自分が本来相続人であっても、相続放棄や遺留分放棄をしている場合、または欠格や廃除によって相続権を失った場合には、遺留分を請求することはできません。つまり、遺留分を主張するためには、相続人としての地位を有していることが前提条件となります。
1-2.遺留分の計算方法
遺留分の計算方法は、相続人によって異なります。
| 相続人 | 計算方法 |
| 配偶者のみ | 法定相続分×2分の1 |
| 子のみ | 法定相続分×2分の1 |
| 配偶者と子 | 法定相続分×2分の1 |
| 配偶者と直系尊属 | 法定相続分×2分の1 |
| 直系尊属のみ | 法定相続分×3分の1 |
たとえば配偶者と長男、次男の3人で相続したときを想定してみましょう。被相続人には1,000万円の財産がありましたが、遺言書には長男に一切相続させない旨の記載が残されていました。
本来であれば、長男の法定相続分は「1,000万円×4分の1」で250万円です。遺留分はその額に2分の1を乗じるため、最低限の金額として125万円まで請求できます。
一方で900万円の財産を、配偶者と被相続人の母親で分配するケースも見ていきましょう。そもそも配偶者と直系尊属の法定相続分は、それぞれ3分の2と3分の1です。直系尊属の法定相続分は300万円であるため、遺留分を計算する際にはさらに2分の1を乗じる必要があります。したがって最終的に請求できる遺留分の額は、150万円です。
1-3.遺留分侵害額請求について
条件を満たしていても、自動的に遺留分の分配が認められるわけではありません。遺留分を請求するには、ほかの相続人と話し合いで解決するか、家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。
ほかの相続人と直接話し合うのであれば、内容証明郵便を活用しましょう。請求した記録がきちんと残ることで、民法150条により完成を最大6か月「猶予」する効果があります。(猶予期間中に調停・訴訟等で時効を更新する手続きが必要です。)
話し合いでも解決できない場合は、相手の住所地を管轄する家庭裁判所に調停を申し立てましょう。調停委員を介して話し合う形となるため、揉めごとが解決しやすくなります。調停でも決着がつかなければ、訴訟で遺留分を争うことも可能です。
2.寄与分とは?
寄与分とは、被相続人の財産の維持もしくは増加に特別な寄与をした相続人に対し、貢献度に応じて振り分けられる増額分です。
たとえば父親が会社を経営しており、従業員ではない長男が無償で手伝いをして、事業に貢献していましたケースなどです。この場合は長男に寄与分が認められ、ほかの相続人よりも多く財産が分配される可能性があります。
ここでは寄与分をより詳しく説明すべく、基本的な考え方と計算方法をみていきましょう。
2-1.寄与分の基本的な考え方
寄与分の基本的な考え方は、法定相続分どおりに分けるのが不公平になるほどの「特別な貢献」をした相続人に、その貢献に見合った財産を上乗せするというものです。この制度が認められるのは、あくまで法律上の「相続人」に限られます。
たとえば、長男の妻が介護をしても、長男の妻は相続人ではないため、この寄与分制度は主張できません(※ただし、別途「特別寄与料」という制度があります)。また、単なる親孝行レベルの貢献では認められず、通常期待される以上の特別な貢献である必要があります。
2-2.寄与分の計算方法
寄与分の計算方法は、法律で「いくら」と決まっているわけではありません。まずは相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で決めるのが原則です。
もし話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所の調停や審判で決めてもらうことになります。裁判所では、たとえば介護が理由であれば「(介護報酬の相場)×(日数)×(裁量割合)」といった計算式をもとに、貢献度を客観的に評価します。
ただし、貢献したと主張する側が、その事実を証明する証拠(日記や領収書など)を提出しなければなりません。
3.遺留分は寄与分によって侵害されない
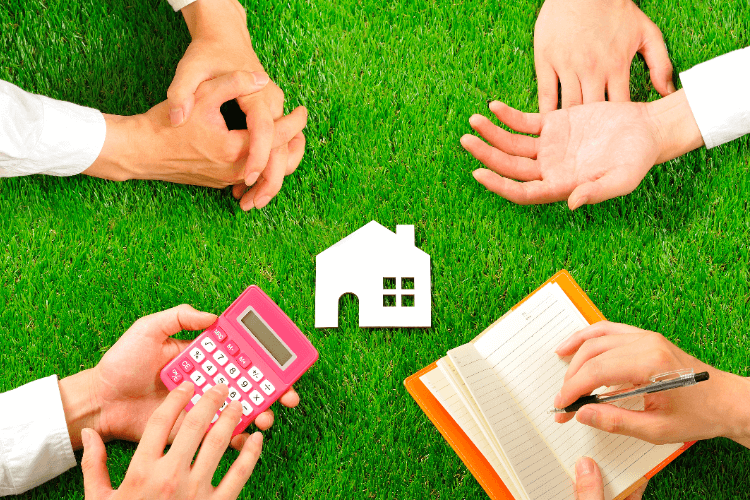
特定の相続人に寄与分が認められた場合、自身の遺留分は請求できるか不安に感じる方もいるでしょう。しかし遺留分が寄与分によって侵害されることはありません。これらの仕組みについて詳しく解説します。
3-1.遺留分の計算において、寄与分は考慮(控除)されない
基本的に寄与分を定めるうえで、ほかの相続人の遺留分を侵害するほど、高額な金額を設定しても違法ではないとされています。したがって高額な寄与分を設定する行為自体は、法律的には問題ありません。
しかし遺留分の計算では、寄与分は考慮されないとするのが一般的な見解です。そのため特定の相続人に対し、あまりにも多額の財産を寄与分として渡す行為は、現実的には認められにくいといえます。
3-2.なぜ寄与分より遺留分が優先されるのか?
寄与分より遺留分が優先される理由は、相続人の生活を保障するといった狙いがあるためです。
たとえば父親と母親、子どもで構成された家族がいました。仮に父親が死亡した場合、残された家族は今後自分たちの力で生活しなければなりません。そのため財産を公平に分配し、誰一人困窮する者を出さないようにするのが望ましいわけです。
つまり相続人からすれば、自分にもきちんと財産が分配されることを期待しています。にもかかわらず、特定の相続人だけに財産が行き渡ってしまったら、自分だけ困窮するリスクが高まります。
こういった状況が認められたら、そもそもの相続の目的が達成されなくなってしまうでしょう。したがって一般的には、寄与分よりも遺留分のほうが優先されます。
3-3.寄与分が認められた相続人に対しては、遺留分侵害額を請求できない
遺留分において注意すべきポイントは、寄与分が認められた相続人に対しては請求できない点です。遺留分を請求する相手は、あくまで受遺者や受贈者となっています。
寄与分とは、相続分をどのように修正するかといった制度であり、贈与ではありません。したがって寄与分により多く遺産を受け取っている者には、遺留分侵害額請求権を行使できないのが基本です。
とはいえ上述したとおり、遺留分を侵害する程度の寄与分を裁判所は積極的に認めないでしょう。直接的に遺留分侵害額請求権で争うのは難しいものの、裁判所の裁量によって寄与分が減額される可能性は高いといえます。
3-4.寄与分は遺留分侵害額請求を拒否するための抗弁にはならない
寄与分は、遺留分侵害額請求を拒否するための抗弁にはならない点も注意が必要です。
たとえば長男が遺言により、被相続人から多額の財産を譲り受けました。次男は当該遺言に納得がいかず、遺留分を請求したとします。このとき長男は、被相続人の介護による寄与分を受けていたことを理由に、次男からの請求を拒否できません。遺留分と寄与分は、お互いに関与し合わないためです。
つまり被相続人から寄与分を受けていたとしても、遺贈や生前贈与を理由に遺留分を請求されたら、余程の事情がない限り最低額を分配する必要があります。民法でも基本的に遺留分を認めているため、請求そのものを拒否することは難しいでしょう。
4.【ケース別】遺留分と寄与分がぶつかったときの計算方法
遺留分と寄与分がぶつかったときの計算方法は、その寄与分を主張するのが「相続人」なのか、それとも「相続人以外の親族」なのかによって大きく異なります。
相続人が主張する寄与分は、遺留分の計算(基礎財産)から引くことはできません。一方で、相続人以外の親族(たとえば長男の妻など)が請求する「特別寄与料」は、遺産総額から先に差し引かれます。
この違いを知らないと、ご自身がもらえるはずの遺留分が減ってしまうと誤解する可能性もあるため注意しましょう。
4-1.ケース1:「寄与分」を主張されても「遺留分」は減らない
ほかの相続人から「介護で貢献したから寄与分がある」と主張されても、あなたが請求できる遺留分の金額は減りません。法律上、遺留分を計算する際の基礎となる財産額からは、相続人が主張する寄与分は差し引かないルールになっているためです。
遺留分は、寄与分よりも優先して保護される強力な権利です。たとえほかの相続人に多額の寄与分が認められたとしても、あなたが請求できる遺留分の最低保障額(侵害額)はその影響を受けない、と覚えておきましょう。
4-1-1.例:遺産1億円で、相続人が長男・次男。長男が全財産相続+寄与分2,000万円を主張
この計算例では、次男が請求できる遺留分は2,500万円となり、長男の寄与分の主張によって減額されません。
まず、遺留分の計算の基礎となる財産は、寄与分を引く前の1億円です。相続人が子2人(長男・次男)だけの場合、全体の遺留分は財産の1/2(=5,000万円)です。次男の法定相続分は1/2のため、その遺留分はさらにその1/2、つまり財産全体の1/4(=2,500万円)となります。
長男の寄与分2,000万円は、この遺留分の計算には影響しません。
4-2.ケース2:「相続人以外の親族の寄与(特別寄与料)」は遺留分の計算に影響する
相続人以外の親族(たとえば長男の妻など)の貢献に対する「特別寄与料」は、遺留分の計算に影響するため注意が必要です。2019年の民法改正で新設されたこの制度では、相続人以外の親族も、無償で介護などをした場合に相続人に対して金銭(特別寄与料)を請求できるようになりました。
この特別寄与料は、法律上「遺産から支払われるべきもの」と扱われます。そのため、遺留分を計算する際の基礎となる財産額から、先に特別寄与料の額が差し引かれることになります。
4-2-1.例:遺産が1億円で、相続人が長男と次男。長男の妻が特別寄与分2,000万円を主張
たとえば、遺産が1億円で、相続人が長男と次男、そして長男の妻が介護の貢献で2,000万円の特別寄与料を請求したとします。この場合、遺留分の計算の基礎となる財産は、1億円から特別寄与料の2,000万円を引いた「8,000万円」となります。
その結果、次男が請求できる遺留分の金額は、8,000万円の1/4である「2,000万円」に減額される可能性があります。
5.遺留分と寄与分が絡む相続トラブルは弁護士への相談が必須

遺留分と寄与分が絡む相続トラブルは、当事者同士での解決が極めて困難なため、弁護士への早期相談が必須です。
これらの問題は、不動産などの「財産評価」の問題と、介護や家業の手伝いといった「貢献度の評価」という、非常に感情的になりやすい問題が複雑に絡み合います。さらに、計算方法や法的な主張の順序も専門的です。
法律の専門家である弁護士に依頼すれば、以下のようなメリットを享受できます。
5-1.複雑な財産評価と法的主張を任せられる
弁護士に依頼すると、遺留分や寄与分の計算の基礎となる複雑な財産評価を任せられます。
とくに遺産に不動産や非上場株式が含まれる場合、その評価額(時価)をめぐって相続人間で対立するのは必至です。弁護士は、不動産鑑定士などの専門家と連携し、客観的な評価額を算出できます。また、「寄与分がいくらになるか」という主張も、過去の裁判例など法的な根拠にもとづいて論理的におこなえます。
感情論になりがちな部分を専門家に任せられるのは大きなメリットです。
5-2.調停・訴訟での代理人として交渉を有利に進められる
もし話し合いで解決せず、家庭裁判所での調停や訴訟に発展した場合、弁護士はあなたの「代理人」として全ての対応をおこなってくれます。
調停や訴訟では、ご自身の主張(たとえば寄与分の具体的な内容や、相手の寄与分が高すぎることへの反論)を、証拠にもとづいて法的に整理し、裁判所に分かりやすく伝える必要があります。こうした専門的な手続きや主張をご自身でおこなうのは非常に困難です。
弁護士に依頼すれば、法廷での交渉や書面作成を全て任せられ、あなたにとって最も有利な解決を目指せます。
6.まとめ
寄与分と遺留分が争われるときは、原則として遺留分のほうが優先されます。仮に自分が遺留分の請求を主張すれば、相手は寄与分を理由に拒否することは認められません。
一方で相手が高額の寄与分をもらっているのに対し、直接遺留分侵害額請求権を行使できないともされています。遺留分の対象は、あくまで遺贈や死因贈与などであるためです。
このように遺留分と寄与分の主張がぶつかると、争いもより複雑になる恐れがあります。お互いに話し合っても解決することは難しいため、あらかじめ相続問題に強い弁護士に相談しておくとよいでしょう。
弁護士法人池袋吉田総合法律事務所では、遺留分をはじめとした相続に関する無料相談を受け付けています。相続に関する問題でお困りの方は、ぜひ当事務所までご相談ください。
このコラムの監修者
弁護士法人池袋吉田総合法律事務所は、相続全般、遺産分割、遺留分、相続放棄、生前対策、遺言作成、事業承継、
相続税など、法律のプロとして幅広い案件を取り扱っています。
初回相談は無料です。一人で悩まず、まずは当事務所へご相談ください。

第二東京弁護士会所属





