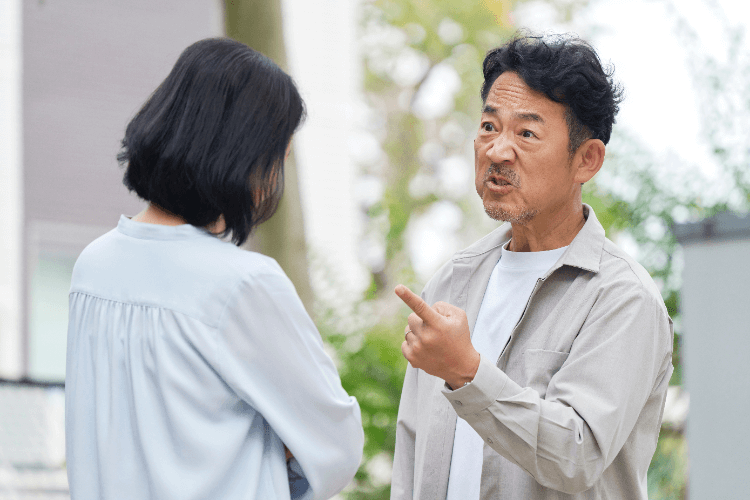
「長男だから遺産は全て俺のものだ。」「俺が一番親の面倒を見ていたんだから、遺産は全て俺が相続する」
親の死後、そんな理不尽な主張を突きつけられ、途方に暮れていませんか?当然のように遺産を独り占めしようとする兄に対し、怒りや悔しさを感じるのは当然のことです。
しかし現在の法律では、長男の特権など存在しません。そのため、正しい対応をとることで、遺産を独り占めされる状況を脱することができます。
そこでこの記事では、長男の勝手な言い分に対する法的な対応方法や、遺留分などの正当な権利を確実に取り戻すための具体的な手順を徹底解説します。
相手の勢いに押されて合意してしまう前に、正しい知識であなた自身の権利を守り抜きましょう。
このページの目次
1.「長男が遺産を独り占めできる」という法律は存在しない
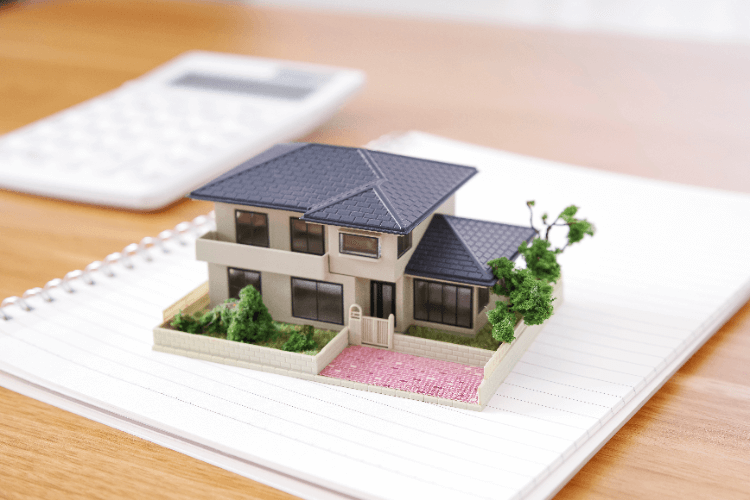
結論から述べると、長男が遺産を独り占めできると定めた法律は存在しません。民法では、配偶者や子ども、親、兄弟姉妹など、法律で定められた法定相続人が遺産を引き継ぐ権利を持つとされています。
したがって、長男であるという理由だけで、ほかの相続人の権利を無視して遺産をすべて受け取ることは不可能です。
しかし現実には、「長男だから」という理由で遺産を独占しようとするケースが見受けられます。これは、過去の法律や慣習の影響が残っているためと考えられます。
1-1.旧民法の「家督相続」は現在の法律では無効
戦前の旧民法では「家督相続(かとくそうぞく)」という制度があり、戸主である父親が亡くなると、原則として長男がすべての財産と家督を単独で相続していました。この制度は、家を存続させることを最優先としていたため、長男以外の兄弟姉妹には基本的に相続権が認められていませんでした。
しかし、戦後の民法改正(1947年)により、家督相続制度は廃止されました。現在の民法では、家督という概念自体がなくなり、相続人は平等に扱われるようになっています。
したがって、「長男だからすべて相続できる」という主張は、現在の法律では無効であり、通用しません。
参考:人に聞けない相続の話(4) 「家督相続」世代と「平等相続」世代のギャップをどうする!?|マイナビニュース
1-2.法定相続分は兄弟姉妹で平等
現在の民法では、子どもの相続分は平等と定められています。長男であっても、次男や長女であっても、受け取れる遺産の割合(法定相続分)に差はありません。
たとえば、相続人が長男と次男の2人だけの場合、法定相続分はそれぞれ2分の1ずつとなります。性別や生まれた順番によって相続分が増減することはないのです。
もし長男が「自分がすべて相続する」と主張しても、ほかの兄弟姉妹が納得しなければ、法定相続分に従って遺産を分ける権利を主張できます。
1-3.親の面倒を見ていただけで独占することはできない
「親の介護をしていたから」という理由で、長男が遺産を独占しようとするケースもあります。しかし、親の面倒を見ていたという事実だけでは、遺産をすべて相続する理由にはなりません。
たしかに、被相続人の財産の維持や増加に特別の貢献をした相続人には、寄与分として相続分の上乗せが認められる場合があります。しかし、寄与分が認められるには、「無償で」「継続的に」「専従して」介護をおこなったなどの厳しい要件を満たす必要があります。
単に同居していた、時々世話をしていた程度では、寄与分として認められるのは難しいのが現状です。また、仮に認められたとしても、遺産の独占まで正当化されるわけではありません。
関連記事:遺留分と寄与分の関係とは?ぶつかったときの計算方法
1-4.兄弟間の遺産相続におけるルールや遺産の分け方
兄弟間で遺産をどのように分けるかは、相続人の構成によってルールが異なります。ここでは、以下3つのパターンにおける法定相続分について解説します。
- 相続人が被相続人の妻と子ども2人のケース
- 相続人が被相続人の子どものみのケース
- 相続人が被相続人の兄弟のみのケース
誰が相続人になるかによって、それぞれの取り分が変わってくるため、ご自身のケースに当てはめて確認することが重要です。一つずつ見ていきましょう。
1-4-1.相続人が被相続人の妻と子ども2人のケース
被相続人に配偶者(妻)と子どもが2人(例:長男・次男)いる場合、法定相続分は以下のようになります。
| 配偶者 | 2分の1 |
| 長男 | 4分の1 |
| 次男 | 4分の1 |
子どもが2人の場合、子どもの取り分である2分の1をさらに人数で等分します。つまり、長男と次男はそれぞれ「4分の1(2分の1 × 2分の1)」ずつの相続権を持つことになります。
配偶者が遺産の半分を受け取り、残りの半分を兄弟で均等に分けるのが基本ルールです。
1-4-2.相続人が被相続人の子どものみのケース
被相続人の配偶者がすでに亡くなっている、あるいは離婚しているなどで相続人が子どものみ(例:長男・長女・次男の3人など)の場合、法定相続分は以下のようになります。
| 長男 | 3分の1 |
| 長女 | 3分の1 |
| 次男 | 3分の1 |
この場合、遺産のすべてを子ども3人で分け合います。3人の兄弟姉妹であれば、それぞれ「3分の1」ずつ均等に相続します。
長男だからといって多くもらえるわけではなく、全員が平等な割合で遺産を受け取る権利があります。
1-4-3.相続人が被相続人の兄弟のみのケース
被相続人に子どもがおらず、両親や祖父母(直系尊属)もすでに他界している場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。配偶者がいる場合は配偶者と兄弟姉妹で分けますが、配偶者もいない場合は兄弟姉妹のみで遺産を分けます。
| 兄弟姉妹全員 | 全ての遺産を兄弟姉妹の人数に応じて均等に配分 |
兄弟姉妹が複数いる場合は、原則として均等に分けます。ただし、半血兄弟(父または母が異なる兄弟姉妹)の相続分は、全血兄弟(父母両方が同じの兄弟姉妹)の2分の1となる点に注意が必要です。
2.長男が全ての遺産を相続するケースもある
先述のとおり、法律上は長男の独り占めは認められていませんが、特定の条件下では長男がすべての遺産を相続するケースも存在します。「長男による独占」が法的に有効となる代表的なパターンは、以下の2つです。
- 遺産分割協議での合意があった
- 相続人が長男一人だけだった
それぞれ解説します。
2-1.遺産分割協議での合意があった
相続人全員が参加する「遺産分割協議」において、全員が「長男がすべての遺産を相続する」ことに合意すれば、長男による単独相続は有効となります。
民法では法定相続分が定められていますが、これはあくまで目安であり、強制力はありません。相続人全員の合意があれば、法定相続分と異なる割合で遺産を分けることが可能です。
たとえば、「長男が家業を継ぐから」「親の介護を献身的にしてくれたから」といった理由で、ほかの兄弟姉妹が納得して遺産を譲るケースがこれにあたります。
ただし、この合意はあくまで「全員の同意」が前提であり、一人でも反対する相続人がいれば成立しません。
2-2.相続人が長男一人だけだった
相続人が長男一人しかいない場合は、長男がすべての遺産を相続します。具体的には、以下のようなケースです。
- 被相続人に配偶者がおらず、子どもが長男一人だけの場合
- ほかの兄弟姉妹が全員「相続放棄」をした場合
- ほかの兄弟姉妹が相続欠格や廃除によって相続権を失っている場合
相続放棄とは、家庭裁判所に申し立てて、最初から相続人でなかったことになる手続きです。ほかの兄弟姉妹が借金などの負債を避けるため、あるいは長男に遺産を集中させるために相続放棄を選んだ場合、結果的に長男が遺産を独占することになります。
3.長男が遺産相続で独り占めしても遺留分は請求可能
もし長男が遺産を独り占めしようとしても、ほかの兄弟姉妹は遺留分を請求可能です。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者、子、親など)に法律上保障された、最低限の遺産取得分のことです。たとえ「全財産を長男に相続させる」という遺言書があったとしても、遺留分を侵害された相続人は、長男に対して侵害された金額(遺留分侵害額)を支払うよう請求できます。
これを「遺留分侵害額請求」といいます。
3-1.遺留分の計算方法
遺留分として請求できる金額は、「遺留分算定の基礎となる財産額 × 個別的遺留分の割合」で計算されます。
まず全体の遺留分は、相続人が直系尊属(親など)のみの場合は遺産全体の「3分の1」、それ以外の場合(配偶者や子がいる場合)は「2分の1」です。そこに各相続人の法定相続分を掛け合わせたものが、個別の遺留分となります。
たとえば、相続人が長男と次男の2人で、遺産総額が4,000万円の場合の次男の遺留分を考えてみましょう。以下のような順に計算していきます。
- 4,000万円 × 2分の1 = 2,000万円
- 2,000万円(1ででた額) × 2分の1(法定相続分) = 1,000万円
このケースでは、もし長男が4,000万円すべてを相続しようとした場合、次男は長男に対して1,000万円を遺留分として請求することができます。
4.長男に遺産相続で独り占めされそうなときの対処法

長男による遺産の独り占めを阻止するためには、泣き寝入りせず、状況に応じた適切なアクションを起こすのが重要です。
ここでは、遺言書がある場合とない場合、それぞれのケースにおける具体的な対処法を解説します。ご自身の状況に合わせて、冷静に対処していきましょう。
4-1.ケース①「長男に全て譲る」という遺言書がある場合
「全財産を長男に相続させる」という遺言書が出てきた場合でも、諦める必要はありません。遺言書の内容は強力ですが、絶対的なものではないからです。
遺言書が存在するケースで検討すべき法的手段は、以下の2つです。
- 遺言の無効を主張する
- 遺留分を主張する
詳しく解説します。
関連記事:遺言書で一人に相続させることは可能?一人に相続する遺言書の作り方
4-1-1.遺言の無効を主張する
遺言書が作成された当時、被相続人が重度の認知症などで判断能力(遺言能力)がなかった場合、その遺言は無効になる可能性があります。
また、自筆証書遺言の場合、筆跡が明らかに違ったり、形式に不備があったりすれば、偽造の疑いも含めて無効を主張できます。
遺言が無効であることを証明するには、医師の診断書や介護記録などの証拠を集め、家庭裁判所に「遺言無効確認調停」を申し立てるのが一般的です。疑わしい点が少しでもあるなら、安易に遺言の内容を認めず、専門家に相談して有効性を確認しましょう。
4-1-2.遺留分を主張する
遺言書が有効であっても、兄弟姉妹以外の法定相続人には遺留分を受け取る権利があります。
長男にすべての財産を譲るという内容でも、ほかの相続人は長男に対して、自分の遺留分に相当する金銭を請求することが可能です。これを「遺留分侵害額請求」といいます。
ただし、遺留分を請求できる期限は、「相続の開始および遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年以内」です。期限を過ぎると権利が消滅してしまうため、内容証明郵便を送るなどして、速やかに意思表示をおこないましょう。
関連記事:遺留分は必ずもらえる?必ずもらえるとは限らない3つのケースも解説
4-2.ケース②遺言書がないのに独り占めしようとする場合
遺言書がない場合、遺産を分けるには相続人全員での話し合い(遺産分割協議)による合意が不可欠です。長男が勝手に「俺が全部もらう」と宣言しても、ほかの相続人の同意がなければ法的な効力はありません。
そのため、以下3つの行動をとるようにしてください。
- 遺産分割協議書への実印・署名を絶対に拒否する
- 預金口座の凍結と取引履歴の開示請求をおこなう
- 使い込みが疑われる場合は調査する
一つずつ解説します。
4-2-1.遺産分割協議書への実印・署名を絶対に拒否する
内容に納得できない遺産分割協議書には、絶対に署名や捺印をしてはいけません。一度でも実印を押して合意してしまうと、あとからやはり納得できないと思っても、その合意を覆すのは極めて困難になるからです。
長男から「とりあえずハンコを押せ」と威圧されたり、「あとで調整するから」と甘い言葉をかけられたりしても、拒否する姿勢を貫きましょう。
また、印鑑証明書を安易に渡すのも危険です。勝手に手続きに使われるリスクがあるため、自分が納得し、署名する段階になるまでは手元で厳重に管理してください。
4-2-2.預金口座の凍結と取引履歴の開示請求をおこなう
長男に預金を勝手に引き出されるのを防ぐため、早急に金融機関へ連絡し、口座を凍結させましょう。銀行などの金融機関は、口座名義人が亡くなったことを知ると口座を凍結し、入出金を停止します。
あわせて、過去の「取引履歴」の開示請求もおこなってください。通帳が見当たらない場合でも、金融機関に請求すれば過去の入出金記録を取り寄せられます。
これにより、生前に不自然な引き出しがなかったか、死後に勝手に預金が動かされていないかを確認できます。客観的な証拠を集めることが、交渉を有利に進める鍵となります。
4-2-3.使い込みが疑われる場合は調査する
取引履歴を確認し、使途不明な多額の引き出しがある場合は、長男による使い込みを疑って調査する必要があります。
被相続人が入院中や認知症で判断能力がない時期に、ATMで頻繁に引き出しがあったり、特定の口座へ送金されていたりする場合は要注意です。これらは「不当利得」として返還請求できる可能性があります。
もし使い込みが発覚したら、その金額を遺産に持ち戻して分割するよう主張しましょう。証拠を隠滅されないよう、弁護士などの専門家に依頼して徹底的に調査するのも有効な手段です。
関連記事:遺産の使い込みが発覚したら?泣き寝入りしないための対処法
5.長男が主張しがちな遺産独占の理由とそれへの反論・対抗策
長男が遺産を独り占めしようとする際、もっともらしい理由を並べてくることがあります。しかし、それらの主張は法的には認められないケースや、反論が可能なケースが多いです。
ここでは、長男がよく口にする3つの主張と、それに対する正しい反論・対抗策について詳しく解説していきます。
- 自分が親の介護をしていたからと主張された場合
- 実家(不動産)は長男が継ぐべきと主張された場合
- 生前贈与をされたから遺産は渡せないと主張された場合
相手の主張を鵜呑みにせず、冷静に法律のルールと照らし合わせることが大切です。それぞれ解説します。
5-1.自分が親の介護をしていたからと主張された場合
「俺が親の介護をしたから、遺産は全部もらう権利がある」という主張は、必ずしも通るものではありません。親子間にはもともと扶養義務があり、通常程度の介護は「当たり前」とみなされるため、遺産を独占する理由にはならないのです。
もし遺産上乗せを求めるなら「寄与分」の主張が必要ですが、これには「無償で」「仕事を辞めて専念した」などの厳しい要件があります。仮に寄与分が認められたとしても、あくまで相続分が増えるだけであり、ほかの相続人の権利がゼロになるわけではありません。
感情論に流されず、法的な基準で判断しましょう。
5-2.実家(不動産)は長男が継ぐべきと主張された場合
「長男だから実家を継ぐのは当然。だから家は俺のものだ」と言われても、タダで譲る必要はありません。
不動産を長男が取得すること自体は問題ありませんが、その場合、長男はほかの相続人に対して相続分に見合う金銭を支払う必要があります。これを「代償分割」といいます。
実家の価値を不動産鑑定などで正しく評価し、その評価額にもとづいて公平な金銭の支払いを求めましょう。もし代償金を払えないのであれば、実家を売却して現金を分ける「換価分割」も選択肢となります。
関連記事:遺産が不動産しかない場合遺留分の計算や請求方法はどうなる?
5-3.生前贈与をされたから遺産は渡せないと主張された場合
「お前は結婚するときに援助を受けたから、もう取り分はない」と主張されることがあります。
たしかに、過去に受け取った多額の援助は「特別受益」として、相続分から差し引かれる可能性があります。しかし、それだけで相続分が完全にゼロになるとは限りません。
また、長男自身も学費や住宅資金の援助を受けている可能性があります。特別受益を主張するなら、長男が受け取った分も同様に計算すべきです。
一方的に言われるがままにならず、過去の贈与の事実関係を公平に洗い出しましょう。
6.遺産を独り占めした長男と話し合いにならないときの流れ
当事者同士での話し合いが平行線をたどり、これ以上進展しない場合は、第三者や法的機関を介入させる必要があります。長男との話し合いがまとまらない場合は、以下の流れに沿って対応をしてください。
- 内容証明郵便による意思表示
- 家庭裁判所への「遺産分割調停」の申し立て
- 調停不成立の場合の「審判」への移行
順を追って解説していきます。
6-1.①内容証明郵便による意思表示
まずは、「内容証明郵便」を使って、こちらの意思や請求内容を相手に通知しましょう。これは、いつ、誰が、誰に、どのような内容の手紙を送ったかを郵便局が証明してくれるものです。
口頭での要求は「言った、言わない」の水掛け論になりがちですが、内容証明郵便であれば証拠として残ります。また、長男に対して「こちらは本気で法的措置も辞さない」という強い姿勢を示すことができ、相手が交渉のテーブルに着くきっかけになることもあります。
とくに、遺留分侵害額請求には1年または10年という時効があるため、期限内に請求した証拠を残す意味でも非常に重要です。
6-2.②家庭裁判所への「遺産分割調停」の申し立て
内容証明を送っても無視されたり、話し合いが決裂したりした場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てます。これは、裁判官と調停委員という第三者が間に入り、話し合いによる解決を目指す手続きです。
調停では、長男と直接顔を合わせて言い争う必要がなく、交互に調停委員と話をする形式で進められます。中立的な立場からの助言や調整が入るため、当事者だけでは感情的になって進まなかった議論も、冷静に進められる可能性が高まります。
6-3.③調停不成立の場合の「審判」への移行
調停でも合意に至らなかった場合は、自動的に審判という手続きに移行します。審判では、裁判官が双方の主張や証拠、法律の規定をもとに、遺産の分割方法を決定します。
審判で下された決定は判決と同じ強い効力を持ち、長男が納得しなくても強制的に従わせることが可能です。仮に長男が遺産を渡さない場合でも、審判書を使って強制執行をおこなうことができます。
ただし、審判は柔軟な解決が難しくなることもあるため、できる限り調停での解決を目指すのが一般的です。
7.長男に遺産を独り占めされたら弁護士への依頼がおすすめ

長男が強硬に遺産を独り占めしようとしている場合、個人で立ち向かうには限界があります。そこで法律の専門家である弁護士に依頼することで、不利な状況を覆し、正当な権利を取り戻せる可能性を格段にあげることが可能です。
ここでは、弁護士に依頼することで得られる具体的な5つのメリットについて解説します。
- 法的権利の確認とアドバイスを受けられる
- 遺産分割協議をスムーズに進めるためのサポートを受けられる
- 遺言書の効力や解釈について専門的な見解を得られる
- 想定されるさまざまなトラブルに対応できる
- 精神的な負担から解放される
詳しく解説します。
7-1.法的権利の確認とアドバイスを受けられる
弁護士に相談すれば、あなたの状況において法的にどの程度の遺産を請求できるのか、正確な見通しを立てることができます。「長男の主張は法的に正しいのか」「自分の遺留分はいくらになるのか」といった疑問に対し、専門的な根拠にもとづく回答を得ることが可能です。
これにより、無理な要求をして時間を浪費することなく、実現可能なゴールに向かって最短ルートで動けるようになります。また、証拠の集め方についても具体的なアドバイスがもらえます。
7-2.遺産分割協議をスムーズに進めるためのサポートを受けられる
弁護士は、あなたの代理人として長男との交渉窓口になることができます。弁護士が介入すると、相手は「法的な争いになる」と認識し、理不尽な主張を撤回するケースも少なくありません。
また、法的根拠にもとづいて冷静に交渉を進めるため、感情的な対立による時間のロスを防げます。遺産分割協議書の作成も任せられるため、内容に不備があって後日無効になるといったトラブルも回避できるでしょう。
7-3.遺言書の効力や解釈について専門的な見解を得られる
不利な遺言書が出てきた場合でも、弁護士ならその有効性を厳密にチェックできます。「自筆証書遺言の形式不備」や「被相続人の認知症による遺言能力の欠如」など、一般の方では気づきにくい無効の事由を発見できる可能性があります。
また弁護士であれば、遺言書の文言が曖昧な場合の解釈についても、過去の判例をもとに有利な主張を組み立てることが可能です。遺言書があるからといって諦めず、まずは専門家の目を通すことが重要となります。
7-4.想定されるさまざまなトラブルに対応できる
遺産相続では、預金の使い込みや不動産の評価額、生前の介護による寄与分の主張など、さまざまな問題が複雑に絡み合うことがよくあります。
弁護士であれば、これらの問題が発生した際も、即座に対応策を講じることができます。使い込みの証拠確保のための調査や、不動産鑑定士や税理士などの他士業との連携もスムーズです。
予期せぬトラブルが起きても、法的な盾となってあなたを守り、最終的な解決までサポートしてくれます。
7-5.精神的な負担から解放される
弁護士に依頼することで、精神的なストレスから解放されるのも大きなメリットです。
高圧的な長男との直接交渉は、大変な心労を伴います。弁護士が代理人になれば、相手との連絡や交渉はすべて弁護士がおこないます。あなたは矢面に立つ必要がなくなり、日常生活の平穏を取り戻すことができるでしょう。
「法律のプロが味方に付いている」という安心感は、相続トラブルという辛い状況において、心の大きな支えとなるはずです。
8.不公平な相続に泣き寝入りせず、正当な権利を取り戻そう
「長男だから」という理屈は、現代の相続において何の意味も持ちません。どれだけ相手が高圧的でも、また「全財産を譲る」という遺言書があったとしても、あなたには「遺留分」という法律で守られた権利があります。
大切なのは、相手の勢いに負けて泣き寝入りしないことです。もし当事者同士での話し合いが難しいと感じたら、無理をせず弁護士などの専門家を頼ってください。プロを味方につけることは、精神的な平穏と正当な財産を取り戻すための最短ルートです。
弁護士法人池袋吉田総合法律事務所では、遺産相続や遺留分をはじめとした相続に関する無料相談を受け付けています。相続に関する問題でお困りの方は、ぜひ当事務所までご相談ください。
このコラムの監修者
弁護士法人池袋吉田総合法律事務所は、相続全般、遺産分割、遺留分、相続放棄、生前対策、遺言作成、事業承継、
相続税など、法律のプロとして幅広い案件を取り扱っています。
初回相談は無料です。一人で悩まず、まずは当事務所へご相談ください。

第二東京弁護士会所属





