
親が遺した、思い出の詰まった「実家」。兄弟姉妹で相続することになったとき、非常にデリケートな問題となります。
「誰が住むのか」「どう公平に分けるのか」、それぞれの想いや事情がぶつかり、仲の良かった兄弟が「争族」に発展するケースは少なくありません。そうならないためには、感情的な話し合いの前に、法的な分け方の選択肢と、正しい手続きを知っておくことが不可欠です。
そこでこの記事では、以下の内容を弁護士がわかりやすく解説していきます。
- 兄弟間で実家を相続する前に知っておきたいこと
- 兄弟間で実家を分割する方法とそれぞれのメリット・デメリット
- 兄弟間で実家を相続するときの流れ
- 実家を相続するメリットとデメリット
さらに記事の後半では、兄弟間の実家相続で揉めるパターンと、トラブルを回避する方法についても触れていますので、ぜひ最後までご覧ください。
このページの目次
1.兄弟間で実家を相続する前に知っておきたいこと
兄弟間で実家を相続する前に、知っておきたいことが2つあります。
- 最も重要なのは相続人調査
- 自身の法定相続分を計算する方法
それぞれの押さえなければならないポイントについて、まとめていきます。
関連記事:実家の相続でやってはいけない行動6選 | 実家相続後の正しい選択肢も解説
1-1. 最も重要なのは相続人調査
実家の相続において、最も重要となるのが相続人調査です。一人でも相続人を欠いた状態で遺産分割協議をすると、効力が発生しないためにやり直しとなってしまうためです。
そのためまずは、戸籍謄本などを収集し、誰が相続人になるかを入念にリサーチしなければなりません。ただし初心者だけで相続人を全員見つけ出すのは難しいので、なるべく弁護士に依頼したほうが賢明です。
1-2. 自身の法定相続分を計算する方法
自身の法定相続分の計算方法も、あらかじめ押さえておく必要があります。法定相続分は、誰が相続人になるかで細かく変わります。
| 相続人(被相続人から見た続柄) | 法定相続分 |
|---|---|
| 子(2人)の場合 | 2分の1ずつ |
| 子(3人)の場合 | 3分の1ずつ |
| 配偶者と子2人の場合 | 配偶者:2分の1、子:4分の1ずつ |
とはいえ遺産分割協議では、法定相続分に従わないで相続分を決めることも可能です。したがって法定相続分は、必ず守らないといけないものではありません。
2.兄弟間で実家を分割する方法とそれぞれのメリット・デメリット
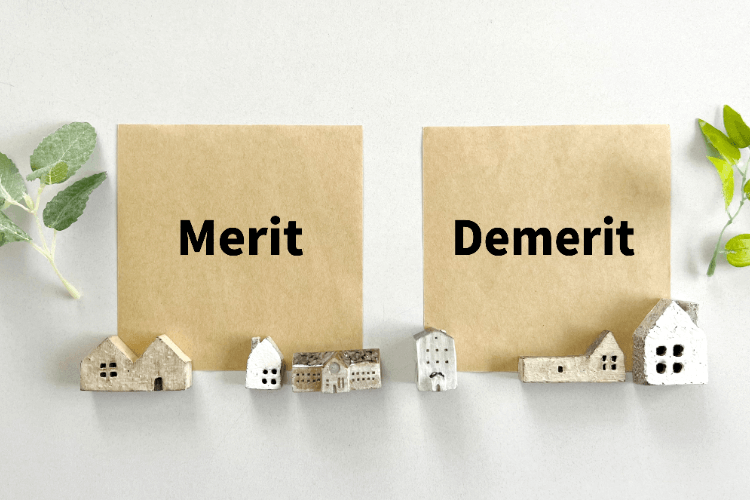
兄弟間で実家を分割するには、大きく分けて4つの方法が存在します。
- 代償分割
- 換価分割
- 現物分割
- 共有分割
それぞれの仕組みを説明するとともに、メリットおよびデメリットについても触れていきます。
2-1. 代償分割
代償分割は、相続人の一人が実家や土地をそのまま相続する代わりに、その人が他の相続人に対して、自己の資産から「代償金」という現金を支払う方法です。実家や土地といった、物理的に分けるのが難しい遺産の相続において、相続人間の公平を保つために用いられます。
たとえば長男が実家を相続し、次男と三男に代償金を支払うケースが該当します。
代償分割のメリットは、公平な財産分与がしやすいことです。代償金は評価額に応じて決められるので、相続人の一人の相続分だけ少なくなるといった事態を防ぎやすくなります。
一方で代償金を支払うには、実家を相続する人の資金力が必要です。代償金があまりにも少なくなれば、相続人同士で揉めやすくなるでしょう。
2-2. 換価分割
換価分割とは、実家を第三者に売却し、得られた現金を相続人間で分割する方法です。
不動産は土地を現金化したうえで分割できるため、不公平になりにくいといったメリットがあります。不動産を相続したいと思う人がいない場合には、とくにおすすめな方法です。
しかし換価分割は、買い手が見つかるまで時間がかかる点がデメリットです。煩雑な手続きも求められるので、専門家と協力しながら進めなければなりません。
2-3. 現物分割
現物分割とは、不動産を物理的に分けて分割する方法です。たとえば相続財産の中に、甲土地・乙土地・丙土地があったとしましょう。この3つの土地について、長男が甲土地、二男が乙土地、三男が丙土地を相続するケースが該当します。
現物分割のメリットは、手続きの手間が少なく、相続財産をそのまま残せることです。しかし実際に、一つの建物を現物分割するケースはあまり見られません。
1階部分を長男、2階部分を二男に分けることは、現実的に考えて難しいからです。土地を分筆する際にも、境界線を巡るトラブルが発生する恐れもあります。
2-4. 共有分割
共有分割とは、実家を相続人で共有する状態を指します。たとえば兄弟3人が実家を相続したとき、法定相続分における持分は3分の1ずつです。相続人は共有持分に応じて、不動産の全部を管理・使用できます。
共有分割も現物分割と同じく、不動産をそのまま残せる点がメリットです。しかし自分一人で不動産を処分することはできず、誰かに売却するときは共有者全員の同意を得ないといけません。不動産の処分を巡り、ほかの相続人とトラブルに発展する可能性も考えられます。
3.兄弟間で実家を相続するときの流れ

兄弟間で実家を相続するときは、以下の手順を踏む必要があります。
- 遺言書の有無を確認する
- 誰が相続人になるのかを確定させる
- 実家を含めたすべての相続財産を調査する
- 遺産分割協議を作成する
- 相続登記や相続税の申告をおこなう
それぞれのプロセスごとに、どういった手続きが必要になるかを解説します。
3-1. ①遺言書の有無を確認する
被相続人が遺言書を残していた場合、その内容どおりに分配するのが原則です。遺言書を探す際には、まず被相続人の自宅から探してみてください。
自宅のほかにも、公証役場や法務局が保管先となっているケースもあります。「遺言検索システム」を利用すれば、遺言書の有無も簡単に調べられます。
3-2. ②誰が相続人になるのか(法定相続人)を確定させる
遺産分割をするときは、誰が相続人になるのかを確定させましょう。相続人を調べるときは、市区町村役場で故人および相続人全員の戸籍謄本を収集する必要があります。
しかし戸籍謄本を発行できるところは、あくまで本籍地のある市区町村役場です。遠方にある場合は、郵送での手続きも念頭に置いておくとよいでしょう。弁護士に依頼すれば、委任状がなくても戸籍謄本を発行できます。
3-3. ③実家を含めたすべての相続財産を調査する
相続人調査と一緒に、実家を含めたすべての相続財産も調査しなければなりません。遺品整理をしつつ、どのような財産があるかを調べましょう。
ほかにも不動産があるときは、その所在地の市区町村役場で名寄帳を取り寄せれば、具体的な情報を確認できます。相続財産の調査も、なるべく専門家に任せたほうが賢明です。
3-4. ④遺産分割協議書を作成する
相続人全員で遺産分割協議をしたあとは、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書の効力が発揮するには、相続人全員の署名捺印が必要です。
遺産分割協議で揉めたときは、家庭裁判所での調停や審判も検討しましょう。
3-5. ⑤相続登記や相続税の申告をおこなう
実家を相続する際には、相続登記を済ませる必要があります。とくに相続登記は、2024年4月より義務化されました。3年以内に済ませないと、最大で10万円以下の過料が科せられる恐れもあるので注意してください。
また相続財産の総額が「3,000万円+(600万円×相続人数)」を超えているときは、相続税の申告も必要です。相続開始があったことを知った日の翌日から起算して、10カ月以内に申告しないと無申告加算税や延滞税などの対象になる恐れがあります。
4.実家を相続するメリットとデメリット
実家を相続するかどうかは、メリットとデメリットの双方を理解したうえで判断するのが望ましいでしょう。ここではメリットとデメリットに分けて、実家を相続するとどのようなことが起こりうるかを解説します。
4-1. 実家を相続するメリット
実家を相続するメリットは、以下のとおりです。
- 資産としての価値がある
- 住居として活用できる
- 相続税の負担を軽減できる可能性がある
- 家族の思い出や心の拠り所が残る
とくに不動産を所有していない人は、これらのメリットについて把握しておくとよいでしょう。
4-1-1. 資産としての価値がある
不動産の状態にもよりますが、一般的には資産としての価値が付きます。そのため第三者に売却すれば、多額の現金が手元に残る可能性があります。
売却以外にも、賃貸契約を交わして家賃収入を得るといった方法も可能です。
4-1-2. 住居として活用できる
不動産を所有していない場合は、住居として活用する方法もあります。賃貸物件で生活すると、定期的に家賃収入が発生してしまいます。
実家のローンが完済していれば、月々のランニングコストを抑えられるかもしれません。家計の状況を確認しつつ、実家を相続したほうが生活費を抑えられるのであれば、住居としての利用も検討してみましょう。
4-1-3. 相続税の負担を軽減できる可能性がある
実家を相続すれば、財産額が大きくなって税負担も重くなると思うかもしれません。しかし小規模宅地等の特例などの節税策をうまく使えば、相続税の負担を軽減できる可能性があります。
小規模宅地等の特例とは、面積が330㎡までの特定居住用宅地について、土地の評価額を最大80%まで減額する制度です。ただし適用されるには、数々の要件を満たす必要があるので、細かく確認しないといけません。
4-1-4. 家族の思い出や心の拠り所が残る
相続人のなかには、子どもの頃に住んでいた家を失いたくないと思う人もいるでしょう。実家を相続すれば、家族の思い出や心の拠り所が引き続き残ります。
思い出が生活のエネルギーになる場合もあるので、相続するかどうかを慎重に判断することをおすすめします。
4-2. 実家を相続するデメリット
実家を相続するデメリットとして考えられる要素が、次の4点です。
- 維持・管理の費用と手間がかかる
- 「空き家」になるリスクがある
- 資産価値が低く「負動産」になる可能性がある
- 兄弟間のトラブルの原因になりやすい
場合によっては、大きなトラブルに巻き込まれることもあるため、デメリット要素もしっかりと考慮しなければなりません。
4-2-1. 維持・管理の費用と手間がかかる
実家を相続するデメリットとして挙げられるのが、維持や管理に費用と手間がかかることです。たとえば土地や不動産を所有しているだけで、固定資産税・都市計画税といった税金が発生します。
またローンを完済していたとしても、建物が古くなればリフォームが必要です。きちんと家計を計算していかないと、生活の負担が大きくなってしまいます。
4-2-2. 「空き家」になるリスクがある
実家を相続したものの、誰も住まなければ「空き家」になるリスクがあります。実家があまりにも古すぎて、倒壊の恐れがある場合は特定空き家に指定されかねません。
特定空き家に指定されると、固定資産税が最大で6倍まで増加します。相続税の節税に成功しても、結果的に高額なコストが発生する可能性もあるので注意してください。
4-2-3. 資産価値が低く「負動産」になる可能性がある
実家の状態によっては、資産価値が低くなるケースも珍しくありません。資産価値が低いと、誰かに売却する難易度が高くなってしまいます。
固定資産税といった費用を請求され続けるなど、いわゆる「負動産」になる可能性もあります。実家の相続においては、売れなかった場合の活用方法も考えなければなりません。
4-2-4. 兄弟間のトラブルの原因になりやすい
実家の活用方法について、兄弟たちの意見が必ずしも合うとは限りません。長男は家を残したいと思う一方で、二男は売却したいと考えている可能性もあります。
また兄弟で共有分割するときも、持分権を巡ってトラブルになることも考えられます。これまで仲の良かった兄弟でも、相続問題で修復できなくなる場合もあるので注意してください。
5.兄弟間の実家相続で揉める3つのパターン

実家を相続するときに、兄弟間で揉めるパターンとして主に3つあります。
- 兄弟間で意見が対立する
- 「生前の援助」「親の介護」などの過去の不公平感を持ち出す
- 実家の価値や分け方について知識がなく感情的に対立する
具体的にどういったトラブルへつながるか、対処法とともに解説します。
5-1. 兄弟間で意見が対立する
実家の相続で揉めるパターンの一つが、兄弟間で意見が対立することです。元々兄弟が疎遠であり、話し合いをする機会がほとんどなかったら、意見もまとまりにくくなるでしょう。
どうしても解決できないのであれば、家庭裁判所の調停手続を利用することをおすすめします。
5-2. 「生前の援助」「親の介護」など過去の不公平感を持ち出す
兄弟間で揉める要因として、「生前の援助」「親の介護」といった話を持ち出すケースも挙げられます。たとえば長男が親から生前贈与を受けていれば、ほかの兄弟は不公平に感じるでしょう。
また子どもの一人が親の介護をしていた場合、「これまで介護に貢献してきた自分が実家の使い道を決める」と主張することも考えられます。話し合いで解決するには、専門家を間に立たせたほうが賢明です。
5-3. 実家の価値や分け方について知識がなく感情的に対立する
兄弟が誰も相続について知識がなく、感情的に対立している場合もあります。弁護士などの法律のプロに依頼し、なるべく早く解決できるようにしましょう。
どうしても話し合いでの解決が難しいのであれば、家庭裁判所の調停または審判も検討しなければなりません。
関連記事:相続でもめる原因とは?仲の良い家族でも注意したいポイントを解説
6.相続放棄をするのもひとつの手段
故人に多額の借金がある場合や、実家が管理の難しい「負動産」である場合には、全ての遺産を引き継ぐ権利を放棄する「相続放棄」も、有力な選択肢の一つです。
相続放棄の手続きを家庭裁判所でおこなうと、あなたは初めから相続人ではなかったことになります。その結果、実家を相続する権利を失う代わりに、故人の借金や、実家の管理義務・固定資産税の支払い義務からも完全に解放されます。
ただし、以下の点には注意が必要です。
- 預貯金などプラスの財産も一切相続できなくなる
- あなたの相続権が次の順位の親族(たとえば故人の兄弟姉妹など)に移る
- 相続の開始を知ったときから3カ月以内に決断する必要がある
相続放棄は、専門家に依頼することで手続きを簡略化することができます。「手続きに費やす時間がない」「必要書類の集め方がよくわからない」という方は、ぜひ弁護士への依頼を検討してみてください。
関連記事:相続放棄後にしてはいけないこととは?認められる行為も解説
7.まとめ
まずは実家を兄弟で相続するにあたって、どの方法で分割するかを決めましょう。遺言書や相続人、相続財産の調査もおこない、遺産分割の効力が発揮できるようにしなければなりません。
相続手続きでは、相続人同士で揉める可能性もあります。話し合いで解決しないときは、法律事務所や家庭裁判所などの専門の機関を頼りましょう。
弁護士法人池袋吉田総合法律事務所では、相続に関する無料相談を受け付けています。相続に関する問題でお困りの方は、ぜひ当事務所までご相談ください。
このコラムの監修者
弁護士法人池袋吉田総合法律事務所は、相続全般、遺産分割、遺留分、相続放棄、生前対策、遺言作成、事業承継、
相続税など、法律のプロとして幅広い案件を取り扱っています。
初回相談は無料です。一人で悩まず、まずは当事務所へご相談ください。

第二東京弁護士会所属





