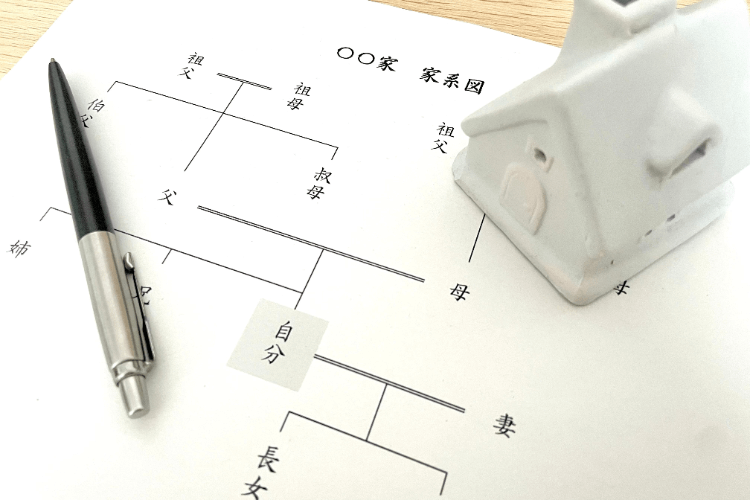
家族とほとんど連絡をとっておらず、相続争いを避けるべく完全に絶縁したいと思っている人もいるでしょう。しかし相続権を手放すには、適切な手続きを経る必要があります。
そこでこの記事では、家族と絶縁したいと考えている人に向けて、以下の内容について解説していきます。
- 家族との絶縁と相続の関係性
- 絶縁したい家族との相続を進めるデメリットやリスク
- 絶縁したい兄弟との相続争いを避ける方法
ほかの相続人を除外する手続きにも触れるので、兄弟姉妹とトラブルのある方もぜひ最後までご覧ください。
このページの目次
1.家族と絶縁しても相続権は手放せない

たとえ家族と疎遠の状態でも、絶縁しただけでは相続権は手放せません。そもそも相続は、被相続人が死亡した時点で自動的に発生するためです。
この章では、以下3つの観点から絶縁と相続権の関係を深堀していきます。
- 絶縁はあくまで個人間の問題
- 絶縁したくても相続順位に応じて相続が発生する
- 絶縁したくても遺産分割協議をしなければ相続は進まない
詳しく解説します。
1-1.絶縁はあくまで個人間の問題
家族と仲が悪くなり、口をきかなくなったり、連絡を絶ったりする「絶縁」は、あくまで個人的な関係を断つという意思表示です。そのため、家族・兄弟などという法律上の関係は変わりません。
そのため、相続が発生した際には、法律で定められた相続人の相続権が守られます。たとえ絶縁したい家族であっても、法律上の家族関係がある限り、相続権は原則として失われないと理解しておきましょう。
ですが、法律上の家族関係を断ち切る手続きも存在します。たとえば、婚姻前の出産で父親が不明な場合、「親子関係不存在確認の訴え」を通じて法的な親子関係を否定することが可能です。また、「特別養子縁組」の手続きを経ることで、実親との親子関係を終了させることもできます。
1-2.絶縁したくても相続順位に応じて相続が発生する
絶縁したいと思っていても、相続は法律で決められた順番で起こります。法律では、誰が遺産を相続できるかが「相続順位」として定められています。
まず、亡くなった被相続人の配偶者(夫や妻)は必ず相続人になります。次に、以下の順番で相続順位が決定します。
| 第1順位 | 被相続人の子ども |
| 第2順位 | 被相続人の親や祖父母 |
| 第3順位 | 被相続人の兄弟姉妹 |
仮に父親である被相続人が亡くなったときは、その配偶者と子どもに相続権が与えられます。そしていくら家族と絶縁したいと思っていても、相続権が与えられた段階で相続が発生するのです。
また、上記の例において絶縁したい兄弟が一人だけいた場合も、その兄弟には相続が発生することになります。
1-3.家族と絶縁したくても遺産分割協議をしなければ相続は進まない
家族と絶縁したくても、相続が起きたら遺産分割協議が必要になるのが原則です。遺産分割協議を経て、被相続人の遺産を誰がどのように分けるかを相続人全員で話し合って決めなければなりません。
そのため、たとえあなたが家族と一切関わりたくないと思っていても、法律上の相続人である以上、遺産分割協議に参加する義務があり、同時に遺産を受け取る権利を持ちます。
もし遺産分割協議をせずに一部の相続人だけで遺産を分けてしまうと、法的なトラブルが発生する可能性が高いです。したがって、家族と絶縁したくても、相続の手続きを進めるためには遺産分割協議への参加は避けて通れません。
関連記事:絶縁した兄弟姉妹との遺産相続 | 手続きの進め方や話し合う際のポイント
2.絶縁したい家族との相続を進めるデメリットやリスク

絶縁したいと思っているにもかかわらず、相続争いに応じると面倒なトラブルに巻き込まれる恐れがあります。考えうるデメリットについて紹介します。
- 説得されて不利な相続をしてしまう
- 遺産の割合で揉め遺産分割協議が長引く
- 遺産分割調停や審判に発展する可能性がある
- 精神的に疲弊してしまう
- 相続税を納めないといけなくなる
- 借金の相続が発生する恐れもある
それぞれについて正しく理解をしましょう。
2-1.説得されて不利な相続をしてしまう
デメリットの一つとして考えられるのが、ほかの相続人に説得されて不利な相続をしてしまう点です。たとえば全く必要のない不動産を押し付けられ、管理や処分に悩まされるといったケースも考えられます。
知識のない状態で遺産分割協議に参加すると、関係のよくない相続人にうまく言いくるめられるリスクが高まるでしょう。そもそも遺産がいらないのであれば、自ら相続権を手放したほうが賢明です。
2-2.遺産の割合で揉め遺産分割協議が長引く
遺産分割協議は、相続人全員で話し合い、決定した内容に合意をしなければ有効ではありません。そのため、相続人同士が揉めることで相続手続きの完了が遅れるのは必然です。
自分の家庭を優先したい人からすれば、絶縁したいと思っている相続人との話し合いに応じるのは、貴重な時間を無駄にする行為です。ですが遺産分割協議で揉めたり放置したりすることで、以下のようなリスクも生じるため、注意してください。
- 遺産を勝手に使い込まれる・処分される
- 相続登記の手続きが進まない
2-2-1.遺産を勝手に使い込まれる・処分される
遺産分割協議が長引くことで、遺産を勝手に使い込まれたり処分されたりするリスクがあります。絶縁状態のまま相続を放置することで、ほかの相続人に遺産を独断で管理されたり使用されたりする可能性が考えられるのです。
たとえば、預金口座からお金を引き出したり、不動産を売却したりするケースなどです。
このような行為は違法であり、後々トラブルの原因となり、遺産分割協議が長引くほどこのリスクが高まります。
関連記事:遺産の使い込みが発覚したら?泣き寝入りしないための対処法
2-2-1.相続登記の手続きが進まない
相続登記とは、被相続人が所有していた不動産の名義を、相続人に変更する手続きのことです。不動産の所有権を明確にし、第三者に対しても権利を主張するためにおこなわれます。
2024年4月以降、相続登記が義務化されました。相続の発生から3年以内に相続登記をしなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があるのです。
また、不動産の権利関係が複雑化したり、不動産の売却や活用が困難になったりといったリスクもあり、注意が必要です。
2-3.遺産分割調停や審判に発展する可能性がある
遺産分割協議がまとまらないと、遺産分割調停や審判に発展する可能性があります。
遺産分割調停は家庭裁判所で調停委員のもと話し合いをおこないますが、それでも解決しない場合は審判に移行します。これらの手続きは時間と費用がかかり、精神的な負担も大きくなるでしょう。
また、裁判所が介入すると、必ずしも自分の望む結果にならない可能性もあります。さらに、このような法的手続きを経ると、家族関係の修復がより困難になる傾向があります。
2-4.精神的に疲弊してしまう
相続人同士のトラブルに巻き込まれると、少なからず心身にも支障をきたしてしまいます。精神的に追いつめられて、うつ病を発症するといった事態にもなりかねません。
まずは、自分の健康を最優先に考えるのが大切です。今後の相続手続きでもめるのがわかっているのであれば、はじめから関与しないことも検討しましょう。
2-5.相続税を納めないといけなくなる
仮に多額の財産を引き継ぐとなったとき、相続税を申告しないといけない場合もあります。
相続税は「3,000万円+(600万円×法定相続人数)」まで非課税であり、対象となる人は決して多くはありません。しかし課税者となった場合、課税価格の10〜55%の税金が発生します。
申告は、相続の発生を知った日の翌日から10カ月以内に済ませないといけません。つまり相続トラブルが長引けば、申告に間に合わなくなるリスクも高まります。延滞税に加え、最悪の場合は追徴課税の対象にもなるので、相続税も念頭に置いてください。
2-6.借金の相続が発生する恐れもある
被相続人の残している財産になかには、資産だけではなく負債がまぎれている可能性もあります。相続人が負債を相続した場合、債権者に対する債務の返済義務が生じます。
このような返済義務から逃れるには、相続放棄の申述をして法的に相続権を手放さないといけません。相続放棄は、ときに自分の生活や財産を守ることも覚えておきましょう。
関連記事:【弁護士監修】相続財産に借金が含まれる場合の対処法や手続きの流れ
3.絶縁したい兄弟との相続争いを避ける方法
絶縁したい兄弟との相続争いを避けるには、大きく分けて次の方法があります。
- 相続放棄をおこなう
- 相続分を放棄する
- 相続分を譲渡する
各制度の内容と手続きの方法について紹介します。
3-1.相続放棄をおこなう
相続権を手放す一般的な方法が、相続放棄です。相続放棄は資産をすべて相続しないことを示す意思表示であり、家庭裁判所に申述して効力を発揮します。有効に成立させるためには、相続の発生を知った日から3カ月以内に申述しなければなりません。
相続放棄時の注意点は、単純承認にあたる行為がみられたら効力を失うことです。単純承認にあたる行為には、以下のケースが挙げられます。
- 被相続人の預貯金を私生活や債務弁済に充てた
- 被相続人が所有していた動産や不動産を売却した
- 被相続人の借りていたアパートを解約した
これらの行為は、相続放棄が受理されたあともしてはいけません。
関連記事:相続放棄後にしてはいけないこととは?認められる行為も解説
3-2.相続分を放棄する
相続争いを遠ざける方法として、相続分の放棄も挙げられます。相続分の放棄とは、遺産分割協議において自身は財産を相続しない旨を主張することです。相続放棄と異なり3カ月以内といった期限はありませんが、法的に相続権を失うわけではありません。
そのため被相続人が借金を抱えていた場合、債権者から返済を迫られる恐れがあります。加えて遺産分割協議の署名捺印をしなければなりません。
3-3.相続分を譲渡する
相続分をほかの相続人に譲渡することも、相続争いを避ける方法の一つです。相続分の譲渡は、相続人以外の第三者に対しても認められます。
一方でほかの相続人は、1カ月以内であれば財産を取り戻すことが可能です。したがって第三者に相続分を渡したとしても、結局ほかの相続人が相続するケースも考えられます。
相続分の譲渡は、相続分の放棄と同様に債権者への責任が消滅するわけではありません。債務の返済を迫られる恐れがある点も押さえてください。
3-4.絶縁したい相続人を除外する
家族全員と折り合いが悪いわけではなく、一部の兄弟が原因で疎遠になっている人もいるでしょう。仮に被相続人の資産を相続したいときは、問題のある相続人を除外するといった考え方もあります。
3-4-1.相続欠格事由に当てはまるか確かめる
問題のある相続人を除外する方法の一つに、相続欠格が挙げられます。相続欠格とは、以下の条件に当てはまる人から相続権を奪うことです。
- 被相続人を故意に死亡させて刑に処された
- 被相続人が殺害されたことを知っていたのに告発しなかった
- 詐欺や遺言により遺言書を作らせた
- 詐欺や遺言により遺言書を取り消させた
- 勝手に遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した
これらの事由に当てはまれば、相続権は強制的に失われます。ほかの相続人たちが、裁判所などで相続欠格に関する手続きをする必要もありません。
3-4-2.廃除の申立てを検討する
相続欠格以外にも、家庭裁判所に対する廃除の申立ても検討してみてください。廃除とは、以下の事由に該当する相続人を、被相続人や遺言執行者が除外する方法です。
- 被相続人に虐待をしていた
- 被相続人に対する著しい侮辱行為があった
- その他、著しい非行があった
ただし廃除は必ずしも認められるわけではなく、却下されるケースもあることを覚えておきましょう。
3-4-3.遺言で財産を渡さないようにする
遺言で財産を渡さないことも、特定の相続人を除外する方法の一つです。遺言は、被相続人の意思に基づいてなされる必要があります。したがって被相続が嫌がっているにもかかわらず、強制的に作成させることはできません。
財産を渡されなかった相続人は、原則として遺留分(取得できる遺産の最低額)を請求できます。相手が遺留分を放棄しない限り、基本的にその部分は渡すことになるので注意してください。
関連記事:「遺留分は認めない」と遺言で残せる?遺留分請求を防ぐための対策
4.絶縁したい家族との相続の進め方
様々なリスクや問題から、絶縁したい家族との相続を避けられない方もいるでしょう。その場合、なるべくトラブルにならないためにも、最適な方法で相続を進める必要があります。
ここでは、住所がわかっているケースと住所がわかっていないケースの2つに分けて、相続の進め方を解説していきます。
4-1.住所がわかっているケース
住所がわかっている場合は、法的手続きを通じて相続を進められます。以下の手順に沿ってください。
- 被相続人の死亡を知らせる通知を配達証明付き内容証明郵便で送る
- 相続開始の事実を伝えることで、遺産分割協議への参加を促す
- 相手が応じない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる
- 第三者である調停委員のもとで遺産分割について話し合う
- それでも解決しない場合は、遺産分割審判に移行し裁判官の判断に委ねる
これらの過程では、弁護士に相談するのが賢明です。
4-2.住所がわからないケース
しばらく疎遠になり、絶縁したい家族の住所がわからないケースもあります。その場合は、以下3つの進め方を検討してください。
- 不在者財産管理人を選定する
- 失踪宣告を申し立てる
- 遺産分割調停を申し立てる
それぞれ解説します。
4-2-1.不在者財産管理人を選定する
不在者財産管理人とは、行方不明となった相続人の財産を管理する人のことで、家庭裁判所によって選任されます。不在者財産管理人の選定は、行方不明の相続人の権利を守ることを目的としています。
ただし、この手続きには費用と時間がかかります。また、管理人への報酬も必要です。
4-2-2.失踪宣告を申し立てる
失踪宣告は、長期間行方不明の人を法律上死亡したとみなす手続きです。7年間生死不明の場合に申し立てができ、認められると相続が開始されます。
ただし、失踪宣告後に本人が現れると法的に複雑な状況になる可能性があるため、手続きには慎重な判断が必要となります。また、申立てから宣告までに時間がかかるのが欠点です。
参考:失踪宣告 | 裁判所
4-2-3.遺産分割調停を申し立てる
遺産分割調停の申立ては、相続人の住所がわからない場合でも可能です。家庭裁判所に申立てをおこなうと、裁判所が職権で相手方の住所を調査します。
それでも見つからない場合は、公示送達という方法で手続きを進めます。公示送達は、裁判所の掲示板に通知を掲示すると、一定期間後に相手に通知が届いたとみなす制度です。この方法により、行方不明の相続人がいても遺産分割を進められます。
ただし、相手の権利を制限する可能性があるため、慎重に判断する必要があります。
5.絶縁したい家族との相続が発生したときは弁護士に相談しよう

絶縁したい家族との相続を問題なく進めるためには、弁護士にアドバイスを求めるとよいでしょう。弁護士であれば、相続に関連するほとんどの業務に対応可能です。
最後に、弁護士ならではの強みについてご紹介します。
5-1.相談者に法的な観点からアドバイスできる
弁護士に依頼するメリットの一つが、法的な観点からアドバイスをもらえる点です。相続放棄すべきかの判断だけではなく、トラブルにどう対応すべきかを提示してくれます。
相続手続きには専門的な知見が求められ、素人だけで話し合うとトラブルが複雑化する恐れもあります。弁護士が話し合いに参加すれば、全員が納得のいく形で解決に導けるでしょう。
5-2.相続に関する書類作成ができる
弁護士は、相続に関するさまざまな書類を作成できます。とくに相続放棄を選ぶのであれば、家庭裁判所に対して申述書や回答書を提出しないといけません。添付書類の準備も含め、弁護士に一任したほうが賢明です。
仮に自分も財産を相続する場合は、遺産分割協議書が必要になることもあります。弁護士に依頼し、迅速かつ正確に書類作成ができるようにしましょう。
5-3.遺産分割調停の代理交渉ができる
家族との絶縁を望んでいるものの、財産が少しも渡されないことに不満を感じる人もいるはずです。自分にとって不利な遺産分割がなされたときの対処法として、調停を申し立てるといった選択肢があります。
遺産分割調停とは、家庭裁判所が間に立って遺産分割を巡るトラブルの解決を目指す制度です。基本的に相手と直接顔を合わせませんが、調停委員に交渉するには専門的な知識も必要となります。弁護士が代わりに交渉すれば、自分の要望も叶えやすくなるでしょう。
5-4.精神的なサポートになる
家族と連絡をとっていない人が、一人で相続争いをするのは精神的な負担も大きくなります。仕事や家庭で忙しい人は、さまざまな手続きをするのが面倒に感じてしまうでしょう。
弁護士に相談すれば、大変だと感じる手続きのほとんどを代理でおこなってくれます。相続が原因で、日常生活に支障をきたすのを防ぐ役目も担います。
6.まとめ
相続争いを避けるには、単に家族と絶縁するだけでは足りません。相続放棄をするか、相続分の放棄または譲渡といった手続きを済ませる必要があります。
離脱したいと思っているにもかかわらず、相続争いを続けていると経済面や精神面にさまざまな支障をきたしてしまいます。弁護士のサポートを借りつつ、自分が納得いく形で解決できるようにしましょう。
弁護士法人池袋吉田総合法律事務所では、相続に関する無料相談を受け付けています。相続に関する問題でお困りの方は、ぜひ当事務所までご相談ください。
このコラムの監修者
弁護士法人池袋吉田総合法律事務所は、相続全般、遺産分割、遺留分、相続放棄、生前対策、遺言作成、事業承継、
相続税など、法律のプロとして幅広い案件を取り扱っています。
初回相談は無料です。一人で悩まず、まずは当事務所へご相談ください。

第二東京弁護士会所属





