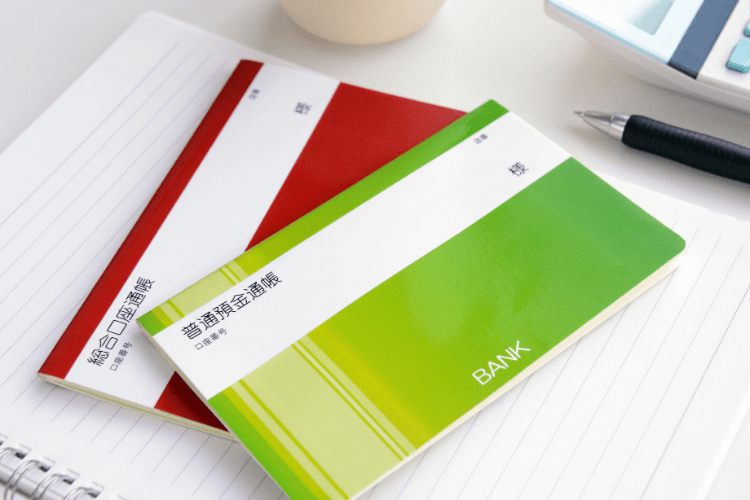
遺産相続を巡り、相続人が被相続人の通帳を見せないといったトラブルに巻き込まれるケースがあります。このような場合、遺産が使い込まれている可能性もあるため、しっかりと調査しなければなりません。
そこでこの記事では、以下の内容を解説していきます。
- 遺産相続における通帳の役割
- なぜ被相続人の通帳を見せてもらえないのか?考えられる理由
- 通帳がなくても自分で故人の預貯金を調査する方法
- 残高証明書を発行する2つの方法
- 通帳を見せてくれない相続人への対処法
相続において、ほかの相続人が被相続人の通帳を見せてくれなくて悩んでいるという方は、ぜひ最後までご覧ください。
このページの目次
1.遺産相続において通帳は重要な書類の一つ
遺産相続において、通帳は重要な書類の一つとされています。ほとんどの人が、お金を銀行に預けているためです。
ただし相続人が通帳を見せてくれず、相続手続きが止まってしまうケースも少なくありません。ここでは、通帳と相続の関係について解説します。
1-1.相続人に通帳を見せるのは義務ではない
被相続人の通帳は重要な書類の一つであるものの、すべての相続人に見せるのが義務づけられているわけではありません。そのため、相続手続きを進めようと思っても、通帳の詳細がわからない相続人がいることはあります。
とはいえ内容が不明確なままでは、いつまでも分配方法を決められません。そこで金融機関や弁護士に依頼すれば、残高の状況を詳しく調べられます。
2.なぜ被相続人の通帳を見せてもらえないのか?考えられる理由
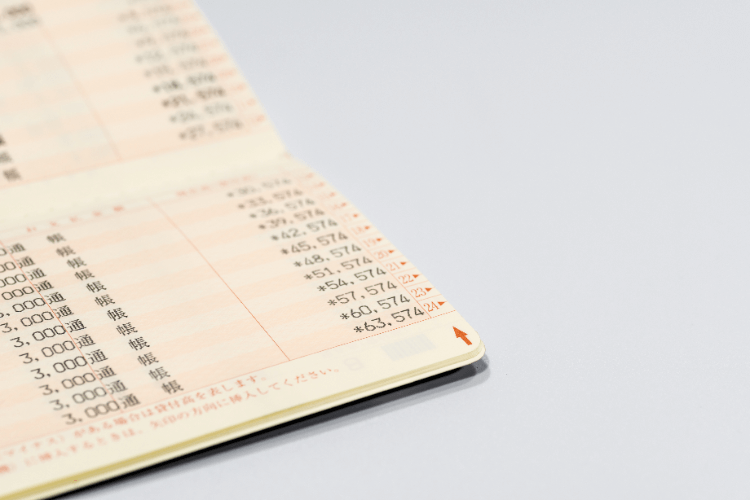
なぜ、ほかの相続人から被相続人の通帳を見せてもらえないことがあるのでしょうか。考えられるのは以下のような理由です。
- 故人の預金の「使い込み」を隠している
- ほかの相続財産を「財産隠し」している
- 単に手続きが面倒か多忙である
- あなたに不信感を抱いている
それぞれ解説します。
2-1.理由①故人の預金の「使い込み」を隠している
最も警戒すべき理由が、故人が亡くなる前後に、その預金を不正に引き出し、自分のために使ってしまった「使い込み」の事実を隠しているケースです。
とくに、生前に故人の財産を管理していた相続人が、故人のキャッシュカードで生活費を引き出したり、自分の口座にお金を移したりしていた場合、その履歴が記された通帳は、不正の決定的な証拠となります。
通帳の開示を頑なに拒む場合は、この使い込みを隠蔽しようとしている可能性をまず疑うべきでしょう。
関連記事:遺産の使い込みが発覚したら?泣き寝入りしないための対処法
2-2.理由②ほかの相続財産を「財産隠し」している
故人の預金だけでなく、ほかに存在している相続財産を意図的に隠し、遺産分割の対象から外そうとしている可能性も考えられます。
たとえば、故人から生前に「贈与された」と主張している高価な貴金属や有価証券が、実際には相続財産に含まれる場合などです。通帳の取引履歴を見られると、故人が亡くなる直前に多額の出金があるなど、ほかの財産の存在を示す手がかりが見つかってしまうのを恐れているのです。
この場合、通帳の開示拒否は、より大きな財産隠しの一端である可能性があります。
2-3.理由③単に手続きが面倒か多忙である
不誠実な意図はなく、単純に、日々の仕事や生活が多忙で、相続手続きを進めるのが面倒だと感じ、後回しにしているだけのケースもあります。
相続手続きでは、多くの書類を集めたり、平日に役所や金融機関へ足を運んだりする必要があります。ほかの相続人から催促されることで、プレッシャーを感じ、かえって対応が遅れてしまうことも考えられます。
この場合は、悪意があるわけではないため、ほかの相続人が手続きを主導して協力する姿勢を見せると、状況が改善するかもしれません。
2-4.理由④あなたに不信感を抱いている
過去の親族間のトラブルなどが原因で、相手があなたに対して、「財産を多く取ろうとしているのではないか」といった、強い不信感を抱いている可能性もあります。この場合、相手は「自分が主導権を握らなければ、不利な条件で遺産分割を進められてしまう」という警戒心から、あえて情報を開示しないという行動に出ることも。
まずは冷静にコミュニケーションを試み、それでも解決しない場合は、公平な第三者である弁護士などを間に入れて、話し合いを進めることが有効です。
関連記事:相続でもめる原因とは?仲の良い家族でも注意したいポイントを解説
3.通帳がなくても自分で故人の預貯金を調査することは可能
通帳が見つからなくても、自分で故人の預貯金を調査することは可能です。ここでは、金融機関でどのような調査ができるかを紹介します。
3-1.まずはどの金融機関を利用していたか調査する
故人の通帳を調べるうえで重要となる情報が、どの金融機関を利用していたかです。支店名がわからなくても、金融機関名さえわかれば問題ありません。
どこで預金口座を開設しているか全くわからないときは、故人の遺品からヒントを探ってみましょう。たとえば金融機関から受け取っている可能性のある封筒やポケットティッシュ、ボールペンなどがヒントになり得ます。これらに金融機関名が記載されていないかをチェックしてみるとよいでしょう。
3-2.相続人であればほかの相続人の同意なく残高証明書を発行してもらえる
故人の口座残高を調べたいときは、金融機関から残高証明書を発行してもらいましょう。法定相続人であれば、ほかの相続人の同意なく単独で発行できます。
残高証明書を発行してもらうにあたって、申立人が当該金融機関の口座を開設している必要はありません。ただし金融機関によっては、発行する際に1,000〜2,000円程度の手数料がかかる場合もあります。無料で提供しているところもあるので、あらかじめ確認しておきましょう。
3-2-1.金融機関での開示請求に必要な書類一覧
金融機関で残高証明をするにあたって、必要となる書類は次のとおりです。
- 残高証明書発行依頼書(金融機関所定のもの)
- 故人の戸籍謄本または除籍謄本(死亡日の記載されたもの)
- 申立人が相続人であることを証明する書類(戸籍謄本など)
- 申立人の身分証明書(運転免許証など)
- 申立人の印鑑証明書および実印
自分で一から集めるのが難しいのであれば、弁護士に収集を依頼するとよいでしょう。
3-3.どの時点の残高証明書を発行すべきか
残高証明書は「故人の死亡日」の残高を発行してもらうのが基本です。誤って現時点のものを取得した場合、取り直しが必要になるケースもあるので注意しましょう。
ただし「故人の死亡日以外」の証明書が追加で必要になるケースもあります。主な例が、遺産分割協議をしたときです。
本人が亡くなり、銀行口座が凍結されるまでは数週間〜1カ月以上かかります。その間に年金や保険金が振り込まれると、死亡日の時点から金額が変わることもあるでしょう。
遺産分割協議でもめないようにするには、故人の口座に動きがない状態で話し合うのが大切です。この場合においては「死亡日」「口座凍結日」の二通りの残高証明書を取得しましょう。
4.残高証明書を発行する2つの方法
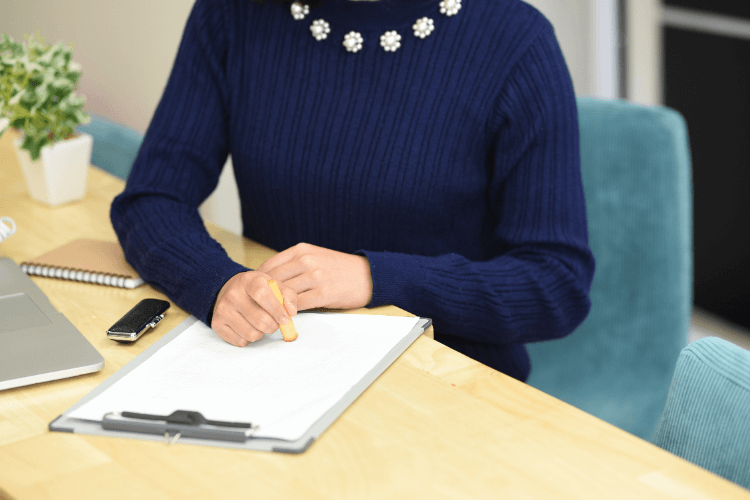
残高証明書を発行するには、大きく分けて2つの方法があります。
- 窓口で発行してもらう
- 郵送で発行してもらう
それぞれの方法のメリットとデメリットについてみていきましょう。
4-1.窓口で発行してもらう方法
必要書類を持って金融機関の窓口に行けば、残高証明書の発行手続きに進みます。発行してもらう手順は次のとおりです。
- 電話やホームページから予約を入れる
- 添付書類とともに「残高証明書の発行請求用紙」を窓口で提出する
- 残高証明書が後日送付される(即日交付されるところもある)
窓口で発行してもらうメリットとデメリットについて紹介します。
4-1-1.窓口で発行してもらうメリット
窓口で発行してもらうメリットとして、手続きの不備を防ぎやすい点が挙げられます。仮に手続き上の不備が発生しても、その場で修正が可能です。
また職員に直接質問しながら、書類等を作成できる点もメリットの一つです。以上から郵送と比べると、正確かつスムーズに手続きを進められるでしょう。
4-1-2.窓口で発行してもらうデメリット
窓口で発行してもらうデメリットは、金融機関へ訪問する手間がかかる点です。基本的に金融機関の窓口は、平日の日中しか空いていません。
平日に仕事がある人は、金融機関に訪問する時間をつくるのが難しいでしょう。普段が忙しくて余裕のない人は、郵送で発行してもらったほうが望ましい場合もあります。
4-2.郵送で発行してもらう方法
窓口に訪問しなくても、次の手順を踏めば郵送で手続きすることが可能です。
- 口座開設先の金融機関から「残高証明書の発行請求用紙」を取り寄せる
- 「残高証明書の発行請求用紙」を作成および郵送する
- 残高証明書が後日送付される
同じく郵送で発行してもらうメリットとデメリットについてまとめます。
4-2-1.郵送で発行してもらうメリット
郵送で発行してもらうメリットは、遠隔地からでも手続きができる点です。故人と離れて暮らしていた人は、取引先の金融機関を訪問するのが難しいでしょう。窓口に訪問する手間も省けるので、時間の節約にもつながります。
4-2-2.郵送で発行してもらうデメリット
郵送で残高証明書を取得するデメリットは、窓口に訪問するよりもコストと日数がかかる点です。郵送に必要な封筒や切手を、返信用のものと一緒に用意しなければなりません。
また金融機関から残高証明書を送るとなれば、書類が届くまである程度の日数がかかります。その日のうちに書類を揃えたい人にはおすすめできません。
5.通帳を見せてくれない相続人への対処法【3ステップ】
被相続人の通帳を見せてくれない相続人がいたら、以下のステップを踏んで対処しましょう。
- 内容証明郵便で正式に開示を請求する
- 自分で金融機関に「取引履歴」の開示を請求する
- 弁護士に依頼し「弁護士会照会」で調査する
各ステップで意識すべきポイントをまとめます。
5-1.①内容証明郵便で正式に開示を請求する
まず内容証明郵便を活用し、相続人に開示請求をしてみるとよいでしょう。内容証明郵便とは、「いつ・誰に・どのような内容」で通知をしたかを証明するための制度です。
もちろん内容証明郵便を利用したからといって、相続人が必ず開示してくれるとは限りません。しかし相続人に対して通知したのが記録として残るため、裁判に発展した場合の証拠となります。
5-2.②自分で金融機関に「取引履歴」の開示を請求する
相続人が開示してくれないときは、自ら金融機関に「取引履歴」の開示を請求しましょう。相続人が通帳を見せない場合、勝手にお金を使い込んでいるケースも考えられます。
仮に相続人がお金を使い込んだとしても、取引履歴を開示すれば発見できるようになります。取引履歴は最大10年分まで調査できるため、弁護士の力を借りながら念入りに調べるとよいでしょう。
5-3.③弁護士に依頼し「弁護士会照会」で調査する
自分で金融機関に開示するだけではなく、弁護士照会を活用するのも効果的です。弁護士照会とは、弁護士会が企業に対して必要な事項を調査することを指します。
複雑な手続きを弁護士がほとんど対応してくれるため、被相続人が複数の金融機関で取引している可能性があるときにもおすすめです。
6.もし遺産の使い込みが発覚したらどうする?
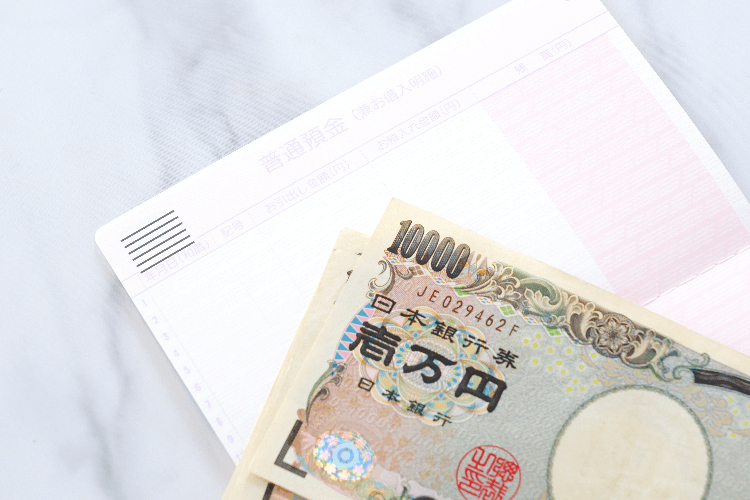
もしほかの相続人による遺産の使い込みが発覚したら、どのような対応をとるべきなのでしょうか。ここからは、使い込まれた金銭を取り返すうえで、どのような対応をすればよいかを解説します。
6-1.まずは遺産分割協議の場で尋ねてみる
まずは遺産分割協議の場で、本人に対して直接故人のお金を使い込んだことについて確認してみましょう。口座の取引履歴や領収書などに証拠が残っていれば、話し合いの際に用意するのをおすすめします。
遺産を使い込んだ者が相続人である場合、遺言や遺産分割協議で特別な決めごとがなければ、相続分以外の分を返してもらうのが原則です。相続人でない場合は、基本的に全額の返還を要求できます。
6-2.解決しない場合は遺産分割調停を申し立てる
直接の話し合いで解決しないのであれば、遺産分割調停を申し立てるのも方法の一つです。遺産分割調停とは、争っている両者の間に家庭裁判所の調停委員が入り、解決を目指す手続きを指します。
基本的に意見は調停委員を介して伝えられるので、感情的に言い争うのを防ぎやすくなるのが主なメリットです。ただし家庭裁判所が審判を下すわけではなく、相続人全員の合意が得られないと調停が不成立になる場合もあります。
6-3.使い込まれたお金は「不当利得」として返還請求できる
使い込まれたお金は、不当利得として返還請求をすることが可能です。不当利得は正当な権利がないにもかかわらず、他人に損害を与えて得た利益を指します。
一般的に返還請求できる分は、現存利益のみです。一方で相手が悪意(正当な権利がないのを知っている者)であれば、利息も含めて全額の請求が認められます。
6-4.話し合いで解決しない場合は「不当利得返還請求訴訟」も視野に入れる
不当利得は内容証明郵便でも請求できますが、解決しない場合は「不当利得返還請求訴訟」を検討しましょう。訴訟して確定判決が得られれば、法的に不当利得の返還が認められます。
相手が判決に従わない場合は、強制執行で金銭を回収できます。訴訟を有利に進めるには、相続問題に強い弁護士へ相談しましょう。
7.まとめ
相続人が被相続人の通帳を見せないときは、金融機関で残高証明書を請求するのが得策です。ただし手続きするには、どの金融機関で取引していたかを押さえなければなりません。まずは被相続人の遺産を頼りに、ヒントを探してみるのをおすすめします。
相続人が遺産を使い込んでいるのが発覚したら、遺産分割調停や不当利得返還請求訴訟を検討してみましょう。相続人全員の権利に関わる問題となるため、弁護士に相談しながら解決を目指すようにしてください。
弁護士法人池袋吉田総合法律事務所では、相続に関する無料相談を受け付けています。相続に関する問題でお困りの方は、ぜひ当事務所までご相談ください。
このコラムの監修者
弁護士法人池袋吉田総合法律事務所は、相続全般、遺産分割、遺留分、相続放棄、生前対策、遺言作成、事業承継、
相続税など、法律のプロとして幅広い案件を取り扱っています。
初回相談は無料です。一人で悩まず、まずは当事務所へご相談ください。

第二東京弁護士会所属





