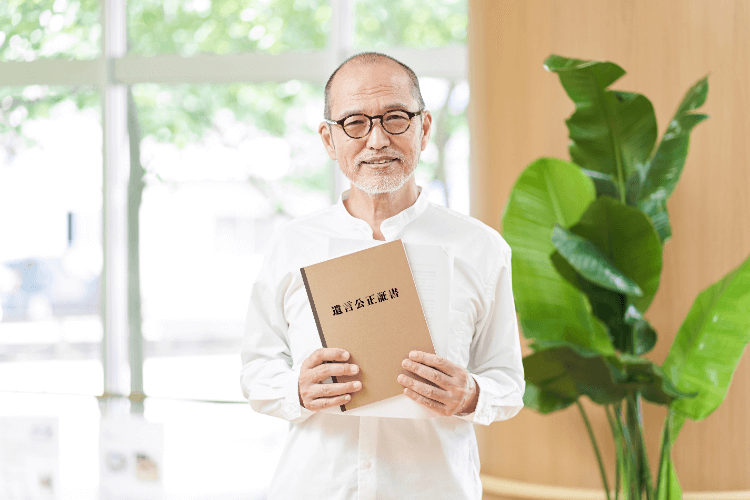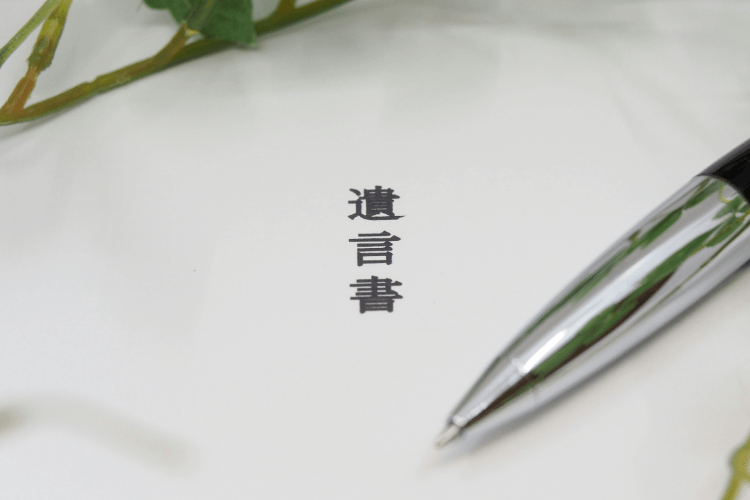法的に最も安全とされる「公正証書遺言」。しかし、その完璧なはずの遺言書が、かえって深刻な親族トラブルの火種になるケースも、実は少なくありません。一体なぜ、法的に安全な公正証書遺言をもってしてでも、家族間でもめてしまうのでしょうか。
そこで記事では、以下の内容を解説していきます。
- 公正証書遺言があってももめるケース
- 公正証書遺言がある相続でもめないためのポイント
- 公正証書遺言があるのにもめた場合の対応策と解決方法
- 公正証書遺言を作成する際の注意点
公正証書遺言がある相続を控えている方や、公正証書遺言がある相続ですでにトラブルが起きている方は、ぜひ最後までご覧ください。
このページの目次
1.公正証書遺言があってももめるケース
公正証書遺言があってももめるケースは、以下のような場合です。
- 遺言書の内容に問題があった場合
- 遺言書作成のプロセスに問題があった場合
- その他の要因に問題があった場合
それぞれのケースごとに解説します。
1-1.遺言書の内容に問題があった場合
公正証書遺言でトラブルになる最も一般的な原因は、遺言書の内容そのものに、争いの火種となる問題が含まれているケースです。主に以下のようなケースです。
- 遺言の内容が不明確・曖昧だった
- 公正証書遺言に明記されていない財産があった
- 法定相続分について考慮されていない
- 特定の相続人の遺留分を侵害している
- 認知している子どもの存在を伝えていなかった
それぞれ解説します。
1-1-1.遺言の内容が不明確・曖昧だった
遺言書に書かれた財産の指定が不明確であったり、誰に相続させるかの表現が曖昧だったりすると、その解釈をめぐって相続人間で争いが生じることがあります。
たとえば、「預貯金の一部を長男に」といった曖昧な表現が残ってしまうと、「預貯金の一部とは具体的にいくらなのか」という点で、あとから揉める原因になります。遺言書は、誰が読んでも一通りにしか解釈できない具体性が不可欠です。
1-1-2.公正証書遺言に明記されていない財産があった
遺言書に、全ての財産の分け方が明記されておらず、記載漏れの財産があった場合、その財産については遺言の効力が及びません。そのため、記載のない財産については、相続人全員であらためて「遺産分割協議」をおこない、その分け方を決める必要があります。
遺産分割協議の話し合いがまとまらないと、後々相続トラブルに発展してしまいます。
1-1-3.法定相続分について考慮されていない
法律で定められた相続の割合である「法定相続分」を完全に無視した内容の遺言書も、トラブルの原因となる可能性があります。
法定相続分は、あくまで相続を進める際の目安であり、通常公正証書遺言はそれより優先されます。しかし、あまりにも法定相続分からかけ離れた内容ですと、財産をもらえなかった相続人の不満が高まり、後述する遺留分の請求や、遺言の無効を主張する争いに繋がりやすくなります。
関連記事:遺言書で一人に相続させることは可能?一人に相続する遺言書の作り方
1-1-4.特定の相続人の遺留分を侵害している
遺言書の内容が、「全財産を長男一人に相続させる」というように、特定の相続人に偏っている場合、他の相続人の「遺留分」を侵害している可能性が高いです。遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人に、法律上最低限保障されている遺産の取り分です。
遺留分を侵害された相続人は、財産を多く受け取った人に対して、その侵害額に相当する金銭の支払いを請求できます(遺留分侵害額請求)。この遺留分侵害額請求をめぐり、家族間でトラブルになる発展する可能性があります。
1-1-5.認知している子どもの存在を伝えていなかった
故人が、家族の知らない間に婚外子などを「認知」していた場合、その子も、法律上実子と全く同じ相続権を持ちます。もし、婚外子の存在を考慮せず、ほかの相続人だけで遺産分割を進めてしまうと、あとからその子が現れて、相続のやり直しを求める可能性があります。
遺言書を作成する際は、全ての相続人を正確に把握しておく必要があります。
1-2.遺言書作成のプロセスに問題があった場合
遺言書の内容だけでなく、その作成プロセスに法的な問題があったと主張されることで、遺言の有効性そのものが争いの対象となるケースもあります。
- 法的要件の不備があった
- 認知症で意思能力がない状態だった
- 口授の有効性が疑われる
- 不適格な証人のもとで遺言書が作成された
- 遺言執行者が不適切に選任されているまたは不在
公正証書遺言は、このリスクが低いのが特徴ですが、ゼロではありません。それぞれ解説します。
1-2-1.法的要件の不備があった
公証人が作成に関与する公正証書遺言で、日付の記載漏れなどの形式的な不備が起こることはまずありません。
しかし、遺言の証人として、法律で定められた不適格な人物(未成年者や、遺産を受け取る予定の相続人など)が立ち会っていたといったケースでは、遺言そのものが無効になる可能性があります。
1-2-2.認知症で意思能力がない状態だった
遺言者が、遺言を作成した当時すでに認知症が進行しており、ご自身の判断能力(意思能力)がなかったとほかの相続人が主張する場合、遺言の有効性そのものを争う深刻な裁判に発展することがあります。
たとえ公正証書遺言であっても、意思能力がない状態で作られたものは法的に無効です。意思能力がない状態を証明するためには、当時の医療記録や介護の状況といった、客観的な証拠が必要となります。
1-2-3.口授の有効性が疑われる
公正証書遺言は、遺言者が公証人に対して遺言の内容を口頭で伝える(口授する)ことが、法律で定められています。
もし、遺言者がほとんど話せない状態で公証人の質問に頷いただけだった、といったケースでは、この「口授」の要件を満たしていないとして、遺言の有効性が争われる可能性があります。
1-2-4.不適格な証人のもとで遺言書が作成された
公正証書遺言を作成する際には、2人以上の証人の立ち会いが必要です。そして法律で、以下のような立場の場合は証人になることができない「欠格者」と定められています。
- 未成年者
- 遺産を受け取る可能性がある相続人
- 相続人の配偶者や直系血族
もし、この欠格者が証人として立ち会っていた場合、その公正証書遺言は無効になってしまいます。遺言書が無効になった場合、遺産分割協議による相続人同士での話し合いが必要です。その遺産分割協議において、相続人同士でもめる可能性が考えられます。
1-2-5.遺言執行者が不適切に選任されているまたは不在
遺言の内容を実現する「遺言執行者」が、遺言書の中で利害関係のある人物に指定されていると、ほかの相続人から「手続きが不公平だ」といった不満が出て、トラブルになることがあります。
また、遺言執行者が指定されていない場合は、相続人全員の協力が必要となり、一人でも非協力的な人がいると相続手続きが滞ってしまいます。
1-3.その他の要因に問題があった場合
遺言書の内容や、作成プロセスに法的な問題がなくても、それ以外の感情的な要因などが、相続トラブルを引き起こすこともあります。以下のようなケースです。
- 相続人間の関係が悪い
- 公序良俗に反している
ひとつずつ解説します。
1-3-1.相続人間の関係が悪い
相続が始まる前から、相続人である兄弟姉妹の関係が悪化している場合は、どんなに公平な内容の遺言書があっても、何らかの理由をつけて相手への不満を主張し、トラブルに発展しやすい傾向があります。
遺言書は、あくまで法的な問題を整理するものであり、家族間の感情的なしこりまでを解決できるわけではありません。
1-3-2.公序良俗に反している
遺言書の内容が、常識的に見て社会の秩序や道徳に反する「公序良俗違反」と判断された場合、その部分が無効になることがあります。
たとえば、「愛人に全財産を相続させ、長年連れ添った妻には一円も渡さない」といった、あまりに不公平で家族の生活基盤を脅かすような内容が、これにあたる可能性があります。
2.公正証書遺言がある相続でもめないためのポイント
法的に強力な公正証書遺言であっても、相続トラブルを完全に防ぐためには、以下のような残される家族への「配慮」を尽くすことが何よりも重要です。
- 遺言の内容を相続人と話し合う
- 遺言内容を明確かつ具体的に記載する
- 遺言作成時に立会人や証人を適切に選定する
- 遺言執行者を信頼できる人物に選任する
- 遺留分を考慮に入れた遺言書を用意する
- 相続人全員に遺言の存在と内容を伝える
- 遺言の保管場所やアクセス方法を明確にする
法律的な有効性だけでなく、相続人全員の感情にも配慮した遺言書こそが、真に「もめない遺言」となります。詳しく解説します。
2-1.遺言の内容を相続人と話し合う
可能であれば、遺言書を作成する前に、なぜそのような内容にしたいのか、ご自身の想いを相続人となる家族に伝えておきましょう。
もちろん、内容の全てを話す必要はありません。しかし、生前にコミュニケーションをとっておくことで、相続人たちが遺言に込められたあなたの真意を理解し、納得しやすくなります。相続時の、感情的な対立を和らげる効果が期待できるでしょう。
2-2.遺言内容を明確かつ具体的に記載する
遺言書の内容は、誰が読んでも一通りにしか解釈できないよう、明確かつ具体的に記載することが非常に重要です。
「預貯金の一部」といった曖昧な表現は避け、「〇〇銀行〇〇支店の普通預金口座(口座番号12345)の全て」というように、財産を特定して記載しましょう。不動産であれば、登記簿謄本に記載されている通り、正確に記載します。
遺言に記載する内容の具体性が、解釈をめぐる争いを防ぎます。
2-3.遺言作成時に立会人や証人を適切に選定する
公正証書遺言の作成には、2人以上の証人が必要です。そして証人には、利害関係のない中立的な第三者を選ぶことが、あとのトラブルを防ぐうえで極めて重要です。
もし、財産を多く受け取る相続人の配偶者などが証人になると、他の相続人から「遺言の内容に影響を与えたのではないか」と、あらぬ疑いをかけられる原因になります。誰に頼んで良いか分からない場合は、公証役場で、信頼できる証人を紹介してもらうことも可能です。
2-4.遺言執行者を信頼できる人物に選任する
あらかじめ遺言書にて、遺言の内容をあなたに代わって実現する「遺言執行者」を指定しておきましょう。その際、信頼できる人物を選任すると良いです。
相続人同士の関係が複雑な場合は、相続人の一人を執行者にすると、ほかの相続人の反感を買う可能性があります。そのような場合は、弁護士や司法書士、信託銀行といった、中立的な立場の専門家を遺言執行者に指定することで、公平かつ円滑に手続きを進めることができます。
2-5.遺留分を考慮に入れた遺言書を用意する
特定の相続人に多くの財産を遺す場合でも、必ず遺留分に配慮するようにしましょう。一部の相続人の「遺留分」を完全に無視した内容は、将来の「争続」の火種となるためです。
遺留分は、法律で保障された、相続人の最低限の権利です。遺言書でこの権利を侵害すれば、相続開始後に、遺留分侵害額請求という金銭トラブルに発展することは避けられません。あらかじめ、遺留分に相当する金銭を、他の相続人に遺すといった配慮が、円満な相続を実現します。
関連記事:「遺留分は認めない」と遺言で残せる?遺留分請求を防ぐための対策
2-6.相続人全員に遺言の存在と内容を伝える
遺言書を作成したあとは、その存在を、相続人となる方全員に伝えておくのが望ましいです。
遺言書の存在が知らされないままだと、相続人たちは、遺言書がないものとして遺産分割協議を進めてしまいます。そのためあとで遺言書が見つかったとき、協議を全てやり直す必要があり、大きな混乱とトラブルの原因となる可能性が高いです。
遺言書の存在とともに、その内容も伝えておくことで、相続人たちが心の準備をすることもできるでしょう。
2-7.遺言の保管場所やアクセス方法を明確にする
公正証書遺言を作成した場合、その原本は、公証役場で厳重に保管されます。そのため、相続人に対しては、「遺言書を作成した」という事実と共に、「どこの公証役場で作成したか」を明確に伝えておくことが重要です。
公正証書遺言が保管されている公正役場がどこかを伝えておくことで、相続が開始したあとに相続人たちが遺言書の謄本をスムーズに請求できます。公正証書遺言が見つからないという事態を防ぐための、重要なポイントです。
3.公正証書遺言があるのにもめた場合の対応策と解決方法
公正証書遺言の内容をめぐって相続人間でトラブルになってしまった場合は、以下の対応策と解決方法を実践してください。
- 遺言の有効性を確認する
- 相続人間で話し合う
- 弁護士へ相談する
- 家庭裁判所へ調停・審判を申し立てる
- 訴訟を提起する
- 遺留分侵害額請求権を行使する
それぞれ解説します。
3-1.遺言の有効性を確認する
まず、その公正証書遺言が法的に有効なものとして作成されているか、その前提を確認してください。たとえば、遺言者が作成当時に重度の認知症で判断能力がなかった可能性や、証人が法律で定められた欠格者であった可能性などです。
もし、遺言を無効にできる明確な証拠があれば、遺言の有効性そのものを争う道が開かれます。
3-2.相続人間で話し合う
公正証書遺言の内容に不満を持つ相続人がいる場合でも、すぐに法的な対立に入るのではなく、相続人全員でもう一度話し合いの場を持つことが、円満な解決への第一歩です。
相続人間での話し合いがまとまったうえで全員がその内容に合意すれば、遺言書とは異なる内容で、相続の方法を決めることも可能です。
3-3.弁護士へ相談する
当事者同士での話し合いが困難な場合や、法的な主張の妥当性を客観的に判断したい場合は、相続問題に詳しい弁護士へ相談することをおすすめします。
弁護士は、あなたの代理人として、ほかの相続人との交渉をおこなってくれます。また、あなたの状況においてどのように主張するのがより有利な結果に繋がるか、専門的な視点からアドバイスをしてくれるでしょう。
3-4.家庭裁判所へ調停・審判を申し立てる
相続人間の話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てる方法があります。調停では、裁判所の調停委員という中立的な第三者が間に入り、双方の主張を聞きながら、円満な解決を目指します。
参考:遺産分割調停 | 裁判所
もし、遺産分割調停でも合意に至らない場合は、裁判官が一切の事情を考慮して分割方法を決定する「遺産分割審判」という手続きに移行します。
3-5.訴訟を提起する
遺言の有効性そのものに疑いがある場合は、地方裁判所に「遺言無効確認訴訟」を提起してください。
遺言無効確認訴訟とは、遺言者が作成当時に意思能力を欠いていたといった理由で、遺言書が法的に無効であることを裁判所に確定してもらうための、最終的な法的手続きです。勝訴すれば、遺言はなかったことになり、法定相続分にもとづいて遺産分割をやり直すことになります。
3-6.遺留分侵害額請求権を行使する
遺言の有効性は認めるものの、その内容が、法律で保障されたご自身の最低限の取り分(遺留分)を侵害している場合は、「遺留分侵害額請求権」を行使しましょう。これは、遺産を多く受け取った相続人に対して、侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを法的に請求する権利です。
遺留分侵害額請求権」の行使は、相続の開始と、遺留分侵害を知ったときから1年以内におこなう必要があります。
関連記事:相続で遺留分がもらえないときはどうする?具体的な対処法を解説
4.公正証書遺言を作成する際の注意点
公正証書遺言を作成する際は、以下の4点に注意して作成してください。
- 公証人との事前相談の重要性
- 必要書類の準備と確認
- 遺言内容の変更や撤回の手続き
- 遺言書の保管と管理方法
一つずつ解説します。
4-1.公証人との事前相談の重要性
公正証書遺言を作成する際は、いきなり本番の手続きに進むのではなく、事前に公証人との綿密な打ち合わせをおこなうことが非常に重要です。
事前の相談を通じて、公証人は、あなたが希望する遺産の分割方法が法的に実現可能か、また、将来的な家族間のトラブルにつながる恐れがないかなどを、法律の専門家として客観的に確認してくれます。
公証人と遺言書の内容を事前にすり合わせることで、遺言書の有効性と完全性を高め、意図した通りの相続を実現できるようになります。
4-2.必要書類の準備と確認
公正証書遺言を作成するために、以下のような書類を準備してください。
- 遺言者ご本人の確認書類
- 相続人・受遺者(財産を受け取る人)に関する書類
- 財産に関する書類(遺言書に記載する財産すべて)
- 証人に関する書類
これらの書類を事前に、そして正確に準備しておくことで、公証役場での手続きがスムーズに進みます。詳しくは、以下のようなページをご覧ください。
参考: Q3.公正証書遺言をするには、どのような資料を準備すればよいでしょうか? | 日本公証人連合会
4-3.遺言内容の変更や撤回の手続き
遺言者は、遺言書を作成したあとであっても、その内容を自由に何度でも変更したり、全体を撤回(取り消し)することができます。
すでに作成した公正証書遺言の内容を変更したい場合は、これとは異なる内容の新しい遺言書を作成します(その際、新しい遺言書を公正証書にする必要はありません)。この場合、作成日が最も新しい遺言書の内容が、以前の遺言より優先され、法的に有効となります。
4-4.遺言書の保管と管理方法
公正証書遺言を作成した場合、法律により、その原本は公証役場にて厳重に保管されます。そのため、自筆証書遺言のように、紛失したり、誰かに隠されたり、書き換えられたりする心配がありません。
遺言者本人には、その写しである「正本」と「謄本」が渡されます。相続人には、この正本・謄本の保管場所を伝えておくか、あるいは、遺言を作成した公証役場の名前を伝えておくだけで十分です。
5.まとめ
この記事では、公正証書遺言がもめる原因から、それを防ぐための作成時のポイント、そして、もめてしまった場合の解決策までを網羅的に解説しました。
真に「もめない遺言」とは、法的な形式が整っているだけでなく、遺留分をはじめとする、残される相続人全員の感情に配慮されたものです。
公正証書遺言は、単に財産の分配方法を指示したものではなく、相続人となる家族に対する最後のメッセージです。その大切な想いを争いの種にしないためにも、公正証書遺言の作成時から弁護士をはじめとした専門家に相談し、確実な文書を作成するようにしましょう。
弁護士法人池袋吉田総合法律事務所では、遺言書作成や相続に関する無料相談を受け付けています。遺言書に関する問題でお困りの方は、ぜひ当事務所までご相談ください。
このコラムの監修者
弁護士法人池袋吉田総合法律事務所は、相続全般、遺産分割、遺留分、相続放棄、生前対策、遺言作成、事業承継、
相続税など、法律のプロとして幅広い案件を取り扱っています。
初回相談は無料です。一人で悩まず、まずは当事務所へご相談ください。弁護士 吉田 公紀
第二東京弁護士会所属