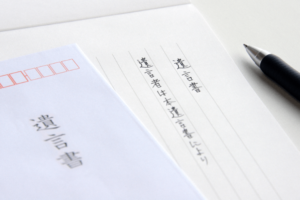遺言書作成に関するこんなお悩みはありませんか?
- どの形式の遺言書を選べば良いのかわからない
- 法律で定められた最低限の取り分(遺留分)の扱いが分からず不安
- 専門家に頼むべきか、自分で書けるのか判断がつかない
- お世話になった人や内縁の配偶者などに財産を遺したいが、どうすれば良いかわからない
- 自宅や土地などの不動産をどう相続するか決められない
- 遺言書の話を家族に切り出すタイミングがわからない
- 完成した遺言書をどこに保管すればいいのかわからない
- 家族への感謝の気持ちや財産の分け方に関する想いをどう書き残せば良いか悩んでいる
東京・埼玉などのエリアで遺言書作成のサポートなら池袋吉田総合法律事務所にお任せください!
遺言書がないとどうなるの?
相続人全員での「遺産分割協議」が必要になる
遺言書がない場合、誰がどの財産をどれくらい相続するのかを、法定相続人全員で話し合って決める必要があります。これを「遺産分割協議」といいます。
この協議がまとまらないと、預貯金の解約や不動産の名義変更といった相続手続きを一切進めることができません。
相続手続きが複雑になる
遺言書があればスムーズに進む手続きも、遺言書がない場合は煩雑になるケースも多いです。
相続人が多い場合や、代襲相続が発生している場合などは、とくに対応が複雑になります。
相続人同士で「争い」が起きやすくなる
遺産分割協議は、必ずしもスムーズに進むとは限りません。各相続人の希望や思惑がぶつかり合い、感情的な対立から深刻なトラブルに発展するケースは非常に多いです。
こじれると家庭裁判所での調停や審判に移行することになり、解決までに長い時間と費用、そして大きな精神的負担がかかります。
故人の想いが反映されない
遺言書がなければ、故人の「誰に、何を、どのように遺したいか」という想いを法的に実現することはできません。
そのため財産を渡したい人に渡せなかったり、希望通りの配分ができなかったりします。
遺言書を作成するメリット
誰に何を相続するか明確にできる
遺言書を作成すると、「誰に」「どの財産を」相続させるのかをご自身の意思で具体的に指定できます。「自宅不動産は妻に」「預貯金は長男に」と明確に定めると、相続人たちが財産の分け方で悩んだり、対立したりするのを防げます。とくに分けにくい財産がある場合に大きな効果を発揮します。
相続手続きの負担を軽くできる
遺言書がある場合、相続開始後の法的な手続きが簡略化され、ご家族の負担を大きく軽減できます。遺言書がないと必要になる相続人全員の戸籍集めや、全員の署名と実印が必要な遺産分割協議書の作成といった、手間のかかる作業を省略できるのです。ご家族は故人を偲ぶ時間に専念できます。
感謝の想いを言葉で伝えられる
遺言書には、財産の分け方だけでなく、ご家族への感謝や想いを「付言事項」として書き残せます。なぜそのように分けたのかという理由や「ありがとう」という言葉が、ご家族の納得感を高めます。
これが、相続人同士の無用な誤解や対立を防ぐ潤滑油の役割を果たしてくれるのです。
後継者へ会社を円滑に託せる
遺言書で後継者を指定すると、会社の株式などをスムーズに承継でき、経営の安定を図れます。
株式が法定相続人に分散すると、会社の経営権が不安定になる恐れがあります。遺言書で後継者に株式を集中させると、円滑な事業承継の実現が可能です。会社の未来を守るために重要な手続きです。
法定相続とは違う配分にできる
遺言書があれば、法律で定められた相続分(法定相続分)とは異なる割合で、自由に財産を配分できます。たとえば、長年ご自身の介護を担ってくれたお子様に多くの財産を遺すなど、ご家族の実情やご自身の想いに合わせた、公平で柔軟な相続が実現可能です。想いを財産配分に反映させましょう。
お世話になった人にも財産を遺せる
遺言書を用いると、法律上の相続人ではない方にも、感謝の気持ちとして財産を遺す「遺贈」ができます。長年連れ添った内縁の配偶者や、子の嫁、お世話になったご友人など、大切な方へ財産を贈れます。ご自身の感謝の想いを形にするための有効な手段です。
未成年の子の将来を守ることができる
遺言書で「未成年後見人」を指定すると、万一の際に信頼できる人にお子様の身上監護や財産管理を託せます。親権者がいなくなってしまった未成年のお子様のために、誰に面倒を見てもらうかをあらかじめ決めておけるため、お子様の将来の生活と財産の安心に繋がるのです。
遺言書作成で当事務所が選ばれる理由
遺言書作成に対する豊富な実績と高い専門性
当事務所は、これまで遺言書作成に関して多くの案件を取り扱ってきました。そのため、さまざまなケースに対応可能な経験とノウハウがあります。
代表弁護士をはじめとする経験豊富な弁護士が、一人一人にあわせて的確にアドバイスさせていただきます。
気軽に相談できる「初回60分無料相談」と明確な料金体系
初めて弁護士に相談する方でも安心な、初回60分の法律相談を無料で実施しています。まずは専門家の話を聞いてから正式に依頼するかどうかをじっくり検討可能です。
また、遺言書作成費用は、サービス内容に応じた料金体系が事前に明示されているため、安心してご依頼いただけます。
多忙な方でも利用しやすい便利なアクセスと柔軟な対応
当事務所は、池袋駅東口から徒歩3分と、どなたでもアクセスしやすい場所にあります。
さらに、事前にご予約いただければ、平日夜間や土日祝日の相談にも対応しているため、仕事などで平日の日中はお時間が取れない方でも、スケジュールを調整しやすい体制が整っています。
依頼者の心に寄り添う親身なサポート体制
当事務所は、「あなたの味方となり、親身にサポート」という理念を掲げています。法律的な問題解決だけでなく、依頼者の気持ちに寄り添う姿勢を大切にしています。
複数の弁護士がチームとなって案件に対応するため、多角的な視点から最適な遺言書の内容を検討・ご提案可能です。
代表弁護士から遺言書作成をご検討中の皆様へ

池袋吉田総合法律事務所代表弁護士の吉田 公紀です。この度は、数ある法律事務所の中から当事務所のWebサイトをご覧いただき、誠にありがとうございます。
遺言書は、残される大切なご家族への「愛情のこもった贈り物」だと私は考えています。しかし、その想いが法的に正しく表現されていないと、かえってご家族の間に争いの種を生んでしまうリスクもあります。
私たちは、皆様一人ひとりの大切な想いを丁寧にヒアリングし、将来のトラブルを防ぐ盤石な遺言書の作成をサポートします。ご家族がこれからも円満であり続けるために、あなたの想いを形にするお手伝いをさせてください。まずはお気軽にご相談ください。
遺言書作成の流れ
①お問い合わせ・初回無料相談のご予約
お電話またはお問い合わせフォームより、ご予約をお願いいたします。
遺言書に関する初回相談は無料ですので、「何から始めればいいか分からない」という段階でもお気軽にご連絡ください。

②弁護士による初回無料相談
初回のご相談は、ご家族の状況や財産の内容、そして「誰に、何を、どのように遺したいか」といったご自身の想いや希望を伺う重要なステップです。守秘義務があるため、安心してお話をしていただけます。
この際に、今後の流れや費用の概算についてもご説明いたします。

③遺言内容のプランニングと方針決定
初回相談でのヒアリング内容をもとに、将来のトラブルを未然に防ぐための最適な遺言内容や、最も確実な「公正証書遺言」などの遺言書の種類を一緒に検討し、方針を決定します。
方針と費用にご納得していただきましたら、正式な契約となります。

④遺言書の文案作成と確認
弁護士が決定した方針に基づき、法的に有効で、かつご自身の想いが正確に反映された遺言書の文案を作成します。
作成された文案は、修正や追加のご希望に沿った調整にも対応いたします。

⑤遺言書の完成
文案が確定したら、いよいよ遺言書の完成です。
公正証書遺言の場合、公証役場との打ち合わせや必要書類の準備は、すべて弁護士が代行いたしますので、手間をかけることなくスムーズに手続きを終えることが可能です。

⑥アフターフォロー
遺言書作成後も、必要に応じて、完成した遺言書の保管方法に関するアドバイスや、将来家族構成や財産状況に変化があった際の書き換え(見直し)といった、継続的なサポートをさせていただきます。
遺言書作成のサポート費用
| 遺言書作成 | 着手金:16万5,000円 |
| 相続財産調査 | 着手金:11万円~ |
※公正証書作成費用は別途。
※詳細はご相談時にお見積り。
当事務所へのアクセス
| 事務所名 | 弁護士法人池袋吉田総合法律事務所 |
| 代表者名 | 吉田 公紀(第二東京弁護士会/弁護士登録番号:49382) |
| 住所 | 〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-18-36 富美栄ビル602 |
| 電話番号 | 03-6709-1710 |
| FAX | 03-6709-1711 |
JR「池袋」駅から徒歩8分
都電荒川線「都電雑司ヶ谷」駅から徒歩6分
東京メトロ有楽町線「東池袋」駅から徒歩6分
遺言書作成に関するよくあるご質問
Q.遺言書は誰でも作成できますか?
A.遺言書は、満15歳以上で、遺言の内容や結果を理解できる判断能力がある方であれば作成可能です。ただし、認知症などで意思能力がないと判断される場合は、遺言書が無効となることがあります。
Q.自筆証書遺言と公正証書遺言の違いは何ですか?
A.自筆証書遺言は、遺言者が自筆で作成するもので、費用がかからず手軽ですが、形式不備により無効となるリスクがあります。
一方、公正証書遺言は、公証人が関与して作成するため、法的な安全性が高く、原本が公証役場に保管されるため紛失や偽造の心配が少ないです。
Q.遺言書を作成するのに最適なタイミングはいつですか?
A.遺言書は、体調が安定しており、判断能力が確かなうちに作成するのが望ましいです。特に、家族構成や財産状況に変化があった場合は、その都度見直すことをおすすめします。
Q.遺言書を作成した後、内容を変更することはできますか?
A.はい、遺言者の意思により、いつでも新たな遺言書を作成して内容を変更することが可能です。複数の遺言書が存在する場合、最新の日付のものが有効となります。
Q.遺言書の保管方法にはどのようなものがありますか?
A.自筆証書遺言は、自宅の金庫や信頼できる人に預ける方法がありますが、紛失や改ざんのリスクがあります。
2020年からは、法務局で自筆証書遺言を保管する制度が始まっています。詳しくは弁護士までお問い合わせください。
Q.遺言書に記載できる内容にはどのようなものがありますか?
A.遺言書には、財産の分配方法だけでなく、推定相続人の廃除や認知、後見人の指定、祭祀主宰者の指定など、法律で定められた事項を記載することができます。
Q.遺言書を見つけた場合、すぐに開封してもよいですか?
A.自筆証書遺言や秘密証書遺言を発見した場合、家庭裁判所での検認手続きが必要です。
勝手に開封すると、5万円以下の過料が科されることがあります。ただし、公正証書遺言や法務局で保管された自筆証書遺言は、検認手続きが不要です。
Q.遺言執行者は必ず指定しなければなりませんか?
A.遺言執行者の指定は必須ではありませんが、指定することで、遺言の内容を確実に実現しやすくなります。
特に、相続手続きが複雑な場合や、相続人間の調整が必要な場合には、遺言執行者を指定することをおすすめします。