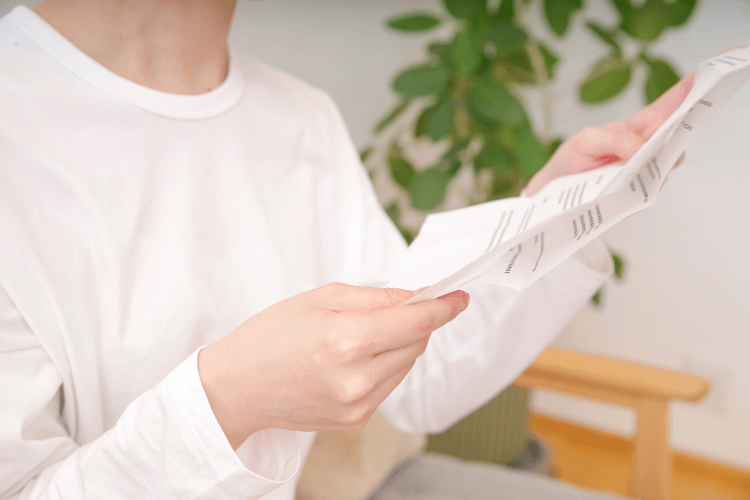
遺言書で「遺言執行者」が指定されていると、その人が全ての相続手続きを進めるため、ほかの相続人は手出しができないように感じてしまいますよね。「遺言執行者の権限は、どこまで及ぶのか」「できないことはないのか」と、不安になる方も多いでしょう。
実際、遺言執行者の権限は強力ではあるものの、決して万能ではありません。その役割は、あくまで「遺言の内容を忠実に実現する」ことに限定されています。
そこでこの記事では、以下の内容を解説していきます。
- 遺言執行者の基本的な情報
- 遺言執行者ができないこと7選
- 遺言執行者のみができること
- 遺言執行者でなくてもできること
- 遺言執行者選任の流れと必要書類
この記事を読むことで、遺言執行者ができることとできないことがわかり、遺言執行者に対する理解を深めることが可能です。ぜひ最後までご覧ください。
このページの目次
1.そもそも遺言執行者とは?
遺言執行者とは、亡くなった方の遺言書の内容を法的に実現するために、必要な一切の手続きをおこなう権限と義務を負った相続人の代理人です。相続手続きをスムーズに進め、相続人間のトラブルを防ぐための、非常に重要な役割を担います。
ここでは、遺言執行者の選任方法から担う業務、遺言執行者ができないことを知る重要性について解説します。
1-1.遺言執行者の選任方法
遺言執行者の選任方法には、主に2つのパターンがあります。
一つは、遺言者が遺言書の中で、「〇〇を遺言執行者として指定する」とあらかじめ指定しておく方法です。もう一つは、遺言書で指定がなかったり指定された人が辞退したりした場合に、相続人などの利害関係人が家庭裁判所に申し立てて、選任してもらう方法です。
遺言執行者として、弁護士や司法書士などの専門家が選ばれることも多いです。
1-2.遺言執行者の役割や担う業務
遺言執行者の主な役割は、遺言書に書かれた内容を、忠実に、そして速やかに実現することです。そのために、まず相続財産を調査して財産目録を作成し、相続人全員に通知します。
そして、遺言書の内容に従って、預貯金の解約・分配や不動産の名義変更(相続登記)といった、具体的な手続きをおこないます。まさに、相続手続きの司令塔となる存在です。
2.遺言執行者ができないこと7選
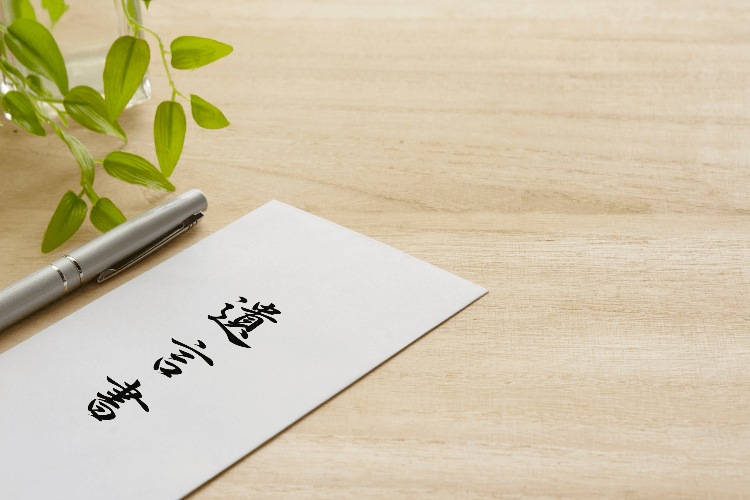
遺言執行者は、相続手続きにおいて非常に強力な権限を持ちます。ですが、その権限はあくまで「遺言の内容を実現するため」という範囲に限定されるのです。その範囲を越えた以下のような行為は、たとえ遺言執行者であってもおこなうことはできません。
- 遺言の内容変更および追加
- 遺言書に記載のない財産の処分や分配
- 相続人同士の遺産分割協議への介入や仲裁
- 相続税の申告や納付
- 相続人の生活や権利を制限する行為
- 不動産の売却や換価処分
- 遺留分の調整や放棄の強要
相続人としてご自身が持つ権利を守るためにも、遺言執行者が「できないこと」を正しく理解しておきましょう。一つずつ解説します。
2-1.遺言の内容変更および追加
遺言執行者は、遺言書の内容を勝手に変更したり新たな項目を追加したりすることはできません。遺言執行者の役割は、あくまで、故人が遺した遺言の内容を忠実に実現することだけです。「この分け方は不公平だから」といった理由から、自らの判断で遺言の内容に手心を加えることは一切認められていません。
2-2.遺言書に記載のない財産の処分や分配
遺言執行者は、遺言書に記載されていない財産を、勝手に処分したり、分配したりすることはできません。遺言執行者の権限は、あくまで遺言書に書かれた財産にしか及ばないためです。
もし、遺言書に記載のない預金口座などが見つかった場合は、相続人全員による「遺産分割協議」によって、分け方を決める必要があります。
2-3.相続人同士の遺産分割協議への介入や仲裁
相続人同士の話し合う遺産分割協議に対し、遺言執行者が法的な介入やその仲裁をすることはできません。遺言執行者は、あくまで遺言の内容を実現する立場であり、相続人間の個人的な争いの仲裁役ではないのです。
もし、遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停手続きなどを利用することになり、遺言執行者がその代理人となることは可能です。
2-4.相続税の申告や納付
遺言執行者には、相続税の申告や納付をおこなう法的な義務や権限はありません。相続税の申告・納付は、財産を相続した「各相続人」が、それぞれ連帯しておこなうべき義務です。
遺言執行者が、税理士の資格を持っていて、相続人から依頼された場合は話が別です。あくまで「遺言執行者」としての業務には、税務申告は含まれていません。
2-5.相続人の生活や権利を制限する行為
遺言執行者は、遺言を実現するために、相続人の固有の権利を不当に制限するような行為はできません。
たとえば、遺言の内容に不満を持つ相続人が遺言の無効を主張して訴訟を起こす権利や、遺留分を請求する権利を、遺言執行者が制限したり、妨げたりすることは一切許されていません。遺言執行者は、相続人の正当な権利行使を尊重する義務があります。
2-6.不動産の売却や換価処分
遺言執行者は、遺言書に「不動産を売却して、その代金を〇〇と△△で分けなさい」といった明確な指示(換価分割)がない限り、不動産を勝手に売却することはできません。
遺言書に「不動産は長男に相続させる」とだけ書かれている場合、遺言執行者がその不動産を勝手に売却し、現金で渡すといった行為は認められていません。
2-7.遺留分の調整や放棄の強要
遺言執行者には、相続人同士の「遺留分」に関する争いや交渉に介入する権限はありません。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に法律で最低限保障された相続財産の取得割合のことです。遺言によってこの割合が侵害された相続人は、他の相続人に対し遺留分侵害額請求をおこなうことで、侵害された分を取り戻すことができます。
遺言執行者が、遺留分に関する話し合いの場に立ち会うことはあっても、特定の相続人の味方をして交渉を主導したり、「遺留分請求権を放棄しなさい」と強要したりする行為は、遺言執行者の職務権限を明確に逸脱したものとなります。
関連記事:「遺留分は認めない」と遺言で残せる?遺留分請求を防ぐための対策
3.遺言執行者のみができることもある
遺言執行者にはできないことがある一方で、遺言の内容を実現するために、法律で定められた以下のような強力な権限が与えられています。
- 「特定遺贈」の履行
- 遺言による子の認知
- 推定相続人の廃除(およびその取り消し)
- 預貯金の払戻しや解約手続き
- 特定財産の引渡しや遺贈の実行
- 一般財団法人設立に充てる財産の拠出
これらは、遺言執行者が相続人の代理人としてスムーズに手続きを進めるために不可欠なものです。それぞれ解説します。
3-1.「特定遺贈」の履行
遺言執行者は、「長男にA不動産を遺贈する」といった、特定の財産を特定の相続人や相続人以外の人に渡す「特定遺贈」を実現する、法的な義務と権限を持ちます。
たとえば、不動産を遺贈する場合、遺言執行者はほかの相続人の協力を得ることなく、単独でその不動産の名義変更(所有権移転登記)の手続きをおこなうことができます。
遺言者の「この財産を、この人に」というピンポイントの意思を法的に実現するのが、遺言執行者の重要な役割です。
3-2.遺言による子の認知
もし、遺言書内に婚外子などを「認知する」という記載があった場合、その認知の届出を役所におこなうのは、遺言執行者だけができる非常に重要な職務です。
遺言執行者は、その職務を開始してから10日以内に、市区町村役場に対して認知届を提出しなければなりません。この手続きによって、認知された子は、法的な相続人としての地位を取得します。
ほかの相続人の感情とは関係なく、故人の意思を実現する重い責任です。
3-3.推定相続人の廃除(およびその取り消し)
遺言書に、「特定の相続人を廃除する」という意思が記されていた場合、遺言執行者は、家庭裁判所に廃除の申立てをおこないます。
廃除とは、故人に対して虐待や重大な侮辱をおこなった相続人の相続権を法的に剥奪する手続きです。遺言執行者は、故人の意思を代弁し、裁判所にその正当性を主張します。
逆に、遺言で廃除を取り消す意思が示されていれば、その取消しの手続きをおこなうのも遺言執行者の役割です。
3-4.預貯金の払戻しや解約手続き
遺言執行者は、遺言の対象となっている預貯金口座について、ほかの相続人の同意や協力を得ることなく、単独でその払戻しや解約手続きをおこなえる権限を持っています。非協力的な相続人がいても、遺言執行者の権限でスムーズに預貯金を現金化し、その後の分配や経費の支払いにあてることが可能です。
3-5.特定財産の引渡しや遺贈の実行
遺言執行者は、遺言書に「A銀行の預金は長男に」「B社の株式は次男に」と書かれている場合、その内容に従って、各財産の引渡しや名義変更手続きを実行します。たとえば、長男がA銀行の預金の払い戻しを受けるために必要な書類を準備したり、次男の証券口座にB社の株式を移管する手続きをおこなったりします。
遺言書という設計図にもとづいて、財産をあるべき場所へ正しく引き渡すのが、遺言執行者の中心的な業務です。
3-6.一般財団法人設立に充てる財産の拠出
遺言によって、「自分の財産で、一般財団法人を設立してほしい」といった、公益的な目的が示されている場合、遺言執行者がその設立手続きをおこないます。
遺言執行者は、故人の代理人として、定款の作成や財産の拠出といった、法人の設立に必要な一連の法的な手続きを実行する権限を持ちます。故人が社会に残そうとした最後の意思を実現するのも、遺言執行者の重要な役割の一つなのです。
4.遺言執行者でなくてもできること
遺言の内容によっては、相続人や財産を受け取る人(受遺者)が、自ら主体となって進められる手続きも数多く存在します。ここでは、遺言執行者の専権事項ではない、代表的な5つのケースについて解説します。
- 包括遺贈に関する手続(受遺者は相続人同様の権利義務を持つため、自ら手続可能)
- 寄与分の指定に沿った調整・手続(相続人間で実務対応が可能)
- 信託の設定に基づく実務手続(遺言記載に従い相続人らで進められる)
- 祭祀承継者の指定に関する承継手続(家督・祭祀財産の承継対応)
- 生命保険金の受取人変更に関わる実務(遺言内容に沿い手続可能)
詳しく解説します。
4-1.包括遺贈に関する手続(受遺者は相続人同様の権利義務を持つため、自ら手続可能)
「遺産の3分の1をAさんに遺贈する」といった、割合で財産を渡す「包括遺贈」の場合、財産を受け取る人(包括受遺者)が自ら手続きに関与できます。なぜなら包括受遺者は、法律上相続人と同様の権利と義務を持つとされているからです。そのため、ほかの相続人と共に遺産分割協議に参加して、具体的な財産の分け方を決めることになります。
遺言執行者は、遺産分割協議の結果にもとづいて、最終的な手続きをおこないます。
4-2.寄与分の指定に沿った調整・手続(相続人間で実務対応が可能)
遺言書で、「長男の〇〇が、私の介護を長年してくれたので、寄与分を認めてほしい」といった記載があった場合でも、その具体的な金額の調整は相続人同士の話し合いで進めることができます。
寄与分は、遺産分割協議にて、その貢献度を考慮して相続人全員の合意で決定されるのが原則です。遺言執行者は、遺産分割協議が円滑に進むようサポートしますが、寄与分の金額を一方的に決定する権限はありません。
4-3.信託の設定に基づく実務手続(遺言記載に従い相続人らで進められる)
遺言で、「私の財産を信託銀行に信託し、その運用益を妻の生活費に充てる」といった信託の設定が定められている場合、その実務手続きは、遺言執行者だけが行うわけではありません。この場合、相続人や、信託を引き受ける受託者(信託銀行など)が主体となって手続きを進めることになります。
遺言によって信託が設定されている場合、遺言執行者の主な役割は、信託の対象となる財産を、信託の受託者(信託銀行など)へ確実に引き渡すことです。その後の信託契約に基づく具体的な財産の管理や運用は、遺言執行者ではなく、信託を引き受けた受託者と、その利益を受ける相続人(受益者)との間で進められます。
4-4.祭祀承継者の指定に関する承継手続(家督・祭祀財産の承継対応)
遺言書の中で、お墓や仏壇などの「祭祀財産」を引き継ぐ人(祭祀承継者)が指定されている場合、その承継に関する実務手続きを遺言執行者がおこなう必要はありません。
祭祀財産は、預貯金や不動産といった一般の相続財産とは別の特別な財産として扱われます。そのため、祭祀承継者として指定された本人が、遺言執行者を介さず、お寺への連絡や墓地の名義変更といった手続きを自ら進めることができます。
4-5.生命保険金の受取人変更に関わる実務(遺言内容に沿い手続可能)
遺言書で生命保険金の受取人を変更する意思が示されていたとしても、その手続きを遺言執行者が単独でおこなうことはできません。なぜなら生命保険金は、本来保険契約で定められた受取人の固有財産であり、遺言書でその権利を直接変更する効力はないためです。
ただし例外的なケースとして、相続人全員が合意すれば、遺言の意思を尊重して受取人を変更できる場合があります。しかし、これは保険会社との交渉も必要となる、非常に複雑な手続きです。
5.遺言執行者の選任の流れと必要な書類
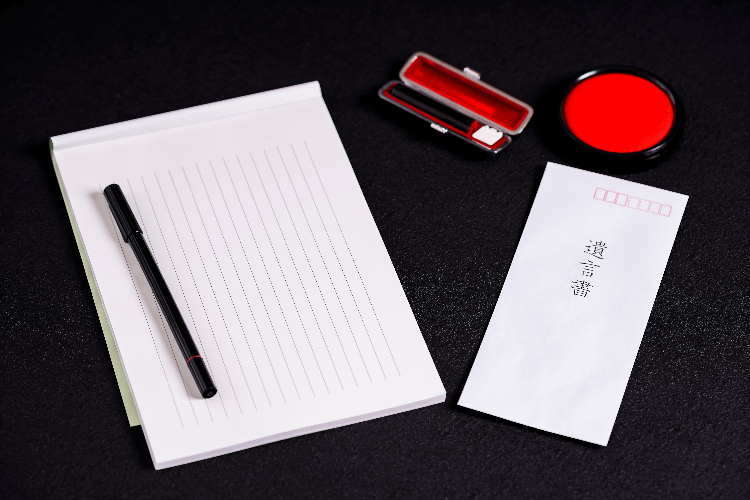
ここからは、遺言執行者の選任の流れと、その際に必要な書類な書類についてそれぞれ解説していきます。
5-1.遺言執行者選定の流れ
遺言執行者の選定は、被相続人が生前に指定しておく場合と、相続の発生後に相続人や受遺者などの利害関係人が対応する場合の2つがあります。
以下は、被相続人が生前に指定しておく場合の流れを表にまとめたものです。
| ステップ(対応者) | 内容 |
|---|---|
| ① 遺言執行者の指定(被相続人) | 遺言書(公正証書遺言など)に「〇〇を遺言執行者として指定する」と記載する。 |
| ② 遺言の発見・通知(相続人または執行者) | 遺言者の死亡後、遺言書の発見と、指定された執行者への就任依頼。 |
| ③ 就任の承諾(候補となる遺言執行者) | 指定された人物が、遺言執行者の就任を承諾する。 |
| ④ 相続人への通知(遺言執行者) | 就任したことを直ちに相続人全員に通知し、遺言書の写しを交付する。(民法改正により義務化) |
| ⑤ 任務の開始(遺言執行者) | 財産目録作成、預貯金・不動産の名義変更など、遺言内容の実現に必要な手続きを開始する。 |
次に、相続の発生後に相続人や受遺者などの利害関係人が対応する場合の流れです。
| ステップ(対応者) | 内容 |
|---|---|
| ① 申立て(利害関係人) | 相続人や受遺者などの利害関係人が、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対し「遺言執行者選任の申立て」をおこなう。この際、執行者の候補者を立てることも可能。 |
| ② 裁判所の審理(家庭裁判所) | 提出された書類(戸籍謄本、遺言書の写しなど)や、候補者への照会書(回答書)を通じて、適任者を選考する。 |
| ③ 遺言執行者の選任(家庭裁判所) | 審判によって遺言執行者を正式に選任する。通常、弁護士や司法書士などの専門家が選任されることが多い。 |
| ④ 審判の確定 | 選任の審判が確定すると、執行者と申立人に審判書謄本が届く。 |
| ⑤ 任務の開始(遺言執行者) | 選任された執行者が就任を承諾し、上記のステップ④以降の手続きを開始する。 |
5-2.遺言執行者の選任に必要な書類
家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てる際は、申立書のほかに、亡くなった方と相続人の関係を証明する複数の公的な書類が必要です。具体的には、以下のような書類です。
- 亡くなった方の死亡の記載がある戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺言執行者の候補者の住民票
- 遺言書の写しなど
これらの書類を、抜け漏れなく、正確に集めることが、スムーズな手続きの第一歩となります。
6.遺言執行者には弁護士を選ぶのが安心
遺言執行者は、遺言書のある相続を進めるうえで重要な役割を担います。そのため、将来のトラブルを防ぎながら円満な相続を実現するため、法律の専門家である弁護士を選ぶのが最も安心です。
弁護士は、常に中立的な立場を維持し、遺言の内容を正確かつ円滑に実現します。万が一、相続人同士の間で紛争やトラブルが発生した場合でも、弁護士であればそのまま代理人として交渉や訴訟への対応まで一貫しておこなえるのが、ほかの専門家にはない最大の強みです。
弁護士は、故人の最後の意思を最も確実に実現してくれるパートナーといえるでしょう。
7.まとめ
この記事では、遺言執行者が「できないこと」を中心に、その権限の範囲と相続人が持つ権利について詳しく解説しました。
遺言執行者は、相続人のうえに立つ存在ではなく、あくまで「遺言書に書かれた内容を実現する代理人」です。遺言にない財産を勝手に分配したり、相続人の遺留分請求を妨害したりすることはできません。
この記事で得た知識をもとに、遺言執行者の行動を正しく理解し、もし疑問を感じた場合は、一人で悩まず弁護士などの専門家へ相談してください。
弁護士法人池袋吉田総合法律事務所では、遺言書作成や相続に関する無料相談を受け付けています。遺言書に関する問題でお困りの方は、ぜひ当事務所までご相談ください。
このコラムの監修者
弁護士法人池袋吉田総合法律事務所は、相続全般、遺産分割、遺留分、相続放棄、生前対策、遺言作成、事業承継、
相続税など、法律のプロとして幅広い案件を取り扱っています。
初回相談は無料です。一人で悩まず、まずは当事務所へご相談ください。

第二東京弁護士会所属





