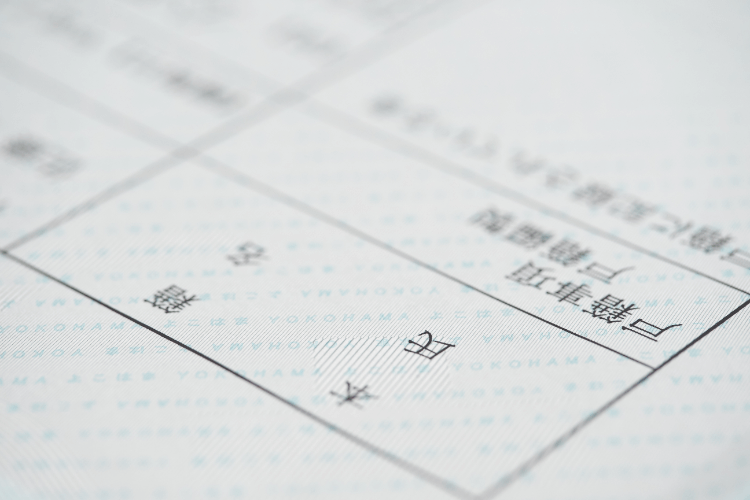
すでに縁を切った親が亡くなったとき、相続手続きを巡って親族から連絡が入ることもあります。この場合に対応を誤ってしまうと、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性が高まるため注意が必要です。
そこでこの記事では、以下の内容を中心に解説していきます。
- 縁を切った親の死亡連絡があったらまず何をすべき?
- 親と縁を切っていても相続人になるの?
- 縁を切った親の相続に関わりたくないときのベストな選択と手続きの流れ
相続に関する民法上のルールや、絶縁している兄弟や親族から連絡がきたときの対処法も解説しているので、ぜひ最後までご覧ください。
このページの目次
1.縁を切った親の死亡連絡があったらまず何をすべき?

縁を切った親の死亡連絡があったら、以下のポイントを意識する必要があります。
- 落ち着いて死亡の事実関係を確認する
- すぐに返事・対応をする必要はない
- 感情的にならず事務的な対応を心がける
実際に親が亡くなったときに備え、対応方法をしっかりと押さえておきましょう。
1-1.落ち着いて死亡の事実関係を確認する
まずは相手の話を落ち着いて聞き、死亡の事実関係を確認しなければなりません。とくに確認したいポイントが、親がいつ死亡したかです。
仮に相続手続きをするのであれば、正確な死亡日を把握しておく必要があります。最終的には戸籍謄本で確認するものの、連絡が来たタイミングでも聞いておいたほうが望ましいでしょう。
1-2.すぐに返事・対応をする必要はない
絶縁した親が亡くなったという連絡が来ても、すぐに返事・対応する必要はありません。その後の相続手続きにおいては、相続放棄を選ぶことも可能です。
家族と一切関わりたくないのであれば、相続放棄する旨を伝えるようにしましょう。
1-3.感情的にならず事務的な対応を心がける
遺骨の引き取りなどを断れば、相手から「親不孝者」などと罵られるかもしれません。しかし相手の言葉に対して感情的に怒ると、揉めごとが大きくなってしまいます。
事務的な対応を心がけつつ、自分の意思を伝えるようにしましょう。
2.親と縁を切っていても相続人になる?
たとえ親と縁を切っていても、相続が発生するのか気になる人もいるでしょう。ここでは民法の規定に照らしつつ、縁を切った親との相続関係について解説します。
2-1.法律上の親子関係は消えないため、相続権は存在する
親と縁を切っていたとしても、法律上の親子関係が消滅するわけではありません。変わらず相続権は存在するため、親が死亡したら相続が発生します。
2-1-1.絶縁状を公正証書で作成しても相続権がある
公正証書で絶縁状を作成したところで、相続権は消滅しません。私人が作成した絶縁状には、法的な効力が働かないためです。
たとえ書類に「相続放棄をします」と記載されていても、相続放棄の手続きが完了したことにはなりません。実際に相続放棄したいのであれば、親の死亡を知ったときから、3カ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
2-1-2.親に会ったことがなくても相続権がある
一度も親に会ったことがない場合でも、相続権は存在します。相続権の有無は、法的な血縁関係をもとに決められるためです。
したがって亡くなった親が自分を認知していないときも、同じく相続は発生します。
2-1-3.親の戸籍から分籍していても相続権がある
親の戸籍から分籍していても、相続権が消滅する事由にはなりません。
たとえば両親と仲違いをして、自分を筆頭者とする戸籍を作ったとしましょう。この場合も、親が亡くなったら当然のように相続権が発生します。
相続財産を引き継ぎたくないのであれば、別途相続放棄の手続きが必要です。
2-1-4.親の再婚相手の養子になっていても相続権がある
両親が離婚をして、母親と暮らすことになったとしましょう。仮に母親が再婚し、再婚相手と養子縁組を結んでも父親との相続関係は消滅しません。
仮に父親が亡くなったら、相続手続きを進める必要があります。
3.縁を切った親の相続に関わりたくないなら相続放棄がベスト

生前に縁を切った親の相続に、一切関わりたくないと考えるのであれば、家庭裁判所で「相続放棄」の手続きをおこなうのが最も確実で最適な方法です。
ここでは、相続放棄の概要について解説していきます。
3-1.相続放棄とは?
相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の、預貯金や不動産といったプラスの財産から借金などのマイナスの財産まで、その全てを一切引き継がないという意思を家庭裁判所に申し立てる法的な手続きです。
「相続人としての地位」そのものを放棄するため、受理されれば、あなたは相続に関して、完全に無関係の第三者となります。
相続放棄の申述には期限があり、相続が開始したことを知ったときから3カ月以内に手続きをする必要があります。
3-2.親との絶縁を理由に相続放棄することは可能
「親と縁を切っていたから」という感情的な理由であっても、相続放棄をすることは可能です。
家庭裁判所でおこなう相続放棄の手続きでは、その理由を詳しく問われたり、証明を求められたりすることはありません。申述書に「被相続人と生前、交流がなかったため」などと、簡潔に記載すれば十分です。
相続放棄は法律で認められた個人の権利ですので、理由を問わず、誰でもおこなうことができます。
3-3.相続放棄のメリット・デメリット
相続放棄をする際は、メリットとデメリットの両方を正しく理解したうえで、慎重に判断する必要があります。以下の表に、相続放棄の主なメリットとデメリットをまとめました。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 借金を引き継がなくて済む。故人の借金や連帯保証債務など、全ての負債から完全に解放される。 | プラスの財産も全て失う。後から価値のある財産が見つかっても、一切のプラスの財産を相続できなくなる。 |
| 相続トラブルから解放される。ほかの相続人との遺産分割協議に参加する必要がなくなり、面倒な争いを避けられる。 | 次の順位の相続人に相続権が移る。分が放棄したことで、故人の兄弟姉妹など、他の親族に借金の返済義務が移る可能性がある。 |
| 手続きが比較的簡単。弁護士などに依頼すれば、自分はほとんど何もしなくても、手続きを完了させられる。 | 一度おこなうと撤回できない。「やはり財産が欲しい」と思っても、受理された後には、原則として取り消しは認められない。 |
一度相続放棄が受理されると、原則として撤回はできません。ご自身にとって最適な方法なのかどうか、十分に検討するようにしてください。
4.相続放棄をするなら「期限」に注意
相続放棄を選択する際には、期限に注意しなければなりません。期限は、相続を知ったときから3カ月以内となっています。民法上の相続放棄のルールについて詳しくまとめます。
4-1.「親の死亡を知った日」とはいつ?
親の死亡を知った日とは、自分自身が親の亡くなった事実を認知したタイミングのことです。たとえば親が8月1日に亡くなったとします。
しかし縁を切っていれば、1カ月後の9月1日に初めてその事実を知ることもあるでしょう。この場合、相続放棄の起算点は9月1日となります。どのタイミングで親の死亡を認知するか、具体例について紹介します。
4-1-1.親族から連絡がきたときの対応
まず考えられるケースが、親の親族から連絡が来ることです。たとえば父親が亡くなった場合、その兄弟(自分から見た叔父)から伝えられます。
父親が再婚していれば、稀に再婚相手の子から連絡が入る可能性もあります。遺産分割協議や銀行口座の解約といった手続きは、相続人全員の対応が必要になるためです。
4-1-2.役所から連絡がきたときの対応
一人暮らしをしている親が孤独死した場合、不動産会社やオーナーは市町村役場に連絡することがあります。すると市町村役場の担当者は戸籍を頼りに、故人の親族へ連絡をします。
具体的な手続きについて教えてくれる場合もあるので、ひとまずは詳しく話を聞いてみるとよいでしょう。
4-1-3.家庭裁判所から連絡がきたときの対応
縁を切った父親の親族が、遺産分割調停を申し立てると家庭裁判所から連絡が来る可能性もあります。相続人全員に対し、遺産分割の意向を確認しなければならないためです。
ほかにも自筆証書遺言書が発見されたとき、検認期日を確認するために家庭裁判所から連絡が入ることも考えられます。
4-1-4.警察から連絡がきたときの対応
親の死亡原因が不明である場合、警察が捜査するケースもあります。捜査を進めるにあたって、遺品を手がかりに親族に連絡する可能性もあるでしょう。
警察から突然連絡が来たとしても、家族と関わりたくないのであればその旨を伝えても問題ありません。
4-2.期限を過ぎてしまったらどうなる?
3カ月の熟慮期間を過ぎてしまうと、法律上「単純承認」をしたものと自動的に扱われてしまいます。単純承認が認められた相続人は、被相続人の全ての遺産を相続しなければならないことから、相続放棄の期限が重要になってくるのです。
ただし、例外もあります。「親とは長年絶縁状態で、借金があるとは到底知る由もなかった」といった、期限内に手続きできなかったことに正当な理由がある場合は、3カ月を過ぎていても家庭裁判所が例外的に相続放棄を認めてくれる可能性があります。
諦める前に、まずは弁護士などの専門家に相談してみることが重要です
関連記事:相続の発生を知らなかった場合はどうなる?対処法やリスクを解説
4-3.3ヶ月で判断できない場合は?
3カ月の熟慮期間内に、プラスの財産と借金のどちらが多いかの調査が間に合わない場合や、気持ちの整理がつかず決めきれないでいる場合もあるでしょう。そんなときは、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てることができます。
この手続きをおこなうと、裁判所の判断にもとづき、熟慮期間をさらに数カ月間延長してもらうことが可能です。焦って不利益な決断をしないために、非常に有効な手段です。
5.縁を切った親の相続を相続放棄するときの流れ
縁を切った親の財産を相続放棄したいときは、以下のプロセスを踏む必要があります。
- 必要書類を集める
- 相続放棄申述書を作成する
- 家庭裁判所に申し立てる
- 裁判所からの照会書に回答する
- 「相続放棄受理通知書」を受け取る
各プロセスにおいて、どういった手続きが必要になるかを細かく説明します。
5-1.①必要書類を集める
家庭裁判所に相続放棄の申述をするには、次の必要書類を集めないといけません。
- 申述書
- 申述人の戸籍謄本
- 被相続人の戸籍附票・住民票除票
- 被相続人の死亡日が書かれている戸籍謄本
- 収入印紙(800円分)
- 郵便切手
状況に応じて必要書類が変わる可能性もあるので、揃える前に家庭裁判所や弁護士に確認してください。
5-2.②相続放棄申述書を作成する
必要書類を揃えたら、相続放棄申述書を作成しましょう。様式は、家庭裁判所のホームページから簡単にダウンロードできます。記入例も一緒に掲載されているので、作成する際の参考にしてください。
5-3.③家庭裁判所に申し立てる
相続放棄申述書の作成が完了したら、期限内に家庭裁判所に申し立てましょう。家庭裁判所の窓口に行けないのであれば、郵送での手続きも可能です。
ただし窓口で提出したほうが、必要書類の不備を教えてくれる場合があります。
5-4.④裁判所からの照会書に回答する
相続放棄の申述をしてから数日経つと、家庭裁判所から照会書が送付されます。照会書とは、本当に相続放棄する意思があるかを確認する書類です。
一度相続放棄をした場合、原則として申述は二度と撤回できません。申述人が後悔しないように、家庭裁判所は照会書で最終確認をします。
照会書が届いたら、同封されている回答書に必要事項を記入してから家庭裁判所に届けましょう。家庭裁判所によっては、照会書のやり取りを省略することもあります。
5-5.⑤「相続放棄受理通知書」を受け取る
相続放棄の手続きが完了すると、家庭裁判所から「相続放棄受理通知書」が届きます。当該書類は、自分が相続放棄した旨を証明する書類です。
再発行できないため、紛失しないよう大事に保管しましょう。万が一、紛失した場合は有料で「相続放棄受理証明書」の発行が必要となります。
6.縁を切った親の借金にあとから気づいたらどうなる?
縁を切った親が亡くなってからしばらく経ったあとに、多額の借金が判明するケースも稀にあります。この場合において、どういった行動を心がければよいかを押さえましょう。
6-1.相続放棄が認められる可能性もある
縁を切った親の借金にあとから気づいた場合、事情によっては相続放棄が認められる可能性もあります。たとえば相続財産がないと聞かされていたら、その話を信じても無理はありません。
親が死亡したのを知った日から3カ月以内を経過したとしても、特別な事情があると認められたときは相続放棄ができます。特別な事情としては、親と疎遠になっている、借金がないと信じることに相当な理由があるといったケースが該当します。
6-2.すぐにやるべきこと
借金の存在を知らせる督促状などが届いたら、すぐに相続問題に詳しい弁護士などの専門家に相談するようにしてください。
また借金の督促状は、相続放棄の起算点となる「知った日」を証明する重要な証拠として、日付の入った封筒ごと必ず保管しておきましょう。
弁護士をはじめとした法律の専門家は、あなたの状況で相続放棄が可能かを見極め、家庭裁判所への手続きを迅速に進めてくれます。
6-3.絶対にやってはいけないこと
一方で絶対にやってはいけないことは、借金の存在を知ったあとに、預貯金の解約や不動産の売却といった、故人の財産を処分する行為です。
たとえ少額であっても、故人の財産に手をつけてしまうと、あなたが相続を承認した(単純承認)と見なされ、あとから相続放棄が認められなくなる可能性が極めて高くなります。
債権者への連絡や、財産の処分は一切おこなわず、現状のまま専門家に相談することが、最も安全な対処法です。
関連記事:【相続後に借金が発覚】泣き寝入りしないための対処法 | 相続放棄はできる?
7.葬儀への参列や喪主を務める義務はある?

縁を切った親が亡くなった場合、葬儀への参列や喪主を務める義務はあるのでしょうか。ここでは、縁を切った親の葬儀や遺体の引き取りなどについて、解説していきます。
7-1.葬儀への参列や香典を出す法的な義務はない
戸籍上では親子関係が続いていても、葬儀への参列や、香典の支出、あるいは喪主を務めることなどを、法律が強制することはありません。これらは全て、故人との生前の関係性やご自身の弔意に基づき、自主的におこなう行為です。あくまで個人の気持ちや、宗教・慣習上の問題であり、法的な強制力は全くないのです。
たとえほかの親族から参列を強く求められたとしても、あなたがそれを拒否したことで、法的な不利益を被ることは一切ありません。ご自身の気持ちに従って、どうするかを判断して良いのです。
7-2.遺体の引き取りや埋葬の義務について
法律上、遺体の引き取りや埋葬の義務は、必ずしも相続人が負うわけではありません。「墓地、埋葬等に関する法律」では、死亡地の市町村長が、引き取り手のない遺体を火葬・埋葬する義務を負っています。
もしあなたが引き取りを拒否した場合、自治体によって火葬・埋葬がおこなわれます。
ただし、その費用は、後日、自治体から法定相続人であるあなたに請求される可能性があります。この費用負担は、相続放棄とは別の問題である点に注意が必要です。
8.絶縁している兄弟や親族から連絡が来た場合の対処法
絶縁している兄弟や親族から連絡が来たときは、正しい対処法を知っておくことが大切です。ここでは、どのように対応すればよいかを詳しく解説します。
8-1.感情的にならず「相続放棄を検討中」と事務的に伝える
絶縁している兄弟や親族から突然連絡が来ても、感情的に対応してはいけません。感情的な対応をしてしまうと、余計なトラブルに巻き込まれる恐れがあります。
相続放棄をしたいのであれば、「相続放棄を検討している」と事務的に伝えましょう。
8-2.遺産分割協議への参加は拒否できる?
相続放棄の申述が無事に受理されたら、相続権を失うので遺産分割協議に参加する必要がありません。したがって適切に手続きをすれば、遺産分割協議の参加も拒否できます。
しかし相続放棄の申述を済ませていないと、いつまでも相続権が残ります。ほかの相続人の遺産分割手続きが進まなくなるので、早めの申述を心がけてください。
遺産分割協議に「出席」するだけでは、相続放棄できなくなることはありません。ただし、そこで遺産の分け方に「合意」し、遺産分割協議書に署名・実印を押してしまうと、相続を承認した(単純承認)と見なされ、原則として相続放棄は不可能になります。
借金があるかもしれない場合は、話し合いの場で安易に同意せず、「相続放棄を検討中です」と明確に伝え、絶対に署名しないことが、あなたの身を守るために最も重要です。
8-3.弁護士を代理人に立てる
疎遠になった親の親族と関わりたくないのであれば、弁護士を代理人に立てることをおすすめします。弁護士に依頼すると、相続放棄の手続きも進めてくれるほか、相続に関するさまざまな知識を提供してくれる点が強みです。
関連記事:絶縁した兄弟姉妹との遺産相続 | 手続きの進め方や話し合う際のポイント
9.一人で悩まず弁護士に相談すべきケース

縁を切った親が亡くなったとき、何も考えずに相続手続きをすると思わぬトラブルに巻き込まれる恐れがあります。余計なトラブルを避けるためには、なるべく弁護士に相談したうえで手続きに取り掛かりましょう。
ここでは、とくに弁護士に相談すべきケースを紹介します。
9-1.親の借金の有無がわからない場合
まず弁護士に相談したほうがよいケースの一つが、親の借金の有無がわからない場合です。財産状況を細かく調べるには、相続財産を調査しなければなりません。
借金をしている人は、仲のよい親族にもその事実を隠している可能性があります。親族に確認するだけで終わらせるのではなく、正式な調査を専門家に依頼しましょう。
9-2.ほかの相続人と少しでも揉めている・揉めそうな場合
ほかの相続人と少しでも揉めている、あるいは揉めそうな場合も弁護士に相談してください。借金を抱えている親の相続を放棄すると、ほかの相続人に負担がかかる恐れもあります。
本来は早めに相続放棄する旨を伝えないといけませんが、連絡しにくいと感じる人もいるでしょう。そこで弁護士に対応してもらえば、ストレスなく相続放棄の手続きに移りやすくなります。
関連記事:
9-3.すべての手続きを任せて精神的負担をなくしたい場合
相続に関する手続きは、精神的負担がかかるものも少なくありません。仮に相続放棄を選択するにしても、期限内の申述が求められます。
弁護士は、本人の代理としてすべての手続きをすることが可能です。普段の生活が忙しく、手続きする余裕のない人は弁護士を頼るとよいでしょう。
10.まとめ
縁を切った親が亡くなったとしても、子であれば変わらず相続権が認められます。しかし親の財産に一切関与したくない場合は、相続放棄を選択するとよいでしょう。
絶縁している親族から連絡が来ても、感情的にはならず事務的な対応を心がけてください。手続きを進めるにあたって、他の親族とトラブルに発展しそうなときは、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人池袋吉田総合法律事務所では、相続に関する無料相談を受け付けています。相続に関する問題でお困りの方は、ぜひ当事務所までご相談ください。
このコラムの監修者
弁護士法人池袋吉田総合法律事務所は、相続全般、遺産分割、遺留分、相続放棄、生前対策、遺言作成、事業承継、
相続税など、法律のプロとして幅広い案件を取り扱っています。
初回相談は無料です。一人で悩まず、まずは当事務所へご相談ください。

第二東京弁護士会所属





