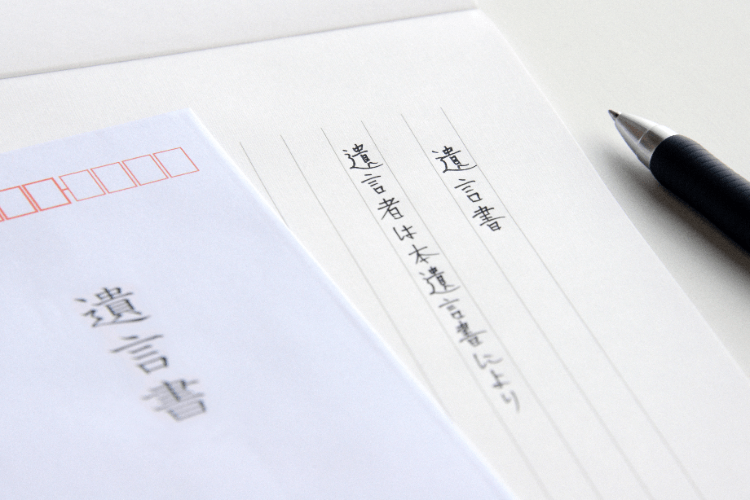
故人の自宅で荷物を整理していたところ、突然遺言書が出てきて困惑している人もいるでしょう。すぐに内容を確認したいかもしれませんが、勝手に遺言書を開封するのは法律違反となります。
この記事では、遺言書を正しく開封する方法について紹介します。種類別の手続き方法に加え、検認が不要になるケースも解説しているので、相続手続きを進める際の参考にしてください。
このページの目次
1.遺言書の勝手な開封はNG!まず確認すべきこと
故人の家で遺言書を発見しても、勝手に開封してはいけません。遺言書を発見したときは、どのような手続きをとるべきかを解説していきます。
1-1.遺言書の開封は原則として家庭裁判所の「検認」が必要
遺言書が自筆証書遺言書や秘密証書遺言書の場合、原則として家庭裁判所の「検認」が必要です。検認とは、家庭裁判所が相続人に遺言の存在および内容を知らせつつ、偽造・変造を防ぐ手続きを指します。検認にかかる日数は、一般的に数週間〜2カ月程度とされています。
手続きが面倒だからといって、遺言書をどこかに隠したり、勝手に破棄したりしてはいけません。これらの行為をすると、最悪の場合相続権が消滅する恐れもあります。
2.もし遺言書を勝手に開封してしまったらどうなる?

家庭裁判所での検認を経ずに遺言書を開封してしまった場合、民法1004条に抵触しペナルティが科される可能性があります。遺言書を開封してしまったからといって、パニックになる必要はありませんが、開封した場合に起こることと、起こらないことを、正確に理解しておきましょう。
2-1.遺言書の内容は無効にならない
まず、遺言書を勝手に開封しても、そこに記載されている内容が無効になるわけではありません。相続人が遺言書を勝手に開封してしまったという手続き上のミスだけで、遺言書そのものが無効になることはないのです。
法律は、故人が遺した最終的な意思を最大限尊重します。遺言が法的な要件を満たして作成されている限り、相続人が開封方法を間違えたからといって、遺言が効力を失うことはありません。
2-2.相続権は失わない
相続人が検認を経ずに遺言書を開封しても、あなたの相続人としての権利が、すぐに失われる(相続欠格となる)ことはありません。相続権を失うのは、遺言書を自分に不利益だからという理由で、破り捨てたり、隠したり、内容を書き換えたりした場合です。
これらの行為は、故人の意思を故意に妨害する行為と見なされるため、厳しいペナルティが課されます。開封してしまった場合は、隠さずに、正直にその後の手続きを進めることが何よりも大切です。
2-3.5万円以下の過料(罰則)が科される可能性がある
検認の済んでいない遺言書を、勝手に開封すると5万円以下の過料(罰則)が科される可能性もあります。過料とは行政罰の一種であり、科された場合は金銭を払わないといけません。
刑罰ではないので前科はつかないものの、経済的に負担がかかってしまいます。たとえ故意ではなくても、罰則が適用されうるので注意しましょう。
3.【遺言書の種類別】によって開封のルールは異なる
遺言書の種類によって、家庭裁判所での検認が必要かどうかが異なります。各遺言書の検認のルールについては、以下のとおりです。
- 公正証書遺言:検認不要
- 自筆証書遺言:場合により検認が必要
- 秘密証書遺言:検認が必要
それぞれのルールについて、詳しくみていきましょう。
3-1.公正証書遺言の場合:検認不要
公正証書遺言の場合、開封するにあたって検認が不要とされています。公正証書遺言とは、証人2人の立ち会いのもと、公証人が作成する遺言書です。
遺言書が作成されたあとは、公証役場にて保管されます。そのため相続人や第三者によって、偽造・変造される心配がありません。したがって公正証書遺言書は、検認が済んでいなくても開封できます。
3-2.自筆証書遺言:場合により検認が必要
自筆証書遺言は、原則として検認が必要です。故人が自分の家で保管していた場合は、第三者に改ざんされるリスクを避けるべく、家庭裁判所に提出しなければなりません。
一方で自筆証書遺言においても「自筆証書遺言書保管制度」を活用したときは、例外的に検認が不要となります。自筆証書遺言書保管制度とは、自筆証書遺言書を法務局に預ける制度のことです。
法務局が保管することで改ざんなどのリスクがほぼなくなるため、検認を経なくても開封できるようになります。遺言書の紛失リスクも少なくなる点から、故人の生前から自筆証書遺言書保管制度を勧めるとよいでしょう。
3-3.秘密証書遺言:検認が必要
秘密証書遺言書の場合は、検認が必要です。秘密証書遺言書は自筆証書遺言書と異なり、法務局に預けることはできません。
遺言者自身が自宅で保管するのが基本のため、改ざんされるリスクがあることから、家庭裁判所の検認を経る必要があります。
4.遺言書の検認が必要・不要なその他のケース
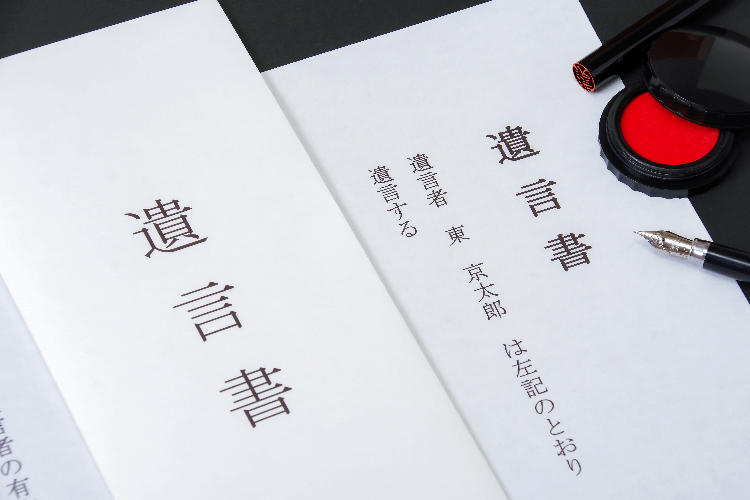
基本的に検認が必要となる遺言書ですが、誰かが誤って開封したり、そもそも封がされなかったりすることもあるでしょう。こういったケースにおいて、家庭裁判所での手続きが必要になるかどうかを解説します。
4-1.遺言書をすでに開封してしまったケース:検認が必要
自分が気をつけていたとしても、ほかの相続人が誤って開封してしまうことは考えられます。しかし開封したからといって、検認を省略できるわけではありません。
検認が完了しなければ、相続手続きがいつまでも進まなくなるため注意が必要です。家庭裁判所に提出する際には、再度封をすることはせず、開封したままの状態で持っていきましょう。
4-2.遺言書に封がされていないケース:検認が必要
故人が遺言書を作成するなかで、封をするのを忘れてしまうケースも考えられます。元々封がされていなかった場合でも、家庭裁判所で検認の手続きをしなければなりません。自分たちで封をすることはせず、そのままの状態で家庭裁判所に提出しましょう。
封jがされておらず遺言の内容が見えるからといって、検認を経ずに相続手続きを進めても効果は発揮しないので、注意してください。
4-3.遺言書が複数見つかったケース:検認が必要
遺言書が複数見つかったケースにおいては、それぞれで検認を済ませないといけません。民法上は遺言書の数に制限がないため、複数作成することも認められています。
しかしそれぞれの内容に矛盾点があった場合は注意が必要です。
たとえば1枚目には「Aに100万円を譲る」と記載されているものの、2枚目には「Aに150万円を譲る」と書かれていたとします。このケースでは日付をチェックし、新しいほうの内容を採用するのが民法上のルールです。
ほかにも2枚目の遺言書については、法務局や公証役場で預かってもらっているケースもあります。これらの機関で預かってもらっている遺言書は、検認を経る必要がありません。このように複数枚の遺言書が見つかったときは内容や日付、保管方法を細かくチェックしてください。
4-4.公正証書遺言の写しが見つかったケース:検認不要
自宅に公正証書遺言の写し(正本)が見つかった場合、基本的に家庭裁判所の検認は不要です。公正証書遺言書の原本は公証役場で保管されますが、写しを自宅で保管することも認められています。
自筆証書遺言書との違いは、公証人や証人の署名捺印があるかどうかで判別しましょう。これらの署名捺印があれば、公証役場にて原本が保管されています。公正証書遺言書の写しを発見したあとは、そのまま相続手続きに進んで問題ありません。
5.【検認が必要な遺言書】家庭裁判所での手続きの流れ
遺言書の検認を済ませるには、以下の手続きを経なければなりません。
- 申立人・申立先の裁判所の確認
- 必要書類の準備
- 家庭裁判所への検認の申立て
- 検認期日に相続人全員の前での開封
それぞれのステップにおいて、どのような手続きが求められるかを解説します。
5-1.①申立人・申立先の裁判所の確認
遺言書の検認は、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てる必要があります。そこで故人がどこに住所を置いていたかを、住民票から確認しなければなりません。
検認の申立人は一般的に遺言書を保管している相続人がなりますが、利害関係者以外もなることは可能です。ただし相続人との関係を、戸籍謄本などで証明する必要があります。
加えて申立人は、検認期日に出席する義務が生じます。基本的に検認期日は平日に割り当てられるため、対応できる人が申立人になるとよいでしょう。
5-2.②必要書類の準備
家庭裁判所で検認の申立てをする前に、次の必要書類を揃えておきましょう。
- 申立書
- 遺言者の戸籍謄本(出生〜死亡すべて)
- 相続人全員の戸籍謄本など
ほかにも相続人の状況によって、追加で書類の提出が求められることもあります。どの書類を集めればよいかで迷ったら、家庭裁判所や弁護士などの専門家に確認するとよいでしょう。
5-3.③家庭裁判所への検認の申立て
必要書類が揃ったら、家庭裁判所へ遺言書と一緒に提出し、検認の申立てをします。検認を申し立てる方法は、直接窓口に持参するか、郵送で送るかの二通りです。
さらに申立書には、800円分の収入印紙に加え、連絡用の郵便切手を貼付する必要があります。記録が残るように、書留や配達記録郵便で郵送するのがおすすめです。
5-4.④検認期日に相続人全員の前での開封
検認の申立てをして数週間〜1カ月程度が経過すると、家庭裁判所より検認期日の連絡が入ります。「検認期日通知書」に加え、「出欠回答書」が送付されます。相続人は、検認期日に出席するかどうかを回答しましょう。
上述したとおり申立人については、必ず検認期日に出席しなければなりません。当日は、申立書の作成に用いた印鑑を持参してください。出席できなかった相続人も、後日家庭裁判所で手続きすれば遺言書の内容を確認できます。
6.遺言書を開封したあとの注意点
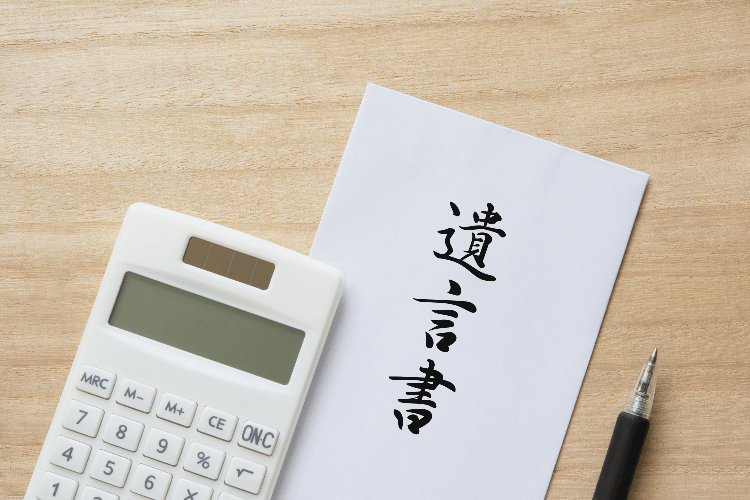
遺言書を正しい手続きのもと開封したら、以下の5点の注意してください。
- 遺言の内容を正確に把握したうえで遺言執行者を確認する
- 相続人全員に遺言の内容を正確に伝える
- 遺言の内容が遺留分を侵害していないか確認する
- 遺言書に記載のない財産の有無を確認する
- 遺言の内容に対する相続人全員の意思を確認する
一つずつ解説します。
6-1.遺言の内容を正確に把握したうえで遺言執行者を確認する
遺言書に書かれた財産の分け方や付言事項を正確に読み解き、とくに「遺言執行者」が指定されているかどうかを確認することが最も重要です。
もし遺言執行者が指定されていれば、預貯金の解約や不動産の名義変更といった、遺言の内容を実現するための手続きは、その執行者が単独でおこなう権限と義務を負います。相続人が勝手に手続きをすることはできません。
遺言執行者の有無によって、その後の手続きの主導者が誰になるかが決まります。
6-2.相続人全員に遺言の内容を正確に伝える
全ての法定相続人に対して、発見された遺言書の内容を、誠実かつ正確に伝える必要があります。内容を一部だけ伝えたり隠したりすると、あとから「遺言書を偽造したのではないか」といった、親族間の深刻な不信感やトラブルの原因となるためです。
遺言書に書かれている内容の透明性を確保し、全員が同じ情報を共有している状態を作ることが、円満な相続の大前提です。遺言書のコピーを渡すなど、形に残る方法で伝えるのが望ましいでしょう。
6-3.遺言の内容が遺留分を侵害していないか確認する
遺言の内容が、「全財産を一人に相続させる」というように、著しく偏っている場合は、ほかの相続人の「遺留分」を侵害していないかを確認する必要があります。
遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人に、法律上最低限保障されている遺産の取り分のことです。もし遺言によってこの権利が侵害されていれば、その相続人は、財産を多く受け取った人に対して、侵害額に相当する金銭の支払いを請求できます。
関連記事:「遺留分は認めない」と遺言で残せる?遺留分請求を防ぐための対策
6-4.遺言書に記載のない財産の有無を確認する
遺言書に記載されている財産と、実際に調査した相続財産の全体を照らし合わせ、記載漏れの財産がないかを確認します。
遺言書は、あくまでそこに記載された財産についてのみ効力を持ちます。もし遺言書作成後に取得した預金口座など、記載のない財産が見つかった場合、その財産は遺言の対象外です。
そのため、記載漏れの財産については、相続人全員であらためて「遺産分割協議」をおこない、その分け方を決める必要があります。
6-5.遺言の内容に対する相続人全員の意思を確認する
遺言書の内容について、相続人全員が納得しているか、その意思を確認することも重要です。たとえ法的に有効な遺言書があっても、相続人全員が合意すれば、遺言とは異なる内容で遺産を分割することも可能です。
また、相続人のなかに、遺言の有効性そのものを争う(たとえば「故人は認知症だった」など)意思を持つ人がいないかを確認します。全員の意思を確認することで、相続争いのリスクを最小限に抑えることができます。
7.【まとめ】遺言書を見つけたら、無闇に開封せず専門家に相談しましょう
遺言書を発見したときは無闇に開封せず、まずは専門家にご相談ください。相続トラブルに強い弁護士に相談すれば、検認の申立てについて詳しく教えてもらえます。必要書類を代わりに集めたり、代理で検認期日に出席できたりする点でもおすすめです。
また検認が完了したあと、相続人間で揉め事が発生する恐れもあります。とくに遺言での相続手続きは、遺留分を請求される可能性が高いでしょう。弁護士に相談しておくと、こうしたトラブルも一緒に解決できます。
弁護士法人池袋吉田総合法律事務所では、相続や遺言書作成などに関する無料相談を受け付けています。相続に関する問題でお困りの方は、ぜひ当事務所までご相談ください。
このコラムの監修者
弁護士法人池袋吉田総合法律事務所は、相続全般、遺産分割、遺留分、相続放棄、生前対策、遺言作成、事業承継、
相続税など、法律のプロとして幅広い案件を取り扱っています。
初回相談は無料です。一人で悩まず、まずは当事務所へご相談ください。

第二東京弁護士会所属





