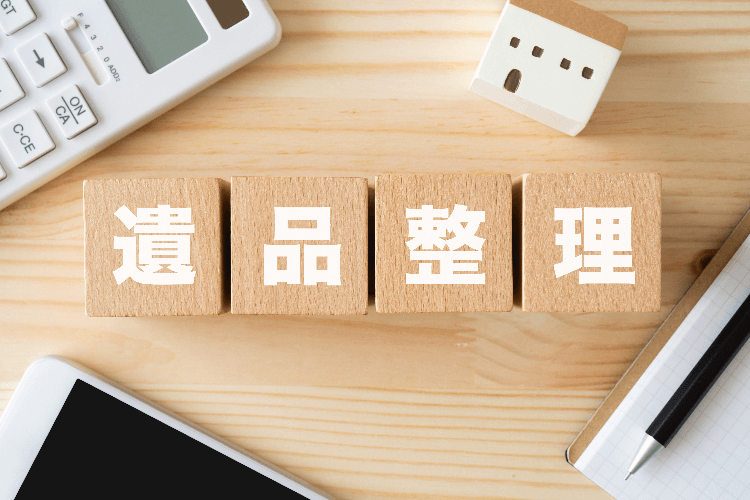
故人である被相続人の遺産を引き継ぎたくなく、相続放棄を検討している人もいるでしょう。しかし家庭の事情によっては、遺品整理をお願いされることがあります。
遺品整理に着手してしまうと、相続放棄にも支障をきたしかねません。そこでこの記事では、以下の内容を解説していきます。
- 相続放棄と遺品整理の定義
- 相続放棄後の遺品整理はしてもいいのか
- 相続放棄後の勝手な遺品整理はバレる可能性が高い
- 相続放棄する人が遺品整理をする際のポイント
- 相続放棄する人が遺品整理をする際の注意点ややってはいけないこと
記事の後半では、遺品整理に関するトラブルを防ぐ方法も解説しています。相続放棄を検討中で、遺品をどうするか悩まれている方は、ぜひ最後までご覧ください。
このページの目次
1.相続放棄と遺品整理の定義
相続放棄したあとに、遺品整理をしても問題ないかが気になる人もいるでしょう。ここでは相続放棄と遺品整理の定義を説明するとともに、それぞれの関係を解説します。
1-1.相続放棄=遺産の相続を拒むこと
相続放棄とは、遺産の相続を完全に拒む制度です。「相続の開始を知ってから3ヶ月以内」に家庭裁判所へ申立てすることで、その効力を発揮します。申立者自身は相続権を失い、ほかの相続人で遺産を分配するようになります。
一度家庭裁判所で申立てが受理されると、相続放棄を撤回することはできません。被相続人が資産を多く持っていたとしても、自分には引き継がれないので注意しましょう。
被相続人の財産調査もおこないつつ、相続放棄するべきかを慎重に判断してください。
1-2.遺品整理=被相続人の私物を処分・形見分けすること
遺品整理とは、被相続人の私物を次のように処分・形見分けすることです。
- 自分で保管する
- ほかの相続人に譲る
- 第三者に売却する
- 廃棄する
これらの作業は、相続人同士で家族の思い出を共有したり、気持ちを整理したりするといった役割を担います。加えて被相続人が暮らしていた部屋を片づけるのも大きな目的の一つです。
相続人の遺品を家族だけで整理するのが難しい場合は、遺品整理業者を頼るとよいでしょう。
2.相続放棄後の遺品整理はおすすめしない

相続放棄を選択するのであれば、特別な事情がない限り遺品整理はおすすめしません。一般的に遺品整理は、「単純承認した」とみなされ、相続放棄が無効になる可能性があるためです。
申立てが受理されたあとも、被相続人の財産を消費したり、売却したりすると相続放棄の効力を失います。相続放棄を選ぶ際には、ほかの相続人に遺品整理を任せ、なるべく自分は作業に関わらないほうが賢明です。
2-1.遺品の管理義務が残ることはある
相続放棄を選択しても、その時点で相続放棄した人が故人の財産を占有・管理していた場合には、次の相続人や相続財産清算人に財産を引き継ぐまでの間、その財産を自己の財産と同一の注意をもって管理する義務が残ることがあります(民法940条)。
たとえば、故人と同居していて家財などを管理していたケースが考えられます。この管理義務があるにもかかわらず、遺品を不適切に処分したり放置したりすると、損害賠償責任を問われる可能性も否定できません。
相続放棄後も、一定の状況下では財産の管理責任が残る点に注意が必要です。
関連記事:相続放棄したら相続財産の管理業務はどうなる?管理業務を回避する方法とは?
2-2.被相続人の自宅内における財産調査は可能
相続放棄をしたあとでも、どのような遺品(財産)があるかを確認するために、故人の自宅内を調査すること自体は原則として問題ありません。これは、相続放棄をするかどうか最終的に判断するため、あるいは他に相続人がいるか、相続財産清算人の選任が必要かなどを検討するために、財産の状況を把握する必要があるためです。
ただし、調査はあくまで現状を確認する範囲にとどめ、遺品を持ち出したり、処分したり、形見分けをおこなったりする行為は絶対に避けるようにしてください。
3.相続放棄後の勝手な遺品整理はバレる可能性が高い
相続放棄の申請後の勝手な故人の遺品整理は、バレる可能性があり、法的なリスクを伴います。
相続放棄をすると、法的には初めから相続人ではなかったことになり、遺産(プラス・マイナス共に)を引き継ぐ権利も義務も失います。しかし、放棄後に故人の遺品(財産価値の有無に関わらず)を処分したり自分のものにしたりすると、「相続財産を処分した」とみなされ、相続放棄を取り消して全ての遺産(借金も含む)を相続する意思を示した「単純承認」と判断される可能性があるのです。
3-1.勝手な遺品整理は誰にバレる?
勝手な遺品整理が発覚する可能性のある相手は、以下の通りです。
| 他の相続人 | 遺品の状況を知っており、変化に気づく可能性があります。 |
| 債権者 | 故人に借金があった場合、調査の過程で財産処分を知り、相続放棄の無効と返済を主張してくる可能性があります。 |
| 相続財産清算人 | 相続人全員が放棄した場合などに選任され、財産調査で不正な処分を発見する可能性があります。 |
安易に「バレないだろう」と考えるのは危険です。とくに借金がある場合は、債権者が調査する可能性が高まります。
どうしても故人の遺品整理が必要な場合は、相続放棄をしていない他の相続人や、必要に応じて選任される相続財産清算人に相談・依頼しましょう。判断に迷う場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
4.相続放棄する人が遺品整理をする際のポイント4選

相続放棄を検討している人が遺品整理をする際のポイントとして、以下の4つを解説していきます。
- 日持ちしない遺品は処分できる
- 金銭的価値がない遺産は形見分けする
- 限定承認も検討する
- 相続人全員が相続放棄したら相続財産清算人に任せる
それぞれ解説していきます。
4-1.日持ちしない遺品は処分できる
相続放棄を考えている場合でも、そのまま放置すると腐敗してしまうような日持ちしない遺品(生鮮食品や植物な)については、衛生上の観点から処分することが一般的に認められています。財産を処分するというよりは、財産の価値を維持するための保存行為、あるいは腐敗による損害拡大を防ぐための行為と解釈されるためです。
ただし、処分する際には、あとでほかの相続人や関係者から疑念を持たれないよう、何を処分したか写真やメモで記録を残しておくのが望ましいでしょう。
4-2.写真や衣類・日用品など金銭的価値がない遺産は形見分けする
故人の写真や手紙、衣類、日用品など、客観的に見て金銭的な価値がほとんどないと考えられる遺品については、相続放棄をする場合でも形見分けとして受け取ることが許容される場合があります。財産的な価値がない遺産は、相続財産の処分には当たらないと解釈される余地があるからです。
ただし、何が「金銭的価値がない」と判断されるかは非常に曖昧であり、トラブルになるリスクもゼロではありません。少しでも価値がありそうなものや、判断に迷うものは、安易に持ち帰らないほうが無難です。
4-2-1.方見分けする際の注意点
金銭的価値がない遺品を形見分けする際には、以下のことに注意してください。
- 本当に価値がないものか慎重に判断し、少しでも換金できそうなものは避ける
- ほかに相続人がいる場合は、その人の同意を得てからおこなう
- 誰が何を持ち帰ったのか簡単な記録を残しておく
形見分けであっても、その行為が「財産の処分」とみなされるリスクは完全には否定できないため、極めて慎重におこなう必要があります。
4-3.限定承認も検討する
故人の借金がどのくらいあるか不明な場合や、プラスの財産の範囲内で借金を返済したい場合に、「限定承認」という相続方法を検討するのも一つの手です。
限定承認は、相続したプラスの財産の限度でマイナスの財産(借金など)も引き継ぐという手続きで、家庭裁判所への申立てが必要です。この方法であれば、相続財産清算人を選任せずに、相続人自身が財産の清算手続きに関与できる場合があります。
遺品整理も清算手続きの一環としておこなえる可能性がありますが、手続きが非常に複雑なため、弁護士などの専門家への相談が不可欠です。
4-4.相続人全員が相続放棄したら相続財産清算人に任せる
相続人全員が相続放棄をした場合、最終的には家庭裁判所によって選任された「相続財産清算人」が遺品の管理・処分を含む清算手続きをおこないます。相続財産清算人は、故人の債権者など利害関係者からの申立てによって選任され、法的な権限のもとで財産を換価し債権者へ支払うことが主な役割です。
したがって、相続人全員が放棄した後は、遺品整理について心配する必要はなく、選任された相続財産清算人に全てを任せるのが正しい対応となります。
5.相続放棄する人が遺品整理をする際の注意点ややってはいけないこと
相続放棄する人が遺品整理する際には、以下6つの注意点ややっていけないことも確認しておきましょう。
- 一度申請した相続放棄は取り消せない
- 被相続人あての督促状を見つけても対応しない
- 入院代の請求書の扱いにも注意する
- 遺品の処分や隠匿はしない
- 被相続人の通帳を使って預貯金を引き出さない
- 被相続人の携帯電話は勝手に解約しない
一つずつ解説します。
5-1.一度申請した相続放棄は取り消せない
原則として、家庭裁判所に申述し一度受理された相続放棄は、あとから「やっぱり相続します」と取り消すことはできません。相続放棄は、相続人の意思にもとづく重要な法律行為であり、一度受理されると法的な効果が確定します。
ただし、例外的に取り消しが認められる可能性が全くないわけではありません。たとえば、ほかの相続人から騙されたり脅されたりして、本意ではないのに相続放棄をしてしまったような場合(詐欺や強迫)には、取り消しを主張できる可能性があります。しかし、これは非常に限定的なケースであり、裁判所での手続きが必要となります。
相続放棄をおこなう際は、ご自身の状況や相続放棄のメリット・デメリットなどをよく照らし合わせ、納得のいく決断をできるようにしてください。
5-2.被相続人あての督促状を見つけても対応しない
家族の知らないところで、被相続人が債権者からお金を借りていることもあるかもしれません。遺品整理をしている最中に、引き出しの中から督促状が出てきたら慌ててしまうはずです。
ただし相続放棄を選択するのであれば、債権者からの督促に対応してはいけません。被相続人の預貯金から返済したら、単純承認したと判断されてしまいます。相続放棄したことを証明すれば、自分に返済義務は生じないことを押さえてください。
関連記事:借金は相続放棄できる?借金と相続放棄の関係や注意点など徹底解説
5-3.入院代の請求書の扱いにも注意する
遺品整理をしていたところ、病院から被相続人の入院にかかる請求書が送られてくることもあるでしょう。被相続人の口座から入院代を支払う行為も、単純承認に該当するので避けなければなりません。
どうしても入院代を支払わないといけない場合は、相続人自身のお金で対応する必要があります。そうすれば被相続人の財産には触れていないため、単純承認とはみなされません。とはいえ放棄した者に支払う義務はないことから、ほかの相続人に対応してもらうのが得策です。
5-4.遺品の処分や隠匿はしない
遺品整理するときは、原則として遺品の処分や隠匿をしてはいけません。処分は、被相続人の所有物を第三者に売却する行為が該当します。隠匿とは、被相続人の所有物を隠す行為です。
例外的に被相続人との思い出の写真をもらうケースは、遺品整理も認められやすくなります。思い出の品であり、財産的価値のないことが相続放棄後に処分できる条件の一つです。
とはいえ財産的価値の有無については、社会通念に照らして考えないといけません。正確な基準もないため、自分一人で判断せず弁護士からアドバイスをもらいましょう。
5-5.被相続人の通帳を使って預貯金を引き出さない
相続放棄を選択するのであれば、基本的に被相続人の通帳には触れてはいけません。通帳を用いて、口座からお金を引き出した場合は単純承認とみなされます。
葬儀費用の支払いについては、例外的に認められることもあります。葬儀は日本において重要な儀式であり、被相続人を供養するうえで欠かせないためです。しかしあまりにも高額で豪華すぎる葬儀は、単純承認と判断される恐れもあるので注意してください。
5-6.被相続人の携帯電話は勝手に解約しない
スマホが普及している現代において、携帯電話を持っている人も増えています。しかし被相続人の代わりに携帯電話を解約する行為も、単純承認となりうるので注意が必要です。
相続手続きに時間がかかっていると、携帯代の催促が来る場合もあるでしょう。このケースでも支払いに応じてしまうと、原則として相続放棄が認められなくなります。ほかの相続人に対応を任せるか、相続放棄後に携帯会社へ連絡を入れることをおすすめします。
関連記事:故人の携帯を解約してしまったら相続放棄はできなくなる?
関連記事:相続放棄後にしてはいけないこととは?認められる行為も解説
6.相続放棄後に遺品整理しないといけないケースもある

相続放棄を選んだとしても、遺品整理しないといけないケースもあります。しかし遺品整理の方法によっては、単純承認と判断される場合もあるので注意が必要です。相続放棄が無効とならないように、どう対応すればよいかを解説します。
6-1.被相続人の連帯保証人になっている
被相続人の連帯保証人となっている場合は、被相続人の遺品を整理しなければなりません。連帯保証人は債権者の弁済の要求に対して、主たる債務者が返済できるかどうかにかかわらず肩代わりする人です。
たとえば被相続人が賃貸物件で一人暮らししていたとしましょう。本来、賃貸物件の解約は単純承認とみなされるため、相続放棄する人はNGとされている行為です。
しかし連帯保証人については、解約手続きに必要な修繕費用を負担する義務が生じます。ほかにも室内で被相続人が亡くなっていた場合は、特殊清掃も手配しなければなりません。
一方で賃貸物件の手続き以外における遺品整理(所有物を売るなど)は、単純承認とみなされる可能性があります。連帯保証人としてどこまで対応すべきかを、弁護士にしっかりと相談してください。
6-2.被相続人が孤独死した
被相続人が賃貸物件に住んでおり、孤独死したケースでも遺品整理が必要になるケースはあります。とくに遺体の発見が遅れてしまったのであれば、特殊清掃も手配しないといけません。悪臭や害虫の発生により、近隣にも迷惑がかかる恐れがあるためです。
相続人がほかにいる場合は、その人に任せたほうが賢明です。一方で相続人が誰もいないのであれば、自分のお金で特殊清掃の対応をするのをおすすめします。
あわせて大家から遺品を持ち帰ってほしいと頼まれることもあるでしょう。しかし大家からのお願いに対して、簡単に応じるのはおすすめできません。自分が遺品を回収することで、単純承認と判断される恐れもあるので、弁護士のアドバイスをもとに動いてください。
6-3.ほかに相続人がいない
自分が相続放棄を選択すると、ほかに相続人がいなくなることもあるでしょう。仮に自身が財産を占有しているときは、相続財産清算人に引き渡すまで、「自己の財産におけるのと同一の注意をもって」保存しなければなりません。
ただしあくまで対象とされているのは、現に占有していると認められるときです。遠隔地に住んでいるなど、財産に全く関わりのない人は保存義務がありません。
仮に保存義務があったとしても、財産を勝手に処分すると相続放棄が無効となります。自身の過失によって財産を毀損したら、損害賠償責任も生じうるため注意しましょう。
7.遺品整理に関するトラブルを防ぐ方法
遺品整理は法律上の根拠がないものも多く、トラブルに発展するケースは少なくありません。作業へ移る前に、トラブルを防ぐ方法として以下の3点を押さえておきましょう。
- 弁護士からアドバイスをもらう
- 遺品整理について家族と話し合う
- 遺品整理業者とのやり取りにも注意する
一つずつ解説します。
7-1.弁護士からアドバイスをもらう
遺品整理をする際には、必ず弁護士からアドバイスをもらってください。相続放棄後にどのような行為が認められるかは、家庭や財産の内容によって細かく異なります。
自分のなかでは「問題ない」と思っていても、単純承認に該当して相続放棄ができなくなる恐れもあるので注意しましょう。
7-2.遺品整理について家族と話し合う
遺品整理のトラブルを防ぐには、家族と話し合うことも大切です。相続放棄の申述自体は、相続人の同意を得ずに単独でできます。
しかし遺産分割協議などで支障が出てしまうため、家族に相続放棄する旨を話しておかないといけません。相続放棄について説明するとともに、遺品整理のことも確認しておくとよいでしょう。
7-3.遺品整理業者とのやり取りにも注意する
自分で遺品整理をしてしまうと、知らないうちに単純承認の要件にふれる恐れがあります。こうしたリスクを防ぐには、プロの遺品整理業者に作業を依頼したほうが賢明です。
弁護士や司法書士のみならず、遺品整理士も遺品の扱いについて豊富な知識を有しています。相続放棄する旨を相談すれば、どのように対応したらよいかを教えてくれるでしょう。
さらに相続放棄する人は、原則として遺品整理業者への費用を負担する必要はありません。家族にも説明し、なるべく相続人が費用を支払うようにしてください。
8.まとめ
結論として、相続放棄をしたあとの遺品整理は基本的にNGとされる行為です。申立てが認められない可能性も高く、今後の生活に著しい支障をきたすリスクもあります。
しかし家庭の事情によっては、遺品整理に協力してほしいとお願いされることもあるでしょう。どうしても作業するのであれば、あらかじめ弁護士に相談するのをおすすめします。加えて、相続放棄を問題なく済ませることを優先的に考えてください。
弁護士法人池袋吉田総合法律事務所では、遺言書作成や相続に関する無料相談を受け付けています。遺言書に関する問題でお困りの方は、ぜひ当事務所までご相談ください。
このコラムの監修者
弁護士法人池袋吉田総合法律事務所は、相続全般、遺産分割、遺留分、相続放棄、生前対策、遺言作成、事業承継、
相続税など、法律のプロとして幅広い案件を取り扱っています。
初回相談は無料です。一人で悩まず、まずは当事務所へご相談ください。

第二東京弁護士会所属





