
さまざまな事情により、一人のみに遺産を渡そうと考えている人もいるでしょう。遺言書で一人に相続させることは可能ですが、今後の手続きで少なからずトラブルを招く恐れもあります。
この記事では、遺言書により一人のみに遺産を渡すメリットと注意点について紹介します。遺産の分配方法に悩んでいる人は、ぜひ記事を参考にしてください。
このページの目次
1.遺言書で一人にだけ相続させることは可能
結論から言うと、遺言書を作成することで、特定の相続人一人に全ての遺産を相続させる、あるいは相続人以外の人(第三者)に遺贈することは原則として可能です。
遺言書は、原則として被相続人の意思が尊重されます。そのため「特定の人にのみに遺産をすべて相続させる」といった遺言を残せます。
また遺産を渡す相手は、法定相続人である必要もありません。お世話になった第三者に対し、遺産を譲るといった遺言書も作成可能です(遺贈)。
一方で兄弟姉妹以外の法定相続人には、遺留分(最低限相続できる額)を請求できます。遺言書の付言事項に「遺留分も渡さない」と残しても、法的には効力を発揮しません。
2.遺言書で一人だけに相続する主な理由や動機

遺言書で一人だけに相続させる主な理由は動機として、以下のようなものが考えられます。
- 財産を配偶者にだけ相続したい
- 自分の財産を渡したくない相続人がいる
- 相続人が相続放棄を選択した
- 事業の跡継ぎのみに相続したい
- 相続人以外の第三者に財産を渡したい
- 共有や分散が難しい財産がある
それぞれ見ていきましょう。
2-1.財産を配偶者にだけ相続したい
まず理由の一つとして挙げられるのが、配偶者にだけ相続分を渡したいためです。たとえば夫婦の間に子がいない場合、民法上は配偶者と直系尊属が相続人となります。直系尊属も全員亡くなっていれば、次に相続権を有するのは兄弟姉妹です。
また、兄弟姉妹と関係性が薄ければ、配偶者に全額譲渡したいと思う人もなかにはいるでしょう。このケースにおいては、配偶者に全額相続するといった内容の遺言書が作られる傾向にあります。
2-2.自分の財産を渡したくない相続人がいる
財産を渡したくない相続人がいることも、一人に相続させる要因の一つです。仮に配偶者がおらず、長男と次男の2人が相続人と仮定します。
長男と自分との関係が悪く、遺産を渡したくないといった事情があれば、次男に全財産を相続させたいと思うでしょう。このケースでは「次男のみに遺産を渡す」といった遺言を残すことが考えられます。
関連記事:絶縁したい家族との相続を進めるデメリットや相続争いを避ける方法
2-3.相続人が相続放棄を選択した
相続人が相続放棄をしたことで、一人のみに財産を譲るといった理由も考えられます。長男と次男が法定相続人と仮定した場合、長男が相続放棄したら相続人は次男のみです。相続人の死亡とは異なり、相続放棄は代襲相続の要因にもなりません。
相続放棄は、家庭裁判所が受理した時点で絶対的な効果が働きます。したがって次男に財産をすべて譲りたいと考えていても、長男はすでに相続権がないので遺言書に書く必要もありません。
関連記事:相続放棄後にしてはいけないこととは?認められる行為も解説
2-4.事業の跡継ぎのみに相続したい
事業者のなかには、跡継ぎとなる相続人にのみ財産を相続したいと考えている人もいるはずです。何代にもわたって事業を継承しており、代々長男に跡を継がせるのが風習となっていることもあるでしょう。
1947年(昭和22年)までの民法では、「家督相続制度」が存在しました。戸主が亡くなった際に、長男が財産や地位をすべて取得する制度です。しかし現民法では、次男などにも遺留分を請求できる権利があるので、注意してください。
2-5.相続人以外の第三者に財産を渡したい
家族ではなく、お世話になった第三者へ財産を渡したいと思う人もいるでしょう。法的には、相続人以外の者に財産を譲るといった遺言も認められています。
とはいえ無関係の第三者が財産を取得することに、納得できない家族がいても無理はありません。遺留分の争いに加え、さまざまな相続トラブルが発生するリスクもあることを念頭に置いてください。
2-6.共有や分散が難しい財産がある
相続予定の財産の中に、物理的に分割したり、複数の相続人で共有したりするのが難しい財産が含まれている場合、「特定の一人に相続させる」と遺言書で指定する理由になります。
たとえば、個人で経営していた事業(店舗や工場など)や、代々受け継いできた農地などがこれにあたります。これらの財産を複数の相続人で分割してしまうと、事業の継続が困難になったり、土地が細分化されて価値が下がったりする恐れがあるため、遺言書で相続人を指定するケースが多いです。
その場合、事業の後継者や、農業を続ける特定の相続人にまとめて相続させ、そのほかの相続人には別の財産(預貯金など)を渡すといった形で、遺産の円滑な承継を図ることがあります。
3.遺言書で一人に相続させるメリット
遺言書で一人に相続させるメリットは、以下の3点です。
- 被相続人の意思が相続手続きに反映される
- 相続手続きがシンプルになる
- 相続税の負担が軽減されることもある
それぞれ解説していきます。
3-1.被相続人の意思が相続手続きに反映される
まずメリットの一つとして挙げられるのが、被相続人の意思が反映されることです。遺言がなければ、原則として相続人同士の遺産分割協議で分配方法が決まります。遺産分割協議の場合、関係の悪かった相続人にも財産が渡る可能性も高まるでしょう。
仮に相続人が虐待や侮辱行為を日常的におこなっていたのであれば、廃除の手続きも可能です。家庭裁判所が廃除を認めたら、遺言で一人に相続することも認められやすくなります。
3-2.相続手続きがシンプルになる
遺言で一人にのみ財産を渡すと、相続手続きがシンプルになりやすいといったメリットもあります。たとえば土地や建物といった不動産を所有していたとしましょう。
不動産を相続するときも、原則は相続分に従って分配されます。しかし相続分を所有したところで、金銭と違って物理的に分けられるものではありません。持分をめぐって、相続人同士でもめることは十分考えられます。
そこで相続人の一人に不動産を管理させれば、共有になることはありません。相続手続きがシンプルになり、相続人の生活においてもプラスに働く可能性もあります。
3-3.相続税の負担が軽減されることもある
一人のみが財産を引き継ぐように遺言を残すと、相続人たちの相続税の負担が軽減される場合もあります。その一つが、小規模宅地の特例です。こちらは事業用・居住用宅地を相続した人が、特定の要件を満たしたときに税負担が軽減される制度を指します。
330㎡以内の居住用宅地の場合は、80%分の減額が可能です。この制度は、配偶者が相続するときの要件はほとんどありません。配偶者のみに相続させれば、配偶者控除の適用もあり税負担の軽減につながりやすくなります。
ただし一次相続は節税できても、配偶者が亡くなった際の二次相続で税負担が大きくなることもあります。相続税対策は複雑であるため、税理士に相談したうえで進めてください。
4.一人に相続させるための遺言書の作り方
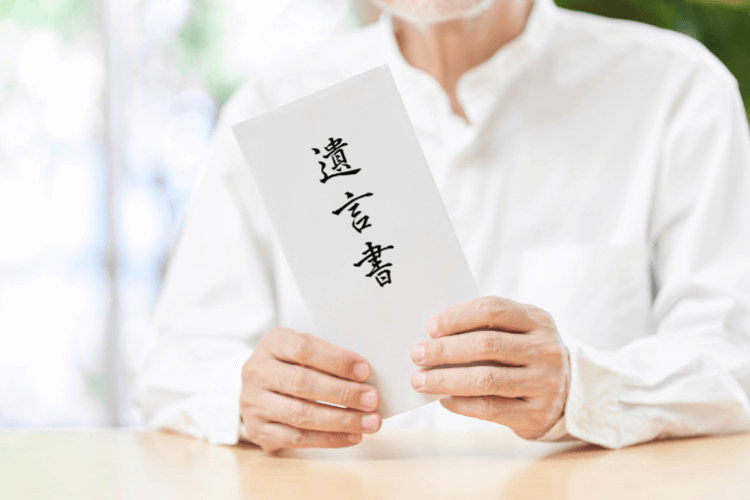
次に、遺産を一人に相続させるための遺言書の作り方を紹介します。遺言書の仕組みについても取り上げるので、併せて参考にしてください。
4-1.どの形式を選ぶかを決める
遺言書には、大きく分けて3つの形式が存在します。
| 形式 | 作成方法 |
|---|---|
| 自筆証書遺言 | 署名や日付、全文を自署で作成する |
| 公正証書遺言 | 証人2人の立ち会いで、公証人が作成する |
| 秘密証書遺言 | 署名は自署で、本文はパソコン作成も可能封筒に遺言書を入れて、封印する |
形式的な不備をなくしたいのであれば、公正証書遺言がおすすめです。原本も公証役場が管理してくれるため、第三者に破棄・改ざんされるリスクも防げます。
自筆証書遺言は原則として自宅保管ですが、2020年より法務局に預けられるようになりました。ただし秘密証書遺言は、法務局では預けられないので注意してください。
4-2.自身の財産の状況を整理・把握する
遺言書を書く前に、財産の状況をもう一度整理する必要があります。正しく把握できていないと、後の相続トラブルを招く恐れもあるので注意が必要です。不安であれば、弁護士のサポートを受けたうえで状況を調査してください。
4-3.各形式に合わせて遺言書を作成する
ここまでの準備が終わったら、各形式のルールに従って遺言書を作成します。自筆証書遺言の場合、全文を自署で記載しなければなりません。財産目録以外は、パソコンでの作成は認められないので注意してください。
公正証書遺言は公証人が作成しますが、遺言者による口授(公証人に遺言の内容を口頭で伝える行為)が必要です。どのように財産を分配したいか、自分の中で整理しておきましょう。
4-4.付言事項も残しておく
遺産を一人に相続させるときは、付言事項にその旨を残すのがおすすめです。付言事項は自分の考えを自由に述べられる部分であり、相続人に思いが伝わりやすくなります。ただし付言事項を残したとしても、遺留分の請求権は失われないので注意してください。
5.遺言書で一人に相続させるときの注意点
遺言書で一人に財産を渡すのは、相続手続きにおいて以下のようなトラブルを招くことがあります。
- ほかの相続人から遺留分を請求される恐れがある
- 遺言の無効を主張される恐れがある
- 弁護士の立ち会いのもとで作成する
トラブルを防ぐためにも、ここで紹介する注意点をしっかりと押さえてください。
5-1.ほかの相続人から遺留分を請求される恐れがある
何度も説明しているとおり、起こりうるトラブルの一つが遺留分侵害額請求です。一般的に兄弟姉妹以外の相続人は、以下の額について請求できます。
| 相続人 | 請求できる額 |
| 配偶者のみ、子のみ | 2分の1 |
| 直系尊属のみ | 3分の1 |
| 配偶者と子(一人) | 配偶者も子も4分の1 |
| 配偶者と直系尊属 | 配偶者は3分の1、直系尊属は6分の1 |
遺留分が放棄されない限り、上記の額は請求者に渡すのが原則です。遺留分が請求されることを前提に、なるべく多く現金を遺しておくのが無難でしょう。
関連記事:「遺留分は認めない」と遺言で残せる?遺留分請求を防ぐための対策
5-2.遺言の無効を主張される恐れがある
一人に相続させるといった内容は、基本的には無効事由に該当しません。しかし「遺言は偽造されたものだ」などと、理由をつけて無効を主張する可能性もあります。
こうしたリスクを防ぐには、公正証書遺言を作成するのがおすすめです。証人2人と公証人が関与しているため、相続人たちも無効を主張するのが難しくなります。
5-3.弁護士の立ち会いのもとで作成する
遺言を巡り、相続人同士で争いが生じる可能性は否定できません。こうしたリスクを防ぐには、弁護士からアドバイスを受けながら遺言書作成に取り組むのをおすすめします。
公正証書遺言の場合、弁護士が証人として立ち会うことも可能です。法律のプロが関与しているとなれば、相手も気軽に争おうとしなくなるでしょう。
弁護士の資格を持っていると、税理士登録もできるようになります。相続税の相談もしたい場合は、税理士業務を提供している法律事務所も探してみてください。
6.結果的に相続人が一人になるケースもある
ここまでは遺言書によって相続人が一人だけ指定されるケースについて解説してきましたが、なかには結果的に相続人が一人になるケースも考えられます。それは、以下のようなケースです。
- 法定相続人が一人だけだった
- 一人以外の相続人が相続放棄した
- 一人以外の相続人が相続権を失った
どのような状況が考えられるのか、一つずつ見ていきましょう。
6-1.法定相続人が一人だけだった
遺言書がなくても、法律で定められた相続人(法定相続人)が初めから一人しかいない場合、その人が全ての遺産を相続することになります。
たとえば、被相続人に配偶者も子もおらず、両親やすでに亡くなっている場合で、兄弟姉妹もいない、または先に亡くなっているケースなどが考えられます。この場合、他に相続する権利を持つ人が存在しないため、特別な手続きや遺言書がなくても、結果的に唯一の相続人が全財産を引き継ぐ形となるのです。
戸籍をたどって法定相続人を確定させた結果、一人しかいなかったという状況です。
6-2.一人以外の相続人が相続放棄した
複数の法定相続人がいた場合でも、特定の一人を除く全員が家庭裁判所で「相続放棄」の手続きをおこなえば、結果的に残った一人が全ての遺産を相続することになります。
相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかったとみなされ、プラスの財産もマイナスの財産(借金など)も一切引き継ぎません。たとえば、借金が多い場合や、特定の相続人に遺産を集中させたいという相続人間の合意がある場合などに、相続放棄が選択されることがあります。
全員が相続放棄の手続きを完了すると、放棄しなかった最後の一人が単独で相続します。
関連記事:借金は相続放棄できる?借金と相続放棄の関係や注意点など徹底解説
6-3.一人以外の相続人が相続権を失った
遺言書がない場合でも、特定の一人以外の法定相続人が「相続欠格」や「相続廃除」によって相続権を失った結果、残った一人だけが相続するケースもあります。
相続欠格は、たとえば被相続人を殺害したり、遺言書を偽造したりした場合など、法律上当然に相続権を失う制度です。相続廃除は、被相続人に対する虐待や重大な侮辱などがあった場合に、被相続人の意思にもとづき家庭裁判所の手続きを経て、特定の相続人の権利を剥奪する制度です。
これらにより他の相続人が権利を失うと、結果的に相続人が一人になる場合があります。
7.遺言書によって一人だけが相続することに不満な場合の対処法

最後に、遺言書によって一人だけが相続することに不満な場合の対処法も解説します。もし遺言書の内容に不満がある場合は、以下の対応を検討してください。
- 遺留分侵害額請求をおこなう
- 相続人同士で話し合う
- 家庭裁判所での調停や訴訟を検討する
詳しく解説します。
7-1.遺留分侵害額請求をおこなう
前述したように、遺言書が有効な場合でも、兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者、子、親など)には、法律上最低限保障されている遺産の取り分である「遺留分」があります。
もし遺言書の内容によってご自身の遺留分が侵害されている場合、遺産を多く受け取った相続人に対して、不足している額に相当する金銭の支払いを請求できます。これを「遺留分侵害額請求」と呼びます。
この請求権は、相続の開始と遺留分侵害を知った時から1年以内という期限があるため、早めに意思表示をおこないましょう。
関連記事:相続で遺留分がもらえないときはどうする?具体的な対処法を解説
7-2.相続人同士で話し合う
法的な手段をとる前に、まずは遺産を相続した人を含め、相続人全員で遺言書の内容や遺産分割について話し合う機会を持つことも有効な対処法です。なぜ遺言書の内容に不満を感じるのか、ご自身の希望や状況などを正直に伝え、相手の意向も聞くことで、お互いが歩み寄れる解決策が見つかるかもしれません。
たとえば、遺留分に満たない部分を他の財産で調整してもらったり、特定の遺品を譲り受けたりするなど、裁判外での柔軟な合意を目指すことが可能です。感情的にならず、冷静に話し合いを進めましょう。
関連記事:相続でもめる原因とは?仲の良い家族でも注意したいポイントを解説
7-3.家庭裁判所での調停や訴訟を検討する
相続人間の話し合いで合意に至らない場合や、遺留分侵害額請求に相手が応じない場合には、家庭裁判所での法的な手続きを検討することになります。
まずは「遺留分侵害額の請求調停」を申し立て、調停委員を交えて話し合いでの解決を目指します。調停でも合意できない場合は、「遺留分侵害額請求訴訟」という裁判を起こし、最終的には裁判官に法的な判断をしてもらう流れとなります。
これらの手続きは専門的な知識が必要で、証拠の収集なども重要になるため、弁護士に相談しながら進めるのがおすすめです。
8.まとめ
公序良俗に反しない限りは、遺言書で特定の相続人一人だけに相続させることも可能です。しかし一人に相続させる方法は、ほかの相続人から反感を買いやすくなります。
相続人には遺留分侵害額請求権があることから、財産のすべてが特定の人に渡るとも限りません。どうしても意思を反映させたいのであれば、プロの弁護士に相談したうえで遺言書を作成してください。
弁護士法人池袋吉田総合法律事務所では、遺言書作成や相続に関する無料相談を受け付けています。遺言書に関する問題でお困りの方は、ぜひ当事務所までご相談ください。
このコラムの監修者
弁護士法人池袋吉田総合法律事務所は、相続全般、遺産分割、遺留分、相続放棄、生前対策、遺言作成、事業承継、
相続税など、法律のプロとして幅広い案件を取り扱っています。
初回相談は無料です。一人で悩まず、まずは当事務所へご相談ください。

第二東京弁護士会所属





